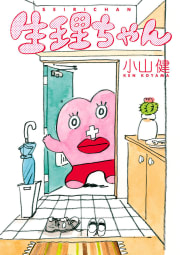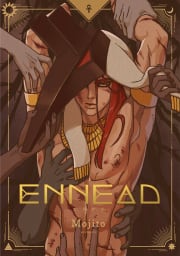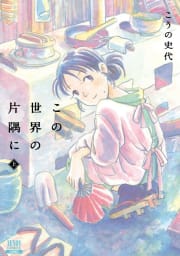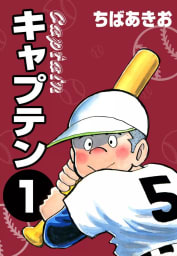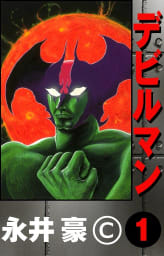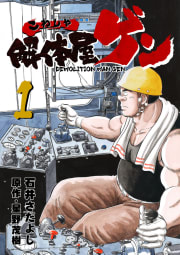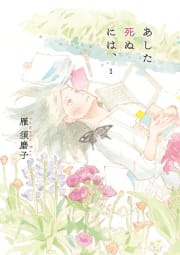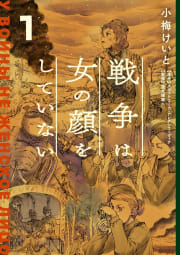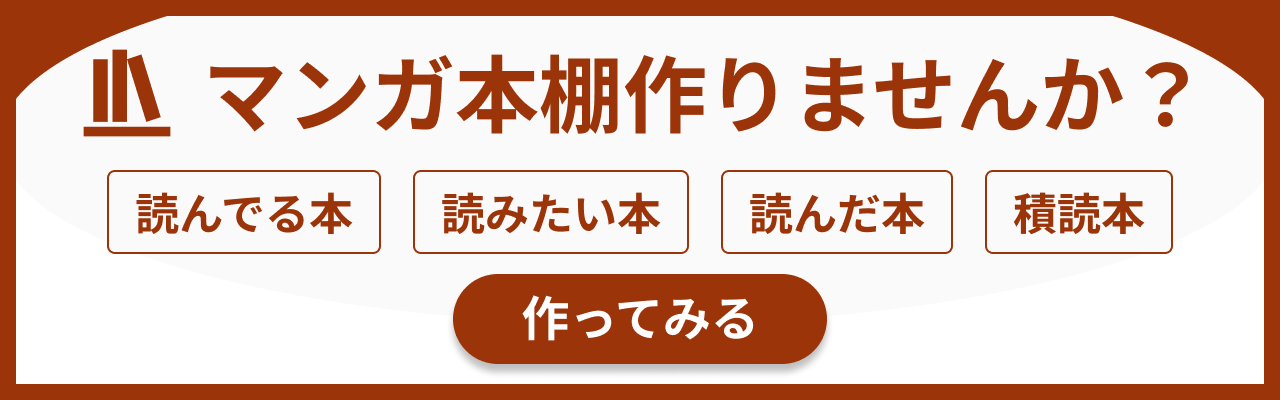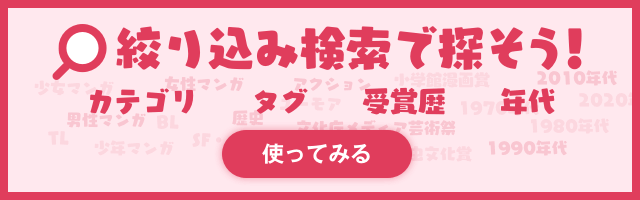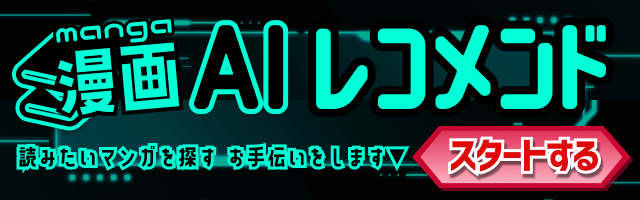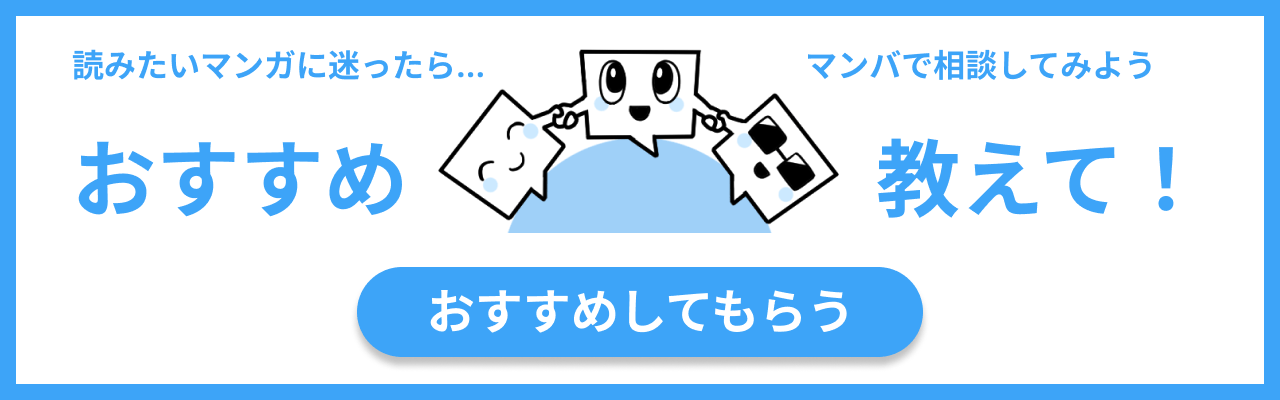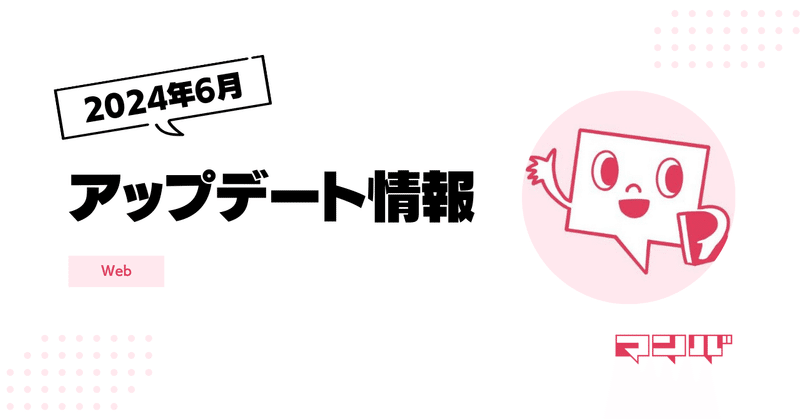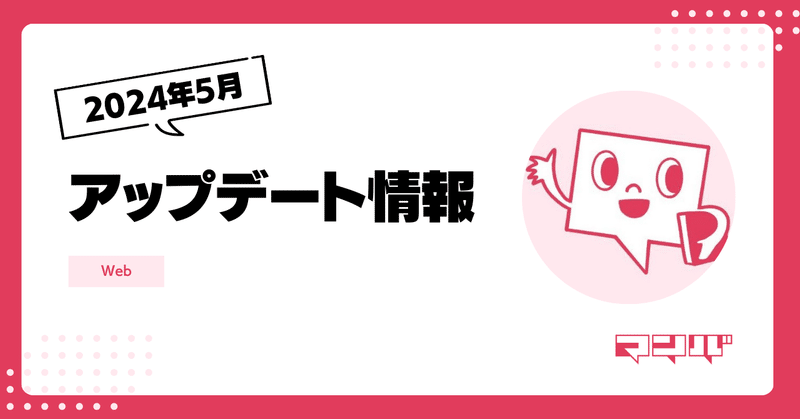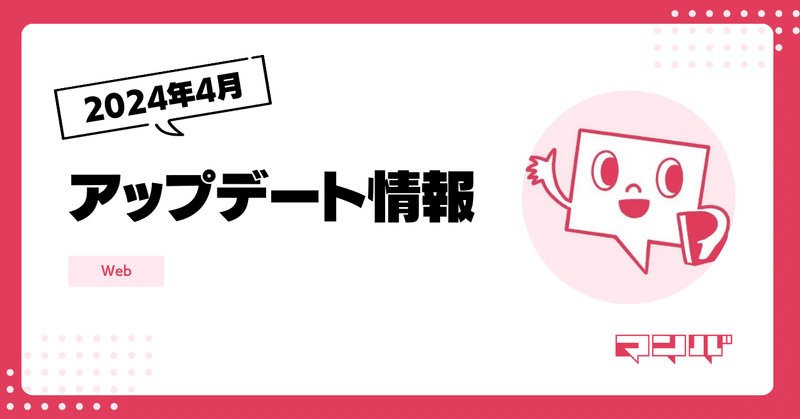せいりちゃん
あらすじ
「大変なのを生理のせいにできないから大変なんです」悩める女性たちの元にも、ツキイチで生理ちゃんはやってくる。イタイ、ツライ、メンドクサイを吹き飛ばすほど、笑って泣けちゃう大傑作!共感の嵐を巻き起こす生理ちゃんが、嬉しい描き下ろしも収録して待望のコミックスに!
生理ちゃんかわいい。
性欲くんと童貞くんのゲスさも好き。
1冊まるまる彼らの作品を読みたいぐらい。
出てくるキャラクターがゆるかわで線が好き。
2巻「小学生と生理ちゃん」
分けられてしまった道がまた交わって、理解し合えればいいなと思った。
いじめや不妊、「人様に迷惑かけない」という呪縛についてや、「わたし」について、生理を交えながらも広いテーマをも含んでいて、読んだあとすこし心が軽くなる。
共感するところも多い。
こだいせんしはにわっと
あらすじ
長野県長野善光寺市に、なんの前触れもなく突如現れた巨大土偶。街を破壊し、阻もうとする人間を排除しながら漸進する土偶を阻止できるのは、そうハニワットしかいない! 『鈴木先生』の武富健治が渾身の筆致で描き出す、超古代伝奇ヒーロー譚!!
きゅうせいしゅ
あらすじ
五十嵐真姫は大学二年生。母の死をきっかけに昔から憧れていたニューヨークに行き、モデルとして生きていこうと心に決めたのだが、モデル事務所から断られてしまった。そんな真姫を意外な人物が救う。カリスマモデルのペトロの推薦を受け、モデル事務所に所属することができたのだ。しかし、ペトロにはある重要な秘密があった。【救世主】他に、【堕天使】【香港遊戯】【アポロン】の全4編。
ほくとのけん
あらすじ
199×年、世界は核の炎に包まれた。破壊され、荒野と化した地球に生き残った人類は、再び暴力に支配された。一滴の水さえも奪い合う時代が到来し、弱者は虐げられるだけの過酷な運命を負わされた。そんな、ある日。一人の若者が水を求めて荒野を歩いていた。彼こそは、肉体に散在する経絡秘孔(ツボ)を突き、内部から相手を破壊するという、一子相伝の暗殺拳「北斗神拳」の使い手、ケンシロウだった。たどりついた村で、ケンシロウは牢に囚われる。牢には、バットという少年がいた。牢番をしていた少女リンは、ケンシロウの優しさに触れ、牢の鍵を渡す。そのとき、村は、豊富な食料と水が目当ての強盗組織「Z(ジード)」に襲われる……。ケンシロウの最初のライバルのシンや、最愛の恋人ユリアも登場。「週刊少年ジャンプ」やTVアニメで爆発的人気を誇り、「おまえはすでに死んでいる」のセリフが流行語にもなった一大格闘巨編、ここに復活!悲哀は、やがて愛へと変わる――。
ぼくのこころのやばいやつ
あらすじ
学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を妄想してはほくそ笑む、重度の中二病の陰キャ・市川京太郎。だが山田を観察する内に、京太郎が思う「底辺を見下す陽キャ」とは全然違うことに徐々に気づいていき…!? 陰キャ男子・京太郎の初めての恋、始まる。陽キャ美少女×陰キャ少年のニヤニヤ系青春格差ラブコメディ!!
ほうかご
あらすじ
ワガママ女子高生、美月の趣味は担任の小林イジメ。だけど全く動じない小林の態度に、美月の不満は爆発寸前! そんなとき、街で絡まれた美月を偶然助けたのは、他でもない小林だった。学校では見せない、大人な小林の魅力に、ハマってしまう美月。小林の家に押しかけて一線を越えてしまったけど、思いもよらない過去の事件が、2人の仲を引き裂く―!?
まんがほんずきのげこくじょう
あらすじ
第三部「領主の養女」アニメ化決定!アニメーション制作:WIT STUDIO「このライトノベルがすごい!」(宝島社刊)殿堂入り!シリーズ累計1000万部突破!(電子書籍を含む)【あらすじ】幼い頃から本が大好きな、ある女子大生が事故に巻き込まれ、見知らぬ世界で生まれ変わった。貧しい兵士の家に、病気がちな5歳の女の子、マインとして…。おまけに、その世界では人々の識字率も低く、書物はほとんど存在しない。いくら読みたくても高価で手に入らない。マインは決意する。ないなら、作ってしまえばいいじゃない!目指すは図書館司書。本に囲まれて生きるため、本を作ることから始めよう!本好きのための、本好きに捧ぐ、ビブリア・ファンタジー。書き下ろし番外編も収録。
えねあど
あらすじ
神を貪るのは誰だ――――遥か遥か昔。「エネアド」と呼ばれる九柱神のうちのひとり、セトの暴政にエジプトの地は疲弊していた。他の神々までセトに頭を下げるなか、まだ神に名を連ねていない若者ホルスが反旗を翻す。傲慢で奔放なセトを玉座から引きずり落とさんと戦いを挑むホルス。二人の関係は次第に執着と欲望を孕んで…!?エジプト神話をもとにした一大叙事詩BLがここに開幕!
あらすじ
主人公・すずは広島市から呉へ嫁ぎ、新しい家族、新しい街、新しい世界に戸惑う。だが、昭和18年から描かれる一日一日を確かに健気に生きていく。戦中の広島県の軍都「呉」を舞台にした戦中を生きる小さな家族の物語。
ぎんがながれぼしぎん
あらすじ
大輔の家に子犬が誕生した。猟師の間で貴重視される虎毛の秋田犬・銀である。猟師である五兵衛の熊犬・リキは、殺人熊・赤カブトと戦い谷底へ転落、消息を絶った。復讐を誓った五兵衛は、生まれて1ヵ月もたたない銀に厳しい訓練をつけ、熊犬として鍛えあげていく。
りへいさんとこのおばあちゃん
あらすじ
「おばあちゃんは、今は一人暮らし。じいちゃんいたけど、せんだって死んだ…。突然ポックリ死んだ」
山間にある素朴で懐かしいちいさな村で、荒物屋を営む、太田利平さんとこの、おしげばあちゃんは、猫のミーコや犬のお杉と、のんびりと、そして賑やかに暮らしています。
人と人との絆を繊細で抒情溢れるタッチで描き、読む者の涙を誘う、優しく切ない珠玉のハートウォーミング・ストーリーズ。すべてのマンガファンのために、遂に待望の電書化!
『利平さんとこのおばあちゃん』とは?
本電子版第1話で、第3回小学館新人コミック大賞佳作を受賞。1970年代後半〜1980年代後半にかけて10年間、小学館『ビッグコミック』とその増刊号にて連載された人気作。過去に小学館、エンターブレインより単行本が出版されている。このたび著者監修のもとエピソードを厳選し傑作選としてマンバより電子書籍化された。
名無し
きゃぷてん
あらすじ
弱小野球部のキャプテンと部員達が、ひたすら努力を重ねて最強チームに成長していく熱血スポーツコミック。墨谷二中に転校してきた谷口タカオ(たにぐち・たかお)は、野球部の練習に参加しようと、以前いた学校のユニフォームに着替える。それが野球の名門・青葉学院のユニフォームだと気付いた野球部員達は、谷口を凄い大物選手だと思い込んでしまう。しかし青葉学院にいた頃の谷口は、パッとしない二軍の補欠選手で……!?
さきがけおとこじゅく
あらすじ
過激なスパルタ教育を施す「男塾」を舞台に、剣桃太郎(つるぎ・ももたろう)を中心とした男気溢れる塾生達の活躍を描いたバイオレンスアクション。行き場を無くした全国の不良少年達を集めて、過激すぎる軍国主義教育を施す男塾。その一号生筆頭である桃太郎は教官に目を付けられて、民家があっても破壊しながら突き進む男塾名物の直進行軍で、直進の先にあるヤクザの組事務所へたった一人で突撃するように命令されて……!?
名無し
さいきょうでんせつくろさわ
あらすじ
「オレが求めているのは……オレの、オレによる、オレだけの……感動だったはずだ……!!」――。うだつが上がらない中年男が、不器用ながらも様々な修羅場に奮闘して、男気ある人間へと成長していく人情コメディ。目標もなく働き続け、年齢を重ねてきた土木作業監督・黒沢(くろさわ)は、ふとしたことで自分の生き方に不安感を覚える。そして、誰にも祝福されず44歳の誕生日を過ごした孤独な黒沢は、人望が欲しいと強く願って……!?
なまこデラックス
あらすじ
ときは飛鳥時代前夜、権勢を誇る蘇我氏の後継者たる毛人は14歳。父に連れられて出仕した朝廷で、10歳の少年、厩戸王子と出会う。毛人と厩戸、ふたりの激動の物語が、いま始まる。数多くの貴重なカラー原稿、トビライラスト、予告カットなどを完全再現。日本の漫画界を代表する山岸凉子の最高傑作「完全版」!
でびるまん
あらすじ
地球の先住民族、デーモン族の存在を知ってしまった不動明と飛鳥了はデーモン族の侵略に対抗するために、悪魔と合体しようとするが…
こわしやげん
あらすじ
借金まみれで自堕落な生活を送る、孫請け解体業者の朝倉巖(通称ゲン)。しかしゲンは、世界を股にかけて活躍した爆破解体技師だった。その噂を聞きつけた大手ゼネコン社員の慶子は、ゲンをもう一度表舞台に引っ張りだそうと画策する。ゲンと慶子の出会いを描く「爆破解体」、家を丸ごと移動させる曳き家を描いた「曳き家のロク」、自殺志願のクレーン技術者ヒデが登場する「初仕事」他。
ふじこえふふじおえすえふたんぺんぱーふぇくとばん
あらすじ
藤子・F・不二雄のSF短編112話を全8巻に完全収録した“PERFECT版”が登場! 鋭い風刺精神を存分に発揮した「藤子美学の世界」にどっぷり浸かれる作品集! ある日突然、ある町のスーパーマーケットのむすめが、スーパーマンになってしまった。「女の子のくせに、えらいものになってくれたね」と嘆く両親だったが、町内会長がやって来て、「スーパーマンの店と大はやりになるだろう」と言ったことから、両親は大喜び。「がんばってスーパーマンをやりなさい」と言われるものの、むすめは何をしたらいいのかわからず……(第1話)。乗っていた惑星間航行ロケットが故障し、生き残ったのはオレ1人。水、食料ともに底をついたが、救助艇がくるのは23日後だという。やっとの思いで不時着した地球型の惑星。そこには低い段階ながらも文明があり、ミノアというかわい子ちゃんとも出会うことができた。ところが、その文明というのが実は……(第2話)。目次 第1話 スーパーさん 第2話 ミノタウロスの皿 第3話 ぼくのロボット 第4話 カイケツ小池さん 第5話 ボノム=底ぬけさん= 第6話 ドジ田ドジ郎の幸運 第7話 じじぬき 第8話 ヒョンヒョロ 第9話 自分会議 第10話 わが子・スーパーマン 第11話 気楽に殺ろうよ 第12話 アチタが見える 第13話 換身 第14話 劇画・オバQ 第15話 イヤなイヤなイヤな奴
あしたしぬには
あらすじ
ものすごく共感できる、老若男女におすすめの傑作です! 四十代女性が直面する体調の変化や人間関係のあれこれに、笑ったり涙したりしつつ うなずきすぎて、私は首が太くなりました……!――三浦しをん、絶賛!! 歳をとるのは怖いですか? ~切実に生きる女子たちの心に寄り添い、そっと背中を押してくれる本。~ 20代ほどがむしゃらじゃない。30代ほどノリノリじゃない。40代で直面する、心と身体の変わり目。立ちはだかる40代の壁。突然の病気、更年期障害、取れない疲労、働き方の変化、お金の不安、これからの人生プラン……私のあしたはどうなるの!? 本奈多子(ほんな・さわこ)、42歳、独身。映画宣伝会社に勤め、ハードワークをこなす日々。ある夜突然、心臓の動悸が止まらず、体が冷たくなって……。もしかして私、更年期障害かもしれない!? 苛々したり、涙腺がゆるんだり、おばさんと言われて悲しくなったり。心身の変化に戸惑いながら、迷いながら、私たちは、あしたを生きる。
ひきだしにてらりうむ
あらすじ
ようこそ、ショートショートのワンダーランドへ。笑顔と涙、驚きと共感。コメディ、昔話、ファンタジー、SF……新進の気鋭、九井諒子が描く万華鏡のようにきらめく掌編33篇。―Web文芸誌マトグロッソでの、2011年8月~2012年12月の約1年半の連載分全篇のほか、「えぐちみ代このスットコ訪問記トーワ国編」「神のみぞ知る」、描き下ろし作品も収録。
こどくのぐるめしんそうばん
あらすじ
個人で輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が一人で食事をするシチュエーションを淡々と描くハードボイルド・グルメマンガ。井之頭五郎は、食べる。それも、よくある街角の定食屋やラーメン屋で、ひたすら食べる。時間や社会にとらわれず、幸福に空腹を満たすとき、彼はつかの間自分勝手になり、「自由」になる。孤独のグルメ―。それは、誰にも邪魔されず、気を使わずものを食べるという孤高の行為だ。そして、この行為こそが現代人に平等に与えられた、最高の「癒し」といえるのである。
名無し
ぽけっともんすたーすぺしゃる
あらすじ
●あらすじ●マサラタウンの超元気少年、レッドは町いちばんのポケモントレーナーだ。ひょんなことからオーキド博士に気にいられたレッドはポケモン図鑑をもらい、図鑑の完成をめざして旅に出る。同じくポケモン図鑑の完成をめざすグリーンや、カスミとの出会いをとおして、少しずつ成長していくレッド。そして、かれらの前に立ちはだかる悪の秘密結社ロケット団。レッドの行く手には、なにが待ちかまえているのだろうか!? 超人気ゲーム『ポケットモンスター』の冒険と感動をまんが化! ポケモンの息づかいが聞こえてくるぜ!! ▼第1話/VSミュウ ▼第2話/VSゴーリキー ▼第3話/VSガルーラ ▼第4話/VSピカチュウ ▼第5話/VSイワーク ▼第6話/VSギャラドス ▼第7話/VSサイドン ▼第8話/VSスターミー ▼第9話/VSオニドリル ▼第10話/VSビリリダマ ▼第11話/VSエレブー ▼第12話/VSカビゴン ▼第13話/VSコダック ▼第14話/VSアーボック
あらすじ
<カラー5ページ増量!!>ダメ男・坂本拓郎が30歳の誕生日に出会った運命の彼女。それはバーチャルリアリティーのゲーム世界の中で生活する、AIキャラクター・月子だった!「現実を直視しろ。おれ達にはもう仮想現実しかないんだ」友人にも背中を押され、どんどん月子に惹かれていく拓郎だったが‥‥‥月子には他に好きな人がいる? もしかして現実世界が見えている!?謎だらけの彼女の存在には、この世界の秘密が隠されていた……!!※本商品は過去に発行されていた商品の収録内容から変更はありませんので(カラー増量ページ除く)、重複購入にご注意ください。
せんそうはおんなのかおをしていない
あらすじ
「一言で言えば、ここに書かれているのはあの戦争ではない」……500人以上の従軍女性を取材し、その内容から出版を拒否され続けた、ノーベル文学賞受賞作家の主著。『狼と香辛料』小梅けいとによるコミカライズ。