時は大正時代。炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は、家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する。唯一生き残ったものの、鬼に変貌した妹・禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を討つため、炭治郎と禰豆子は旅立つ!! 血風剣戟冒険譚、開幕!!
主人公・すずは広島市から呉へ嫁ぎ、新しい家族、新しい街、新しい世界に戸惑う。だが、昭和18年から描かれる一日一日を確かに健気に生きていく。戦中の広島県の軍都「呉」を舞台にした戦中を生きる小さな家族の物語。
少女のあずみを含む10人の子供達が、人里離れた場所で秘かに刺客として育てられていた。そして、彼らは爺の言葉をすべて正しいこととして疑うことを知らない、精鋭の刺客として育った。ある日、爺からいよいよ外界に出る時になったと告げられる。しかし、その前にこれまでの修業の総仕上げとも言うべき凄まじい試練が待っていた!
ロンドン警視庁の犯罪資料館「黒博物館」に展示された“かち合い弾”と呼ばれる謎の銃弾。ある日、それを見せてほしいという老人が訪れたとき、黒衣の学芸員は知ることになる。超有名な「お嬢様」と、「もうひとり」が歴史的大事件の裏で繰り広げた、不思議な冒険と戦いを…! 藤田和日郎の19世紀英国伝奇アクション超待望の第2弾、ここに開幕!!
1755年、この年ヨーロッパの3つの国で、やがてフランスのベルサイユで宿命的な出会いを持つことになる3人の人間が生まれる。スウェーデンの上院議員の長男として生まれたハンス・アクセル・フォン・フェルゼン、フランスの将軍家の末娘として生まれたオスカル・フランソワ・ド・ジャルジュ、そして、オーストリア、ハプスブルグ家の皇女として生まれたマリー・アントワネット!!少女漫画史上に輝く大傑作、ついに登場!
『不死身の杉元』日露戦争での鬼神の如き武功から、そう謳われた兵士は、ある目的の為に大金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海道へ足を踏み入れる。そこにはアイヌが隠した莫大な埋蔵金への手掛かりが!? 立ち塞がる圧倒的な大自然と凶悪な死刑囚。そして、アイヌの少女、エゾ狼との出逢い。『黄金を巡る生存競争』開幕ッ!!!!
花火師である父親と2人暮らしの少年・花菱烈火は、「忍者」に強い憧れを抱く高校1年生。地元では負けナシと恐れられている同級生・石島土門をも一蹴してしまう烈火は、日頃から「ケンカでオレに勝ったらその人の『忍』になる」と公言しているものの、いまだに自らの君主を見つけられずにいたが…。400年の時を超えた因縁を巡る戦いが幕を開ける!炎を操る烈火が繰り広げる、長編忍術スペクタクル!!
現代の料理人・ケン。彼が目を覚ますとそこは戦国時代だった。京で評判の料理の噂を聞きつけた信長は、強引にケンを自分の料理人にするが…!?戦と料理が織りなす前代未聞の戦国グルメ絵巻!コラム&レシピ「戦国めし」も必見!
【カラーページを収録したデジタル特別編集版!】紀元前11世紀の中国、殷(いん)の時代末期。崑崙山脈(こんろんさんみゃく)の仙人・太公望(たいこうぼう)は、悪しき仙人・道士を封印する「封神計画」という任務を受ける!殷の皇帝・紂王(ちゅうおう)を誘惑して暴虐の限りを尽くす仙女・妲己(だっき)を、太公望は真っ先に封神しようとするが…!?
江戸の世、天下人・徳川家康は甲賀(こうが)と伊賀(いが)という忍法の二大宗家を相争わせ、十人対十人の忍法殺戮(さつりく)合戦の結果どちらが生き残るかによって、三代将軍の世継ぎ問題を解決させることにした。だが憎み合う両家にあってそれぞれの跡取り、甲賀弦之介(げんのすけ)と伊賀の朧(おぼろ)は深く愛し合っていた――。時代に翻弄(ほんろう)される忍術使いたちのあまりにも過酷な運命の幕が上がる!!
登場人物/ムジナ(修行中の忍者。忍者としての生き方に悩む)ゴキブリ(ムジナの父親。自分が生き抜くためダメ忍者を装っている)シロベ(下忍。首領の駒としての生き方に疑問を持ち里を抜ける)あらすじ/皆からゴキブリと呼ばれるダメ忍者の親父をもつムジナ。「この親にしてこの子あり」の如く、修行中のムジナもぱっとしない。ゴキブリは、首領のために死ぬ生き方の悲しさを秘術とともにムジナに教え、後日、任務中に囮として使われ死ぬ。ゴキブリの妻・アヤメは復讐のために首領に近づく。以前から、首領のために死ぬ生き方に疑問を持っていたシロベが里を抜け出す。このシロベの始末をムジナが所属する組に命じられた。死んだかに見せかけたシロベを発見したムジナ。口封じのためにシロベに殺されそうになり、追いつめられたムジナは、父・ゴキブリに教えられた秘術を使おうとする。▼第1話/鎌鼬(かまいたち)▼第2話/鮟鱇(あんこう)▼第3話/でんでん太鼓▼第4話/秘術▼第5話/月▼第6話/馬追虫(うまおいむし)▼第7話/抜け忍▼第8話/察気術(さっきじゅつ)▼第9話/鯣(するめ)▼第10話/糞(くそ)▼第11話/陰(ほと)▼第12話/猿(さる)▼第13話/簪(かんざし)▼第14話/死装隠れ▼第15話/再び秘術◆その一/手裏剣◆その二/忍び刀登場人物/ムジナ(卍衆の忍び、下忍の中でも劣等生)陣内(首領の息子、ムジナの友人)ゴキブリ(ムジナの父親、出来の悪い下忍)
戦国時代。武士・醍醐景光(だいご・かげみつ)は己の天下取りという野望のために、わが子を48体の魔物に差し出した。体の48か所を奪われ、不思議な能力を持って生まれた百鬼丸(ひゃっきまる)は、妖怪から自らの体を取り戻すため旅に出るが……。 <手塚治虫漫画全集収録巻数>◦MT147「どろろ」1巻収録 ◦MT148「どろろ」2巻収録<初出掲載>◦『どろろ』 少年サンデー 1967年8月27日号~1968年7月22日号 ◦『どろろ』 冒険王 1969年5月号~10月号
すべての“風呂”は、“ローマ”に通ず。「マンガ大賞2010」と「第14回手塚治虫文化賞短編賞」をW受賞、実写映画(主演:阿部寛)も記録的な大ヒットとなった超ベストセラー・爆笑コミック! 紀元前128年、第14代皇帝ハドリアヌスが統治し、かつてない活気に溢れているローマ。すべてに斬新さが求められるこの時代、古き良き浴場を愛する設計技師のルシウス・モデストゥスは、生真面目すぎる性格が時代の変化に合わず、職を失ってしまう。落ち込むルシウスは友人に誘われた公衆浴場から、突然現代日本の銭湯にタイムスリップしてしまい……!?
山田誠也、のちに「忍法帖」シリーズでその地位を確立する大作家・山田風太郎は、昭和20年、医学生として東京にいた。時は太平洋戦争末期、同世代の若者は、みな戦地へ。しかし体調不良で召集を見送られた誠也は、お国のために体を張れない葛藤を抱えながら、日々を送っていた。そんな彼が当時の世間を、そして日本をどう見ていたか。克明に綴られた日記を、令和の今だからこそ、コミカライズ。個性派漫画家・勝田文がユーモアを交えて描く風太郎と昭和20年は、必読ものです!
戦艦「大和」を阻止せよ!!! 日本の未来を1人の数学の天才が変える!? 時は1933年。日本海軍の中枢・海軍省の会議室で、次世代の旗艦を決める新型戦艦建造計画会議が開かれ、2つの陣営が設計採用を争う事に。これからの海戦を見据え、高速の小型戦艦を打ち出す“航空主兵主義”派に対し、海軍内で権力を握る“大艦巨砲主義”派の計画は、世界でも類を見ない超巨大戦艦の建造だった――!!
『沈黙の艦隊』『ジパング』に続く、かわぐちかいじの新軍事エンターテインメント第1集!! 20XX年、尖閣諸島沖で海上自衛隊と中国海軍が衝突!! 戦闘は回避したものの、危機感を募らせた日本政府は、最新鋭戦闘機を搭載した事実上の空母「いぶき」を就役させ、新艦隊を編成――――!!! 艦長は、空自出身の男・秋津―――。
ちょっとした超能力が使えるのが取り柄の南丸こと、ナン丸はある日、知り合いでもない民俗学の教授・丸神から呼び出しを受けた。だが丸神は調査のため「丸神の里」へ行ったきりで戻っておらず、残された研究生からは「教授とナン丸は、同じルーツを持つらしい」と告げられ、心当たりを尋ねられた。だが何も知らない――。いっぽう「丸神の里」東北の丸川町では、殺害方法のわからない猟奇事件が起きた。失踪した丸神教授の研究内容と足取りを追って、丸神ゼミとナン丸は「丸神の里へ」おもむくが…。
「その生き血を飲めば永遠の命を得ることができると言われている……」。「永遠の命」をテーマに、手塚治虫が生涯にわたって描き続けたライフワーク作品「火の鳥」シリーズがついにはじまる! 第1巻には「騎馬民族渡来説」を取り入れ、独自の解釈による日本神話を描いた「黎明編」に加え、手塚治虫エッセイ集より抜粋した「『火の鳥』のロマン」を掲載。 <手塚治虫漫画全集収録巻数>・『火の鳥』黎明編(手塚治虫漫画全集MT201~202『火の鳥』第1~2巻収録) ・『「火の鳥」のロマン』(手塚治虫漫画全集別巻MT389『手塚治虫エッセイ集』第3巻収録) <初出掲載>・『火の鳥』黎明編 1967年1月号~11月号 COM連載 ・『「火の鳥」のロマン』1983年1月号 「旅」掲載
ちさかあや(郷土を愛する実力派)×原恵一郎(漫画家兼農家) 長野県在住コンビが贈る、信州・幕末農業ドラマ!! 人の向上心が農業の発展を促す! 農政を司る郡奉行・目白逸之輔の周囲にはいつも農事にまつわる無理難題と悲喜こもごもが……
いまから三千五百年ほどの昔、インダス川のほとりに住むアリアン人はバラモンを頂点とする身分制度を築いていた。そんな中、物語の主人公であるシッダルタが誕生する少し前、奴隷出身のチャプラはコーサラ国の将軍を助けたことがきっかけで彼の養子となる。そして、出自を隠して権力の座を狙うが、チャプラもやはり身分制度の呪縛からは逃れることができなかった……。ブッダが生きた時代とその生涯を描いた大作がここに始まる! <手塚治虫漫画全集収録巻数>手塚治虫漫画全集MT287~288『ブッダ』第1~2巻収録 <初出掲載>1972年9月号~1978年7月号 希望の友/1978年8月号~1979年12月号 少年ワールド/1980年7月号~1983年12月号 コミックトム連載
70年代に少女たちの間で空前の「はいからさん」ブームを巻き起こしたラブコメの名作が、装いも新たに登場!! 時は大正、花村紅緒、17歳。明るく元気いっぱいのハイカラ娘。恋も結婚も自分で選びたいと夢見ていたある日、伊集院忍という許嫁の陸軍少尉が現れる! 自分のじゃじゃ馬ぶりをいつも面白がる笑い上戸の彼が気に入らない紅緒は、この結婚を破談にしようとして!? 2017年に劇場版新作アニメも公開予定!
最強の忍として畏れられ、抜け忍として囚われていた画眉丸は、打ち首執行人の“山田浅ェ門佐切”から無罪放免になる為の条件を突きつけられる。その条件とは極楽浄土と噂の地で「不老不死の仙薬」を手に入れること…!! 生死を悟る忍法浪漫活劇、開幕――!!
父を殺し、母を攫(さら)った剣客集団『逸刀流(いっとうりゅう)』に復讐を誓う少女・浅野凜(あさのりん)は、「百人斬り」の異名を持ち、己の身体に血仙蟲(けっせんちゅう)という虫を寄生させることで不死の肉体を持った剣士・万次(まんじ)を用心棒として雇い、逸刀流の統主である宿敵・天津影久(あのつかげひさ)を追う旅を始める――。




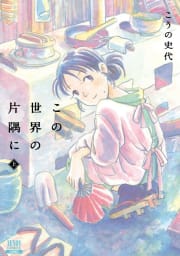





















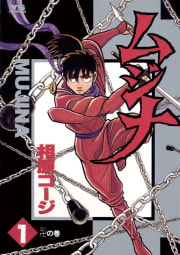
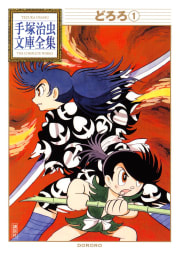




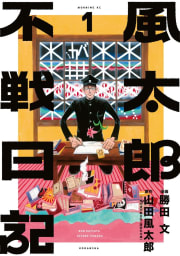

















私は、幼い頃から漫画が好きだった。定かな記憶ではないが、初めて読んだ漫画は星のカービィとポケモンの四コマ劇場だったと思う。その後も、週刊少年ジャンプの漫画を中心に数々の作品に読み触れていった。 私は週刊少年ジャンプを買ったことがなかった。読み始めた小学生の頃から、読むのをやめた高校生の頃までずっと、隣に住む従兄弟のお兄さんに貰って読んでいたのだ。読み始めた頃には、アイシールド21でまだデスマーチが行われていたし、愛染もまだ良い人だと思っていた。テコンドーを題材にした漫画がすぐに打ち切りになってしまったり、リボーンやムヒョ、銀魂、SKET DANCE、ToLOVEる等等の作品が輝きを放っていたりと、沢山の漫画に囲まれていたあの頃を懐かしく思う。成人した今でも漫画は好きで、継続して読んでいる作品も少なくないが、週刊少年ジャンプの世界はもう私の知るところにはなくなってしまっていた。 鬼滅の刃を読もうと思ったのは別に奇跡でも必然でも数奇な巡り合わせでも何でもない。私がこの作品を読み始めた時には既に19巻まで刊行され、TVでは社会現象的な人気と報道されるほどの一大ムーブメントな作品として周知されていた。情けない話だが、私という人間は天邪鬼で人気で話題の作品ほど読むことを躊躇い、敬遠する。いつからこんな厄介な人間性になったのか…… 連休を迎える前、職場の後輩くんが「もうすぐ完結するかも」と、教えてくれたことで今が丁度良い頃合いかもしらんと思い、この度鬼滅の刃を読むに至ったのだ。 私が漫画を読んで泣いたのはこれが二回目だった。 この作品は、鬼狩りと呼ばれる鬼殺隊の青少年たちが、家族や友人の仇となる鬼を殲滅するまでのお話で、各登場人物が信念を胸に文字通り命懸けで鬼に立ち向かっていく。 3巻ほど読み終えた時の印象は、「サンデー作品っぽい」というところだった。想起したのは犬夜叉とうしおととら(こちらは未読)で、"妖怪奇譚"モノという印象を受けた。心地よいコメディ調、可愛らしいデフォルメ顔、インフレを起こさない"考える戦い方"に惹き込まれていった。 少年漫画から暫く距離が空いていた私がこの作品で感じたのは、"敵が強すぎる"ということ。ONE PIECEのアラバスタ編のように味方陣営、敵陣営ともに一人ずつが各人を相手に戦っていくスタイルに馴染みが深かった私は、「上限の鬼強すぎるぞ……」と、登場人物同様に絶望した。鬼滅の刃の戦いは基本的に鬼の首を斬り落とすことに注力して進んでいく。ただ、鬼が強すぎてまぁ斬れない斬れない。そこで現れるのが心強い味方。それも一人じゃなく二人。場合によっては何人でも味方が駆けつけて共闘してくれるのだ。まさに物量作戦!と思ったが、そんな糞みたいな冗談では片せないほどにこの作品のキャラクター達は生命力に溢れていて、強く優しい。どんなにボロボロになっても折れることなく進み続ける。弱きを助け悪しきを挫く彼らのその姿は、私がかつて憧れたジャンプヒーローそのものだった。 主人公・炭治郎は真っ直ぐでクソ真面目でとにかく優しい心の綺麗な少年。共に闘う仲間たちは勿論、命のやり取りをした鬼でさえも、炭治郎の温かな優しさに触れてしまえば、忘れていた大切なことを思い出してしまうのだ。その優しい炭治郎もまた、様々な人の優しさに助けられ、自らを奮い立たせ、どんな窮地でも諦めることを選ばなかった。誰かに守って貰ったように、自分も誰かを守る。優しさの連鎖は絶ち切れることなく繋がっていく。数珠繋ぎになり循環し、滅ぶことはない。 ONE PIECEのチョッパーの出自の話で泣いたのは小学生の頃のこと。齢二十五にもなった自分が漫画を読んで何度も泣いてしまうとは思わなかった。そのことに気恥ずかしさもあるが、少し嬉しくも感じた。素晴らしい少年漫画は、次話を渇望させる。コミックスで読み始めた私が、ジャンプ+のアプリで本誌を購入してまで続きを読んだように。サラリーマンの自分が月曜日を待ち遠しく感じるなんて有り得なかった。人生で最初で最後になるかもしれないが、私は週刊少年ジャンプを買いに行った。 ありがとう鬼滅の刃。 心を燃やせ。赫い刃を。折れない心を。 (204話で完結と思ったら205話で完結だったので結局二回買うことになりました)