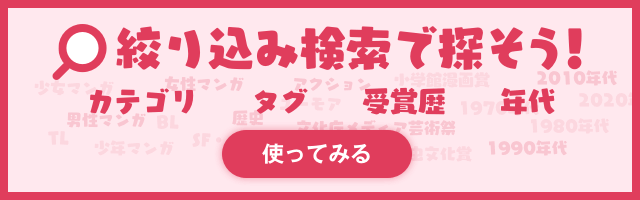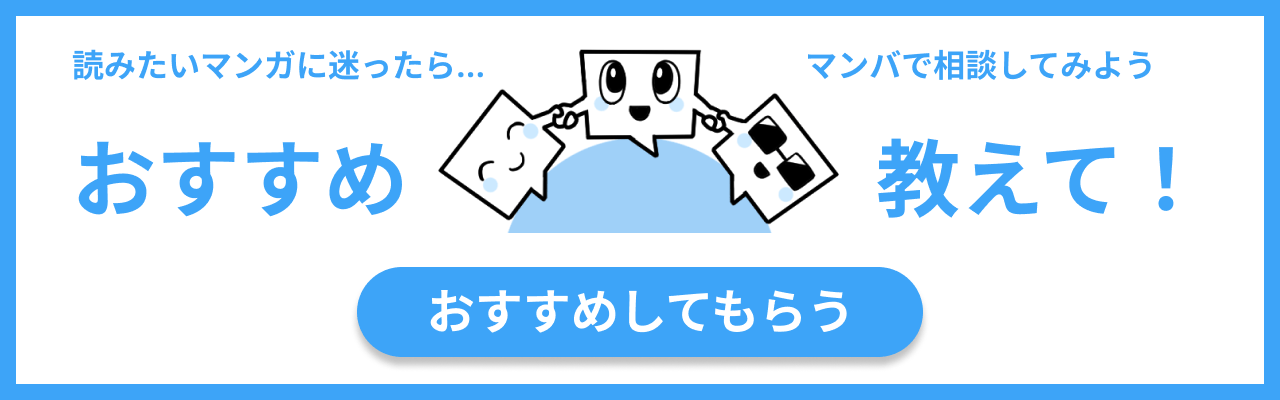マンガの編集部に赴き、編集者が今おすすめしたいマンガやマンガ制作・業界の裏側などを取材する連載企画「となりのマンガ編集部」。第14回は、小学館『ビッグコミックオリジナル』(以下『オリジナル』)を訪ねました。編集長の菊池さんと、若手編集部員の鈴木さんにお話をうかがいました。共に最初はマンガ編集者ってつまらない、と思っていたというお二方がどのように編集者の醍醐味に至ったのか? また、皆さんの中にも『オリジナル』という雑誌のイメージがあるかと思いますが、そのイメージも大きく変わるであろう内容です。ぜひお楽しみください。
取材:マンガソムリエ・兎来栄寿
――最初に、現在と過去の担当作品を含めた自己紹介をお願いします。
菊池 私は『オリジナル』では編集長で担当は持っていないんですけれども、元々『週刊ポスト』というところに1年半ぐらいいたんです。それから『ヤングサンデー』という雑誌がありまして、そこに行きました。担当した作品は『ザ・ワールド・イズ・マイン』、『いぬ』、『マイナス』などです。
六田登さんという方が『ICHIGO[二都物語]』というマンガを描いていて、それを担当させていただいたことで「漫画家ってすごいんだな」という風に身にしみて感じたところがありまして。もうひとり自分がすごく影響を受けたのが青木雄二さんです。『ナニワ金融道』を当時『モーニング』で描かれていて大好きで、頻繁に遊びに行かせていただいて。ある意味、弟子みたいなところがあって、非常にかわいがっていただきいろいろなことを教えていただきました。なので、自分としては青木さんと六田さんに影響されてマンガに入ったようなところがあります。
『ヤングサンデー』には大体10年ぐらいいて、その後『ビッグコミックスピリッツ』(以下『スピリッツ』)に異動しまして山本英夫さんの『ホムンクルス』、柏木ハルコさんの『花園メリーゴーランド』、あと私は花沢健吾さんの最初の担当で『ルサンチマン』などを担当しました。『ボーイズ・オン・ザ・ラン』は別の人がやっていたんですけど、『アイアムアヒーロー』の立ち上げをやりました。
『スピリッツ』も10年ぐらいいまして、その後は『ビッグコミックスペリオール』(以下『スペリオール』)へ異動になり、昨年の秋まで10年ぐらいいてそのうちの9年くらい編集長をしていました。直接の担当としては押見修造さんの『血の轍』をやっていました。一昨年の秋に『オリジナル』に異動になりまして、現在に至るという感じです。
鈴木 自分は入社して今6年目で最初は『スピリッツ』に配属になりました。初めはサブでいくつかの作品に付いたんですけど、最初が『二月の勝者』という中学受験のマンガで、その後『リボーンの棋士』という将棋マンガの担当になりました。『アフロ田中』シリーズも一時期担当させてもらったのと、あとはグラビアもやったりしていました。
『リボーンの棋士』が終わって新連載を作らなきゃいけないということで結構頑張って『路傍のフジイ』という新連載が始まったんですけど、それが立ち上がった瞬間にちょうど『オリジナル』へ異動になりました。『オリジナル』では、最初『昭和天皇物語』と『オリジナル増刊』でカレー沢薫さんの『わたしの証拠』、そして『釣りバカ日誌』を引き継いでいます。また、1月発売号から『父を怒らせたい』という新連載を始めています。
――お二方が編集者になられたきっかけを教えてください。
菊池 『GORO』というグラビアとマンガの折衷みたいな、『週刊プレイボーイ』のような雑誌がありまして、出版社自体はそこでやりたくて入ったんです。その後、いろいろあって『ヤングサンデー』に来た当時はマンガの編集って何をやるのか全然分からなくて、もう単純に作家さんが描いたものを持ってきて入稿するだけで、何が面白いんだろうと思ってたんですよ。もう会社を辞めようと思って。バブルの残り香漂う時代だったんですけど、本当にまさに辞めようと上司に言おうとした日の会議で、「お前、出張でモンゴル行ってこい」という話になって。「それは良いな」と思って(笑)辞めずに済んだんですけど。
そうこうしているうちに、先ほど挙げた六田登さんという漫画家さんがいらっしゃって。当時『ヤングサンデー』は隔週だったんですけど『ICHIGO[二都物語]』を、週刊で『スピリッツ』の『F』と『サンデー』の『バロン』をやってらっしゃって。でも、六田さんは筆が遅い方なんです。なので、木曜日の夜ぐらいから六田さんの家に泊まりこんでいるんですね。金曜はまるまる潰れて土曜日の深夜24時ぐらいに上がるんです。そのままタクシーで印刷所へ直行しないと落ちるという、そういう人でした。すぐ前にテニスコートがあったんですが、当時は20代で若かったですから、土曜日もまるまる潰れてるときに呑気にテニスの「ポーン」という音とかが聞こえてくると、「六田、死ねぇぇ!!」とか思っていたんですけど(笑)。でも、原稿が上がると、なんだか全部許せるみたいな。本当にすごい原稿が上がってくるんですよ。
もう1人、当時の上司に好きな漫画家のところに誰でも良いから会いに行けと言われて、青木雄二さんのところに行ったらやっぱり非常に個性的な方で。本当に天才と言っていいと思うんです。40過ぎでデビューされて、腱鞘炎で体ボロボロになりながらずっと描いてらっしゃったところもすごいんですけど、人生経験もすごくて物の見方とかそういうところもユニークで。
漫画家ってすごいなというのを青木さんと六田さんで感じて、これは面白い仕事だなっていうことに気づき始めたと。もう60近いですが、自分が本腰を入れてマンガ編集として人生を送ってきたのはそのおふたりがきっかけだったなと思います。
鈴木 学生時代、すごく家が貧乏だったので、学費を稼がないといけなくて、WEBメディアの編集部でほぼフルタイムで2年間くらい働いてたんです。そのときにマンガの記事がとても伸びるというのがあって。それまでは友達の家で『ONE PIECE』を読んでいたりするくらいでした。小説が好きで本は読んでいたんですけど。でも、仕事になるからちょっとマンガも読もうかなという感じでいろいろ読んでみたら結構面白くて。特にそのとき僕は『スピリッツ』がすごく良い雑誌だなと。当時は『アオアシ』はもちろん『闇金ウシジマくん』もあって、あと『恋は雨上がりのように』や『スローモーションをもう一度』という作品なんかもすごく好きでした。こんなに面白いマンガがたくさん載っていて全ページすごく面白いのに数百円で買えるってすごい雑誌だなというのがあって。
一応、その編集部に就職できるということになったんですけど、ちょっとマンガも面白そうだし受けておきますとやっていたらたまたま受かって。一応マンガ志望でという形で最初は『スピリッツ』にトントン拍子で入れてもらったんですけど、全然思ったより面白くなかった(笑)。
でも、それは仕事に対して自分の向き合い方が全然わからなかったからで、やらなきゃいけない言われた仕事が大量にあるし、できなかったら怒られるし、メンタルは強い方じゃなかったんで結構病んじゃったんですよ。とはいえ年次が上がっていくにつれて、ひとりで作家と向き合わなきゃいけなくなっていって。
あんまり面白いって思えないネームが上がってきたときに「良いですね」みたいなことを言ってしまったことが何回かあったんです。めちゃくちゃ頑張って描いてもらったし、打ち合わせだって本気でやったし、それで上がってきたネームに対して面白くないって言えないな、悪いな、みたいな気分でいたんです。でも、何かどこかしら引っ掛かっていて、面談で菊池にそのことを打ち明けたんですよ。要は初めて立ち上げた作品で、たまたまタイミングが良くて立ち上げられたけど、正直そこまで面白いと思ってない、ということを言ったときに「それは駄目だ」と本当に淡々と言われて。やっぱりそれは心のどこかでは自分でも思っていたので、それは駄目なんだと。
先ほど言った『リボーンの棋士』が終わった後の新連載の打ち合わせも結構そんな感じだったんですよね。つまり、悪くないんだけど、正直う~んと思っている。元々は『路傍のフジイ』ではなく別のヒップホップの企画で、少しずつ進めて2、3話くらいまで作って、でもやっぱりどうしても面白いと思えないので、もう意を決して「すみません、嘘ついてました。正直面白いと思えなくて別ネタでやった方がいいと思います」みたいなことを言ったんです。それはもう、怒られるわけですよ。半年くらいやっていたので、その時間は何だったんですかみたいにめちゃくちゃ怒られ、もう平謝りするしかない。
でもそこから切り替えて、いろいろ紆余曲折ありましたけど『路傍のフジイ』の最初の1話のネームを読んだときは本当に人生で初めてぶっ飛びました。そういう経験ができて、この感覚で作品が見えたときは行けるという自分の中の感覚として基準ができたというか。それが今見れば、編集者として一歩スタートに立てたかなという瞬間ではあります。自分の興奮と同じような感想をSNSなどで見かけると堪らないですよね。
『オリジナル』編集部が今推したいマンガ
――今、『オリジナル』編集部として推したい作品を教えてください。
菊池 今ちょうど雑誌を変えていこうというところで、これから始まる作品も結構あって難しいんですけど。まずは山本おさむ先生の『れむ a stray cat』です。
もちろん山本先生自体がすごいキャリアもすごいし、だから、非常に素晴らしい表現力を持ってらっしゃる方なんですけど。
基本的に私個人の考えとしては、漫画家さんに限らないんですけど漫画家さんも前進しないと退化すると思っているところがあるんです。つまり、現状維持というのはないと思っていて、前進しているつもりでも現状維持ぐらいだろうという気がするんですけど、そういう意味では、山本先生のように素晴らしいキャリアをお持ちの方にもやっぱりさらに新しいチャレンジをしていただきたいというのはすごくあるんですね。そして、マスターピースを作っていただきたいという。
分かりやすく言うと『スペリオール』でやっていたときに『トリリオンゲーム』という作品を池上遼一先生に始めていただいたんですけど、あれは池上先生の新しい一歩になったなと思っているんです。
――あんな大御所になって、新しい境地を切り開いているのは凄まじいですよね。
菊池 すごいと思うんですよね。やっぱり第一線でいらっしゃるし、作家さんが何歳になっても同じことばかりやっていてもしょうがないだろうというのはあって。そういう意味では山本先生が今回新しい挑戦をしてくれたなという感じがすごくあります。ちょっと先まで読んでいるので言っている部分もあって、1話だけだとちょっとわからないかもしれないですが、非常に期待をしております。
――ちなみに、山本おさむさんの前作の『父を焼く』であったり、齋藤なずなさんの『ぼっち死の館』などが70歳以上をターゲットとした「ビッグコミックフロントライン」という新レーベルで単行本が発売されていましたが、そちらに懸ける想いはどういったものだったのでしょうか。
菊池 あれは、販売部がやろうといってやったみたいですが、その後、あまり話は聞きませんね(苦笑)。
――そうなんですね。個人的にはこれからマンガに親しんだ層も高齢化していき70代以上の読者もどんどん増えていくと思うので、そういった取り組みを小学館さんのような大手からやっていってくださるのはすごく良いなと思っていたのですが。
菊池 そこは確かにあることはあるんですよね。高齢者とまでは言わないですけど、例えば『オリジナル』に来て驚いたのはやっぱり未だに長寿作品がすごく売れているんですよね。『黄昏流星群』とか、『三丁目の夕日』とか。そういう読者の人たち向けにも作品を作っていくべきだな、とは思います。
次にほぼ新人と言っていいおかくーこさんの『父を怒らせたい』。
――1話目の最初の見開きからオーラがありました。
鈴木 1話は訳が分からないかもしれないです(笑)。でも最初からすごく良いネームが上がってきて。おかくーこさんとの出会いはコミティアだったんですけど、とても良い同人誌を描かれているんですよ。これだけの人、当然既に他で描かれているんだろうなと思ったんですけど、色々な編集部に見てもらったもののあまり上手くいっていなかったということで。うちとしてはラッキーだなと。
菊池 編集長としては、雑誌も前進しなきゃ退化すると思っているんですね。だから一番良くないのって「『オリジナル』らしい作品を作ろう」っていうスタイルだと思ってるんですよ。『オリジナル』らしさというものは、ないと思っていて。それは要するにそのときの『オリジナル』らしさであって新しい『オリジナル』に進化していかなければ古くなっていって、どんどんどうでもいい雑誌になっていくだろう、どうでもいいマンガを量産する場所になっちゃうだろうなと。そういう意味では新しいことをどんどんやっていった方がいいと思うんです。
おかくーこさんは他のところで描いてらっしゃるので新人さんという言い方はちょっと失礼なのかもしれませんけども、非常にフレッシュに感じております。
鈴木 菊地が『オリジナル』で新連載をどんどん始めて行ってほしいと編集部全体に投げかけたときに、いろいろなざっくりした枠組みとか、こういうのを狙った方がいいんじゃないかみたいなことなども話していたんですけど、自分は言ってしまえばまだ一応編集部の中ではかなり若い方ではあると。作家さんも若い方なので、じゃあ自分は何も難しいことを考えずに自分の作家さんが本気で面白いものを作りさえすればいいだろうと。それが多分、今の『オリジナル』じゃないものになるだろう、ということで作っていっていて、手応えを持ってやれています。
菊池 『オリジナル』らしさとかは気にしなくていいと思っているんです。
『ミワさんなりすます』もそういう意味では、同じで良い意味で『オリジナル』らしくない。
だいぶ前に始まってドラマにもなりましたけれども、『オリジナル』とはちょっと外れてるいるかなという気もしていて。でも訴求力があって、非常に読んでいて単純に楽しいし、今だなという感じがしています。
鈴木 自分はもう一読者として読んでいる感じですけど、言葉がすごいなというのは思っていますね。絵はもちろん良いんですけど、言葉を生かすための演出というか、コマ割りとか流れとか、絵とともにある言葉と構図がすごく決まっている。ちょっと文学性すら感じるぐらいに強烈なパワーを感じますね。
菊池 私なんかの世代からすると「推し」への情熱ってもうよく分からないんで、そういうのも勉強になるなって(笑)。

流行を自ら作り出すのが編集者の醍醐味
――編集部は今何人くらいでやられているんでしょうか。
菊池 ちょうど10人ですね。
――編集部の中で今現在流行っているものやことはありますか。
菊池 うちの会社はどこもそうだと思いますけど、結構みんなバラバラに動いていて社内でも全然会わないくらいなんですね。出勤時間も全然違って、朝7時くらいに来て10時11時くらいには作家さん巡りに出ていく方もいれば、私は結構夕方くらいしか出てこない。
鈴木 一部だけなんですが、THEE_MICHELLE_GUN_ELEPHANTのチバさんが亡くなられた件についてはすごく話題になりました。
――編集部の方が行きつけのお店や好きなお店があったら教えてください。
菊池 「セルジュ」という古い神保町の飲み屋があるんですけど、小学館の編集者のたまり場みたいなところがあるんです。若い人はいかないよね?
鈴木 そうですね、行かないです(笑)。
菊池 若い人はどこ行くの?
鈴木 「リベルテ」というすずらん通りのバーがあるんですけど、そこにたまに行くぐらいですかね。自分は普通に「三幸園」とか行ってます。
――「編集者が繋ぐ思い出のマンガバトン」ということで毎回編集者の方の思い出のマンガ作品をお聞きしているんですが、お二方の人生を語る上で外せない思い出のマンガを挙げていただけますか。
菊池 いろいろありますけど、いましろたかしさんのデビュー単行本の『ハーツ&マインズ』。
作家さんのファンも多くて、我々世代はハマっている方が多いと思います。要はもういろいろなしょうがない負け組の方の人生みたいな話がショートであって面白いんですけど、自分と重なったのはイタズラ電話にハマっちゃった男の話です。女の子と「何履いてるの? げへへ」とかそういう話をして「馬鹿じゃない!」って切られちゃったりするんですけど、そういうことをやっているやつがこのままじゃ駄目だと思ってバッティングセンターに行ってみたら意外とバッティングセンスがあって、草野球のチームで4番になって人生救われるという話なんですよ。
それとほぼ同じようなことがあったというか。ある女性に失恋をして行き詰まっているときに似たようなことをやっちゃって、もう自己嫌悪の塊みたいな。そのころにちょうど『ハーツ&マインズ』に出会って、いや~マジかぁ……となってバッティングセンターへ行って、バッティングの才能はなかったんですけど(笑)何かそれはそれで気持ちよくて、それで就職しようかなみたいになったということがありまして。好きというか、自分にフィットした作品ですよね。
――ありがとうございます。鈴木さんはいかがでしょうか?
鈴木 たくさんあって……好きかどうかはちょっと怪しいんですけど、一番すごいなと思ったのは『銭ゲバ』です。
確か小学館に入社をしてから出会ったんですが、ただただ本当にすごい。「金のためなら何でもするズラ!」という風に生きるしかなかった人が、悪として生きていたんだけど最後に自分で死を選ぶことで、それで良いとは思ってないぞというか、何かめちゃくちゃ意志のようなものを感じたんです。どんな理不尽があっても、そこでNOと言えるみたいな。単純に絵がすごいのもあるんですけど、読んだ後に何でこんなすごいマンガを作れるのかと衝撃を受けました。
もうひとつは『よつばと!』です。
自分は8年大学にいたんですけど、本当に留年も何回もして、友達はもういなくなって本当に1人で、多分鬱みたいな感じだった気がするんですけど、そのときに「よつばは無敵だ」みたいなセリフがあるんですけど、本当に日常のどんなどうでもいいことを見ても、彼女の目を通せばそれがとても輝いて見える。それがすごく眩しかったですね。『よつばと!』に救われていたのかもしれないです。
――他社作品の中で、現在注目しているマンガがあれば教えてください。
菊池 『アフタヌーン』の『青野くんに触りたいから死にたい』はすごいなと思います。天才だなと。怖くてしょうがないですね。人間のリアクションが何か想像を超えてるところがあるんですよ。この作者の人ってどういう風に人間を見ているんだろうなっていうのがそら恐ろしいというか、ちょっと戦慄を覚えるぐらい、すごいなと。本当に細かいリアクションなんですけど、普通にこうしたらこうするだろうっていう当たり前の人間のルールがあるんですけど、そうじゃない動き方をするんですよね。そこが本当にすごいなと感じています。
鈴木 押見さんの『おかえりアリス』はもう終わりましたけど好きでしたね。あと『8月31日のロングサマー』はすごいですね。シンプルに面白いです。伊藤一角さんは『月刊!スピリッツ』で連載していた『僕はお肉じゃない』を読んでいたのですが、めちゃくちゃ面白いの描いてるなと。
――同じ時代でマンガを作っている次の編集者の方へのバトンといたしまして、何かコメントをお願いします。
菊池 思うのはやっぱり編集って非常に面白い仕事だと思うんですね。もちろん千差万別なんですが、例えば今これが流行っているから作ったらいいんじゃないかという考え方が結構増えてきている印象があるんです。けど、せっかく流行とかを作れる立場にいるので、もっと仕掛けたらいいのになというか。流行は自分から作るものだという自負を持って仕掛けるのはこのマンガの仕事の一番の醍醐味というか。新しい表現などを作っていって、極端に言えば新しいジャンルを切り拓くとかができれば理想的ですけど、できないにしても何かそういうことを意識してやるのは大事なことだなという風に思います。
新しいことを仕掛けていけるということがやっぱりすごく楽しいし、楽しかったですから、でも偉そうにちょっと上から目線とはならないようにそういうことを意識して、後輩とかに対しては言ってほしいなと思いますね。
30年やっているから言えるところでもあるんですけど、やっぱり作家さんって本当にすごいんですよね。単純に面白いことを考えてるんですよ。それを描いてくださいっていうだけでもう終わるというか。いろいろこんがらがったりとかそういうことはあると思うんですけど、作家さんの話をもっと徹底的に聞けばほとんどの問題は解決するのになと思うことは、偉そうに言うと個人的には多いですね。
これは後輩・部下とかに言うんですけど、なんかアイディアとか出さなきゃ駄目だみたいな文化が少なくとも小学館の青年誌にはあって、でもそれは全然必要がないというかやらない方がいいと思ってるぐらいなんです。何か付け足すんじゃなくてもっと削り取るという。
ある作家がいたときにその純度が高くなればなるほど面白くなると思うんですよね。その純度を高めるということは、要するに余分なものを削り取るということなんです。記事もマンガもそうですが編集の作業って基本的にはどちらかというと削る作業だと思うんですけど、付け足すんじゃなくて削ればいいのになということをすごく思いますね。そこはただあんまり言ってもね、ピンとこないかな(笑)? どうですかね?(笑)
鈴木 いや~、そうですね……(笑)。連載ネームを見てもらって何話目かで何の話か分かんないよみたいなことを言われたんですけど、根っことしては多分同じで。要は何の話なのか、このマンガはどこに行くのかということだし、多分作家と自分が何をそれぞれ思っているかを明確にしていくということだと思います。ただ、頭ではわかってはいるけどそれをやれるとは限らないっていう好例だと思いますが(笑)肝に銘じてやろうとは思ってます。
「マスターピースへ挑む場」という本質への回帰
――何かお知らせがありましたらお願いします。
菊池 先ほども言ったことなんですけど、『オリジナル』をこれから変えていくというか、作家さんや才能もそうだし何でもそうだと思うんですけど、進歩しなければ退化すると思っているんですね。『オリジナル』でよく言われるのが『オリジナル』って今年で50周年なので歴史と伝統がある。青年誌で1、2を争うほど部数は未だにあるんですよ。だから『オリジナル』らしい作品をどうのこうのとか、作家さんも『オリジナル』で描くというときにはやっぱり何か『オリジナル』らしさというのを無意識でも意識しちゃうというか。
『ヤングマガジン』が我々の時代だと大雑誌で、不良的でエロスがあってナイスバカがいてというような『ヤングマガジン』文化があったんですが、やっぱり作家さんもそこで描くときはみんな『ヤングマガジン』らしさを意識してしまうところがあったんですけど、それと同じで『オリジナル』で描くのであれば何か保守的で長尺マンガみたいなものを狙うのかなと無意識に思ってしまうことがすごく多いと思うんです。ただ、そういう『オリジナル』らしさって自分は表層でしかないと思っていて。
ジョージ秋山先生もそうですし、長尺の作品は確かに多いんですよね。でも長尺ってことはどういうことかっていうと、それは要するにマスターピースなんです。例えばジョージ秋山という作家のキャリアを考えたときに、先ほども出た『銭ゲバ』とか『アシュラ』とかいろいろあって。でも『浮浪雲』はやっぱり必ず入るんですね。例えばジョージ秋山先生の訃報みたいなものがあったときに、必ずマスターピースとしてキャリアの中に入ってくる。そういう作品が、うちは多かったんですよ。『あぶさん』も『風の大地』もそうです。
つまり、保守的で長尺な作品が多いんじゃなくて、作家さんがマスターピースを描く場所なんですよね。そういう認識が『オリジナル』の本質だと思ってるので、そこだけは大事です。名前のある人であれ新人であれ、すごい才能を持ってる方がマスターピースを描く場所というところに持っていきたいと思っています。そこが『オリジナル』の本質ですし、それは長尺でも短い3巻の本でもいいと思うんです。そういう雑誌として、これからやっていきたいなと思っています。
表層的には雑誌を変えるということなんですけど、自分の感覚としては本質に戻すという感じです。山本おさむさんの新作に期待しているというのもそういうところですね。名のある作家が、新しい挑戦をする。縁起でもない話ですけど、もし山本おさむさんにいつか何かがあったときに、「れむ」という作品を描いていたと紹介される。そういうマスターピースに挑んでもらえるような場所にしていきたいです。

――最後にいつも『オリジナル』を読んでくださっている読者のみなさんと、この記事を読んでくださってる読者の皆さんにコメントをお願いします。
菊池 長尺作品が多いと言いましたし、そういうイメージがあると思うんですけど、それは先ほども言ったように意図的にそうなったわけではないんですね。なのでそこは元に戻しますということで、今10本以上新連載も用意しています。ぜひご期待ください。うちの若手のエースからは?(笑)
鈴木 (笑)。雑誌でもいいですしX(旧Twitter)で見つかってもいいですし、こちらは全力で作りますのでどこかで作品を知ってもらって、一瞬でも面白いなって感じてもらえたら嬉しいです。
――本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。
私の中で一際燦然と輝くマスターピースとして新井英樹さんの『ザ・ワールド・イズ・マイン』が存在するのですが、その担当編集である菊池さんからさまざまなお話を直接うかがえたことは貴重な体験でした。「オリジナルは長寿作品が載る場ではなく、作家がマスターピースに挑む場所」「現状維持は退化」というヴィジョンには魂を熱くさせられました。今後たくさんの新連載が出てくるということで、また新たな傑作が登場することは間違いなく、楽しみです。