2022年9月16日(金)から26日(月)にかけて、東京の日本科学未来館などで、第25回文化庁メディア芸術祭の受賞作品展が行われる。今回はその第25回メディア芸術祭で、マンガ部門の優秀賞を受賞したティー・ブイ『私たちにできたこと―難民になったベトナムの少女とその家族の物語』(椎名ゆかり訳、フィルムアート社、2020年)を取り上げたい。
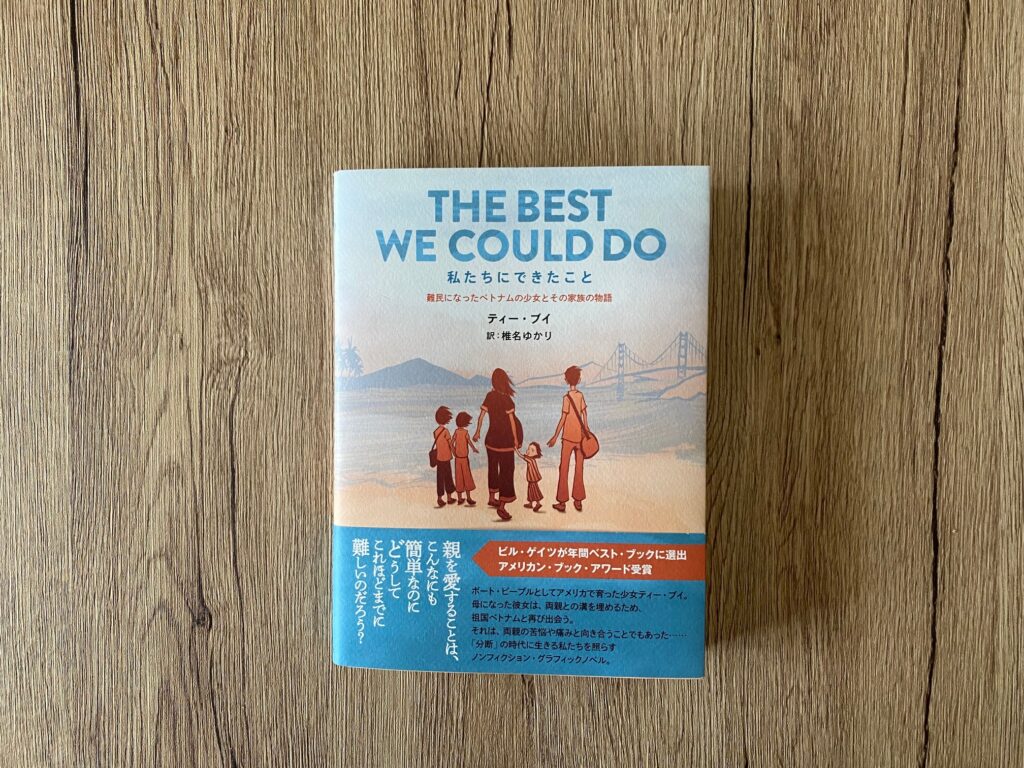
***
まず、文化庁メディア芸術祭について手短に説明しておこう。同祭公式サイトの説明によれば、「文化庁メディア芸術祭はアート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバル」である。主催は文化庁メディア芸術祭実行委員会で、始まったのは1997年のこと。2015年の第19回までは毎年開催され、2016年に一度だけ開催されなかったが、その後は着実に回を重ね、今年2022年で第25回を数える。上述の4つの部門に対して、国内外から、プロ・アマ問わず、さまざまな作品の応募があるのが特徴で、任期制の審査委員会が、毎回、大賞、優秀賞を始めとする各賞を選出し、受賞した作品はのちに受賞作品展で展示される。
メディア芸術祭は4部門でひとつの賞ではあるが、当然、それぞれの部門に焦点を当てることも可能で、筆者もとりわけメディア芸術祭マンガ部門に、日本国内の主要なマンガ賞のひとつとして注目してきた。マンガの賞は国内に数あれど、受賞作に日本の商業マンガも自主制作作品も海外マンガも並ぶという点で、メディア芸術祭は異彩を放っている。
受賞作一覧のページもあるので、詳しくはそちらをご覧いただきたいが、これまでさまざまな海外マンガがメディア芸術祭の各賞を受賞している。中でも注目すべきは2011年の第15回で、パコ・ロカ『皺』(小野耕世、高木菜々訳、小学館集英社プロダクション、2011年)とアリソン・ベクダル『ファン・ホーム~ある家族の悲喜劇~』(椎名ゆかり訳、小学館集英社プロダクション、2011年)が優秀賞を受賞し、ニコラ・ド・クレシー『氷河期』(大西愛子訳、小学館集英社プロダクション、2010年)とアレハンドロ・ホドロフスキー作、メビウス画『アンカル』(原正人訳、小学館集英社プロダクション、2010年)、AKRU『北城百画帖』(蓋亜文化、2010年※邦訳ではなく、台湾で出版された原書)が審査委員会推薦作品に選ばれている。小学館集英社プロダクションの作品ばかりというところが若干気にはなるが(当時、それだけ小学館集英社プロダクションが海外マンガの邦訳出版に力を入れていたということでもある)、それでもこれだけ多くの海外マンガが、日本国内で、日本のマンガと並んで評価されるということは、なかなかあることではない。
翌2012年の第16回も壮観で、ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画『闇の国々』(古永真一、原正人訳、小学館集英社プロダクション、2011年)がなんと大賞を受賞し(海外マンガがメディア芸術祭の大賞を受賞したのは今のところこれだけである)、エマニュエル・ルパージュ『ムチャチョ—ある少年の革命』(大西愛子訳、飛鳥新社、2012年)が優秀賞を受賞、その他、マルジャン・サトラピ『鶏のプラム煮』(渋谷豊訳、小学館集英社プロダクション、2012年)、ヴィンシュルス『ピノキオ』(原正人訳、小学館集英社プロダクション、2011年)、シルヴァン・ショメ作、ニコラ・ド・クレシー画『レオン・ラ・カム』(原正人訳、エンターブレイン、2012年)、『Euromanga Vol.7 追悼メビウス特集』(飛鳥新社、2012年)、クレイグ・トンプソン『Habibi』(風間賢二訳、ティー・オーエンタテインメント、2012年)が審査委員会推薦作品に選ばれている。
その後もほぼ毎回、邦訳海外マンガが何がしかの賞を受賞している。詳細については上述の受賞作一覧ページからご確認いただきたい。こうした流れの中で、今年2022年の第25回メディア芸術祭で、マンガ部門優秀賞を受賞したのが、ティー・ブイ『私たちにできたこと―難民になったベトナムの少女とその家族の物語』というわけだ。
メディア芸術祭は、ことほどさように、海外マンガが日本のマンガと並べられて評価される、またとない貴重な機会であるわけだが、今年8月24日、「令和4年度については、作品の募集は行わないこととなりました」という一文が同祭サイトに掲載された。その後、文化庁側からの公式発表ではないものの、どうやらメディア芸術祭が終わるらしいという報道が、「朝日新聞デジタル」と「ITmedia NEWS」でなされている。事実であれば、非常に残念である。
***
気を取り直して、ティー・ブイ『私たちにできたこと―難民になったベトナムの少女とその家族の物語』を紹介することにしよう。現状、日本でどれだけ読まれているのかわからないが、メディア芸術祭マンガ部門優秀賞に輝いたのもうなずける、すばらしい作品である。
作者のティー・ブイは、1975年に南ベトナムに生まれたアメリカ人のグラフィックノベル作家。作品は決して多くなく、イラストレーターとしての仕事がいくつかあるようだが、まとまったグラフィックノベルの仕事は、現状、本書『私たちにできたこと―難民になったベトナムの少女とその家族の物語』だけである。原書は2017年、アメリカのエイブラムス・コミックアーツ社からThe Best We Could Do: An Illustrated Memoirというタイトルで出版された。2017年にナショナル・ブック・クリティックス・サークル・アワードにノミネート、2018年にはアメリカン・ブック・アワード受賞およびアイズナー賞ノミネートと、さまざまな賞を受賞していて、本国アメリカでの評価も高い。
日本語版の副題で端的に説明されているように、本書は「難民になったベトナムの少女とその家族の物語」である。「難民になったベトナムの少女」とは、作者ティー・ブイ本人に他ならない。
物語は2005年のニューヨークから始まる。ひどい陣痛に苦しみながら息子を出産したばかりの作者ティー・ブイは、かつて同じ思いをして自分や姉弟を産み育ててくれたであろう母親に強い共感を覚える。

実は、作者の家族―両親とふたりの姉と作者とひとりの弟―は、もともと南ベトナムで暮らしていたベトナム人だったのだが、1978年、ベトナム戦争の余波で混乱に陥った首都サイゴンから逃れる決断をしたのだった。作者が3歳の頃の話である。一家は、ボート・ピープルとして、ほうほうのていでベトナムからマレーシアのプラウ・ブサル難民キャンプに到着すると、人生をやり直す移住先をアメリカに定め、クアラルンプールから空路アメリカに向かうことになる。

親戚を頼って、一旦はシカゴに落ち着いた彼らだが、気候も文化も異なる異国での生活が大変なものだったことは想像にかたくない。寒さに耐えきれなくなった彼らは、別の親戚を頼って、今度はカリフォルニアに向かう。新生活は、とりわけ両親にとってつらいものだった。ベトナムではふたりとも教師をしていたが、難民としてやってきたアメリカではそうはいかない。父親はアメリカでの暮らしに馴染めず、仕事にも就かずに、家で無為な時間を過ごすばかり。時に地域住民の憎悪が向けられることもあり、彼の自尊心はますます傷ついていく。父の代わりに一家を支えたのは母だった。彼女は家族の面倒を見ながら、勉学も怠らず、低賃金ながら正規雇用の勤め口を見つける。

そういったつらい体験のせいか、その後、両親は別居し、親子の関係もギクシャクしたものになってしまう。作者にとって両親は、「意志と怒りに満ちた亀裂の両側を表す象徴」(P38)だった。彼女は問う。「私たちはなぜこれほど孤独な場所に来てしまったのか」(P47)と。こうして、過去と現在、両親と自分の間にある隙間を埋めるため、作者は自分たちのルーツを振り返るための取材に取りかかることになる。

興味深いことに、本書は最初からグラフィックノベルとして企画されていたわけではないらしい。本書の序文によると、2002年、当時大学院で美術教育を学んでいた作者が着手したのは、「ベトナムとアメリカのブイ家:記憶の再構築」という、文章と写真と絵からなるオーラルヒストリーの学術的なプロジェクトだった。2005年、作者は、この企画はむしろグラフィックノベル向きなのではないかと思い至る。一時は、「難民反射神経」というタイトルが当てられたこともあったそうだが(この「難民反射神経」なるものについては、第9章「火と灰」で語られる)、それから10年以上の歳月を経て、この企画は、2017年、最終的に『私たちにできたこと―難民になったベトナムの少女とその家族の物語』として日の目を見ることになった。
上の要約では、一家の身に起きたことを、ある程度、時系列に沿って整理したが、本書は決して理路整然とした物語ではない。第1章で2005年のニューヨークにおける作者の出産が描かれたかと思えば、第2章では、10年飛んで、2015年、作者が本書を執筆している最中と思われるカリフォルニアのバークリーに向かい、ページをめくると、今度は1999年、まだ若い作者がカリフォルニアのサンディエゴで両親と一緒に暮らしていた時代に話が飛ぶ。もともと本書はオーラルヒストリーのプロジェクトであったという話だが、まさにその実践であるかのように、時折飛躍をはらみながら、曖昧な記憶を辿るようにして、両親の体験を中心に家族の歴史が語られていく。
その結果、掘り起こされたのは、短い紙幅ではとても紹介しきれないブイ家5世代にわたる豊饒な物語である。作者とその息子、作者の姉弟、両親、両親の両親、両親の祖父母……。当然ながら、そのそれぞれにさまざまな物語がある。とりわけベトナムの激動の歴史を背景にした、作者の父親とその父親、祖父の波乱に富んだ生涯はめちゃくちゃ面白い。ぜひ一読をおすすめしたい。
一家はベトナム戦争後の共産主義政権の監視社会で生きる恐怖に耐えかね、狭いボートの船倉に息を殺してひそみ、やっとの思いで亡命に成功する。ところが、紆余曲折の末に辿りついたカリフォルニアはサンディエゴのアパートも、難民の体験がしみついているだけに、一歩外に出ればどんな危険が待ち構えているかわからないと怯えざるをえない、決して心休まることのない場所だった。両親の不安や苛立ちが立ち込めたその家は、いわば「他に行き場を持たない魔物を囲う檻」(P76)。薄暗がりの中に魔物がひそみ、幼い作者の体を奪おうと、虎視眈々と狙っていた。

夜になり、不安がいや増すと、幼い作者はギュッと目をつぶり、夢の中に逃れるのだった。夢の中では、アパートは水の中にあって、作者は魔物に怯えることもなく、自由自在に泳ぎまわることができた。大人になった作者がこの本で成しとげようとしたことも、ある意味、これと同じことなのかもしれない。おそらくは歴史の重みや両親の不安や苛立ちに由来するわけのわからない違和感から、当の両親にオーラルヒストリーを試みることで自由になること。しがらみから自由になって泳ぎまわる。ただし、今度は目をつぶることなく。
母と同じように親となった作者は自問する。ベトナムから、両親から受け継いだ「哀しみの遺伝子」(P335)を、彼女もまた息子に伝えてしまうのではないか。過去と現在、両親と自分の間にある隙間を埋めるために本書を執筆した彼女が、その問いにどのような結論をくだしたのか、ぜひ自分の目で確認していただきたい。
筆者が編集長を務めていた海外マンガの情報サイト「ComicStreet」で、中垣恒太郎さんが邦訳刊行前に本書を類書と併せて取り上げている。興味がある方はそちらもぜひ。
***
筆者が友人たちと行っている週一更新のポッドキャスト「サンデー













