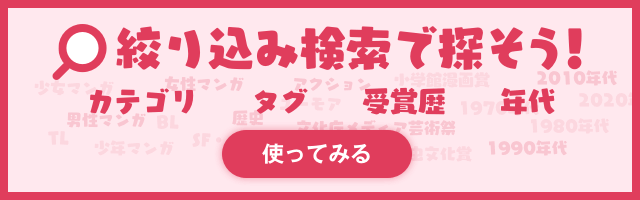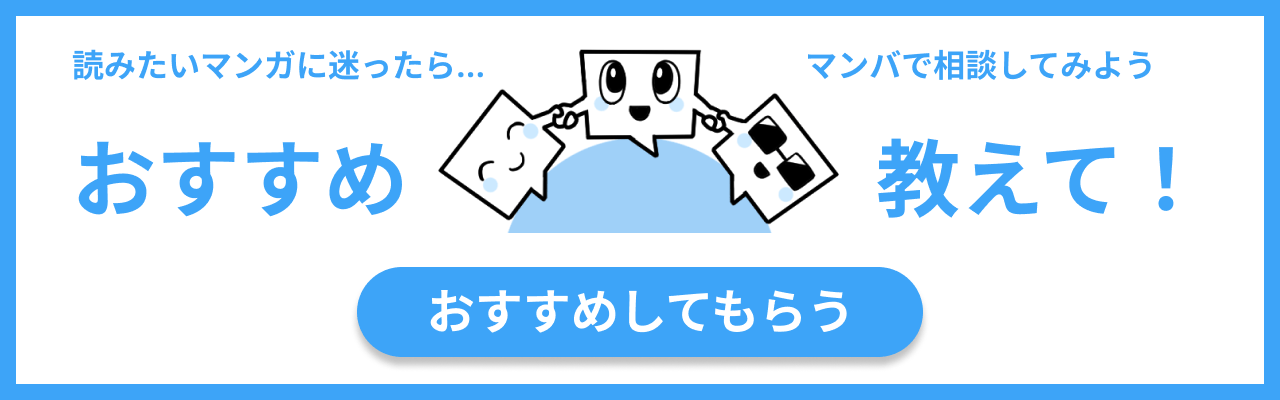この連載では、これまで20作品以上の海外マンガを紹介してきた。こうなったらマンガで世界一周といきたいところだが、実はこれまで取り上げてきたマンガは、北米、西ヨーロッパ(特にフランス語圏)、東アジアに偏りがちで、南米、アフリカ、中東、東南アジアなど、紹介できずにいる地域はまだまだ多い。
そもそも南米にしろアフリカにしろ中東、東南アジアにしろ、これらの地域のマンガは邦訳が決して多くない。だからこそなかなか紹介する機会を得られずにいるのだが、今回はそうした未紹介の地域のマンガの中から、東南アジアはマレーシア発のマンガをひとつ取り上げたいと思う。ちょうど10年前の翻訳になるが、ラット『カンポンボーイ』(監訳:左右田直規、訳:稗田奈津江、東京外国語大学出版会、2014年)という作品である。

ご覧の通り判型は横長、中面にはコマ割りがなく、1枚絵の連続に文章がついた絵物語的な紙面で、フキダシの使用も少ない。パッと見、私たちに馴染みのあるマンガとはだいぶ違っていて、絵本と言ってしまってもよさそうだが、本書はれっきとしたマンガ。本文の正味は140ページほどで、読みごたえもたっぷりである。
原書は1979年、Kampung Boyというタイトルでマレーシアのブリタ・パブリッシングから、マレー語交じりの英語で出版された。意外にも原書刊行から5年後の1984年には、最初の日本語訳が刊行されていている(ラット『カンポンのガキ大将』荻島早苗、末吉美栄子訳、晶文社、1984年)。今回紹介するのは、その最初の翻訳から30年の時を経て、2014年に刊行された新訳版である。
***
タイトルにもある「カンポン」とは村のこと。本書は「マレー半島のペラ州キンタ地区のまんなかにあるカンポンで生まれた」語り手が、カンポンでの暮らしを振り返っていく作品である。語り手は父母に見守られながらすくすくと育ち、やがて10歳を迎えると、全寮制の学校に編入すべく、カンポンを去ってイポーという町に越していく。10年ほどの長い期間が扱われているわけだが、物語はその間の印象深い、とはいえ特に劇的というわけでもないさまざまな出来事を描いていく。
本書の語り手には名前がないが(本書の続編『タウンボーイ』で彼が「マット」という名前であることが判明する)、作者ラットの分身と考えて差し支えないだろう。ラットの出身地がまさにペラ州キンタ地区であり、本書には彼自身の体験がふんだんに盛り込まれていると思しい。時代設定についても、特に作中には記されていないが、作者の生年が1951年で、作中で語り手は最終的に10歳を迎えるので、おそらくは1950年代の10年間を描いているのだと推察される。ちなみにマレーシアという国が建国されるのは1963年のこと。当時、マレーシアはまだイギリスの保護領マラヤ連邦だった。本書はその時代を描いた物語である。

1950年代のまだ近代化されていないマレーシアの片田舎の風景が、語り手の目を通して描かれていく。いかにも東南アジアという感じの高床式の住居。家の外に広がる広大なゴム園、その奥の泥水がたまった池に浮かぶ、スズを採取するための怪物めいた浚渫船(しゅんせつせん)、路面に簡素な店が立ち並ぶカンポンの中心街……。

過去を愛おしむ語り手の視線と作者ラットのクセのある、それでいてチャーミングなタッチが相まって、これらの風景からは言いようのないなつかしさのようなものが感じられる。ロケーションこそマレーシアだが、ここで語られる語り手の幼少期の体験は、必ずしもマレーシア特有というわけでもなく、万国共通のものである。大人にしてみればなんてことはないが、幼い子供にとっては広大な住居や屋根の隙間から差す日差し、父母が与えてくれる安心感、安全な室内とは対照的な、どこか不気味でそれだけに子供を惹きつけてやまない外の世界、初めて子供たちだけで川に行き魚をとった日の感動……。マレーシアを訪れたことすらない筆者がこの作品になつかしさを感じたところで、不思議はないのかもしれない。
ちなみに本書の巻末には監訳者の左右田直規さんの詳細な解説がつけられているのだが、左右田さんはそこで、もともと英語で出版された『カンポンボーイ』はマレーシア在住の外国人をも読者に想定していて、だからこそ、本書には「カンポンを俯瞰的に対象化してとらえる視線が感じられ」、本書は「マレーシア人以外の読者たちにも単なるエキゾティシズムにとどまらない、ある種の普遍的な郷愁を引き起こす」(P149)のではないかと分析している。

マレーシアはマレー系、中華系、インド系など、さまざまな民族が共生する多民族国家だが、語り手の一家はマレー系で、彼らが暮らすカンポンも、その住人のほとんどがマレー系である。彼らが信仰するのはイスラム教で、その教えに根差した人々の日々の暮らしが描かれていて、まったく異なる文化圏に育った読者にしてみれば、そのいちいちが非常に興味深い。
語り手が誕生するや、父親は彼を抱きかかえてアザーンを唱え、誕生から45日目には、語り手は髪の毛を剃られ、ハンモックで揺られ、訪問者たちのマルハバンの歌声で歓迎される儀式を受け、6歳になると、小学校とは別にコーラン塾に通い、コーランを学ぶ……。

とりわけ興味深いのが、男児が10歳になると受ける割礼式である。語り手はふたりのいとこと一緒に祖母の家でこの儀式を経験することになるが、その顛末は10ページ以上を費やしてたっぷり描かれている。式当日、多くの村人たちが集まり、3人の子供が大人の仲間入りをするのをまるでお祭りのように祝っている様子が楽しい。

こうしたいつから続いているとも知れない伝統的な暮らしの裏では、近代化の波がひたひたと押し寄せている。多くの村人にとって移動手段は徒歩や自転車だが、自動車もちらほら普及し始め、彼らが住むカンポンに止まることはないとはいえ、すさまじい速度で進む郵便列車も走っている。そうした近代化の象徴は、とりわけスズを採取する浚渫船だろう。この作品においては、伝統と近代はまだのんびりと同居していて、牧歌的な様相を呈しているが、そんな状態がいつまでも続くわけではない。

語り手自身、10歳を迎えると、全寮制の学校に編入するためではあるが、イポーというより大きな町へと引っ越していき、このなつかしいカンポンに別れを告げることになる。
***
今や自伝的なグラフィックノベルが世界のマンガの中で確固とした地位を築いているのは周知の事実だろう。本書『カンポンボーイ』が発表された1979年にそういった作品がどれくらいあったのか、さらには作者のラットがそういった作品を参照していたのかどうか、筆者は現時点では何も知らない。ただ、今この作品を読むのであれば、その文脈を無視することはできないだろう。自伝的なグラフィックノベルの傑作として名前があがる作品にアート・スピーゲルマンの『マウス』やマルジャン・サトラピの『ペルセポリス』があるが、本書はそれらと並べても何ら遜色のないアジア発のグラフィックノベルである。
今回紹介した日本語版は、2014年に東京外国語大学出版会から出た新訳だと冒頭で触れたが、日本の大学出版局から海外マンガの翻訳が出版されるのは珍しいことではないかと思う。既に述べたように本書には監訳者で東南アジア近現代史、マレーシア政治社会史を専攻する左右田直規さんの優れた解説がついていて、学術的な成果と言っても過言ではない仕上がりになっている。
本書の扉裏を見ると、「本書は、東京外国語大学出版会とマレーシア翻訳・書籍センターの共同出版による刊行物です」というクレジットがついていて、マレーシア翻訳・書籍センターによって何がしかの助成がなされていることが想像できる。やはり冒頭で触れたように、日本では、海外マンガの邦訳は北米、西ヨーロッパ、東アジアの作品に偏りがちなのだが、そのような状況下で、マレーシアが誇る古典的作品ラット『カンポンボーイ』の新訳が、マレーシアの協力を得て、こうして日の目を見ることができたのは、実に有意義なことだと思う。
本書の翌年に刊行された続編のラット『タウンボーイ』(訳:左右田直規、東京外国語大学出版会、2015年)を除けば、類似のケースを目にした記憶はないが、こういった邦訳海外マンガももっと出版されてもいいのではないかと思う。
筆者が海外コミックスのブックカフェ書肆喫茶moriの森﨑さんと行っている週一更新のポッドキャスト「海外マンガの本棚」でも、2023年12月22日更新回で本書『カンポンボーイ』とその続編『タウンボーイ』を取り上げている。よかったらぜひお聴きいただきたい。