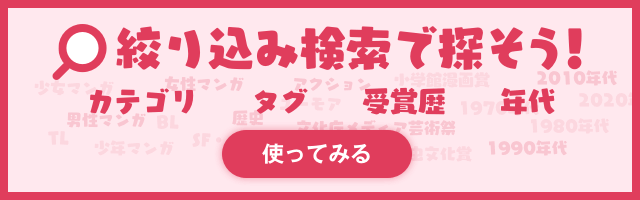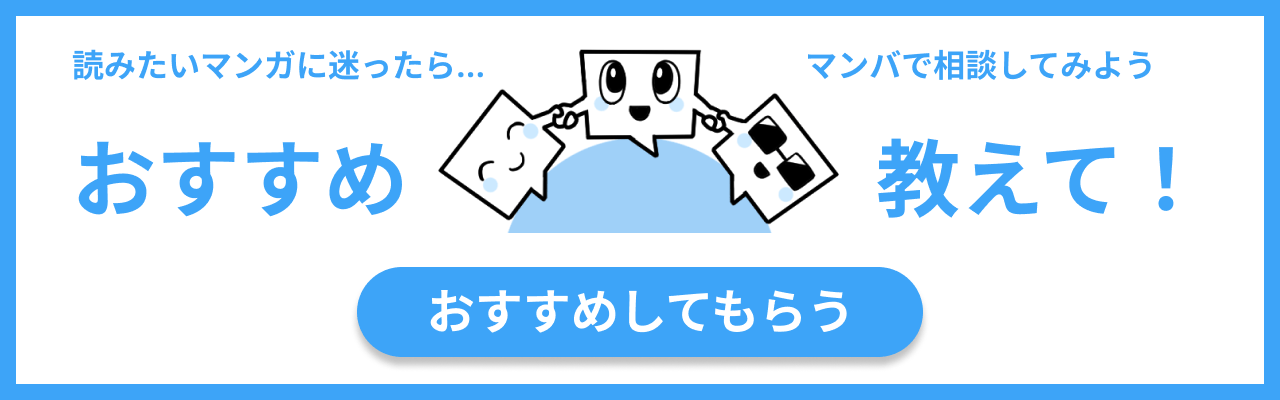世田谷文学館の「描くひと 谷口ジロー展」(2022年2月27日まで)*1は原画展である。過去にも谷口原画展を観ているが、その度に度肝を抜かれる。あの小さな原稿にここまで描き込むか、という職人工芸的な単純な驚きから、そこに施された遠近法やそれを裏切る秘かな技法、超絶的に緻密で繊細なのに抜けがあってバランスのとれた絵、スクリーントーンを加工して描かれた背景の凄さなど、どれも圧倒的で、しかもその多くがじつは普通の印刷では再現不能だったりする。原画でしかわからんのである。一体なんでここまで、という谷口の作家的情熱にひたすら感嘆する。
今回は、日本での谷口評価をもっと上げたいと以前から話し合っていた、フランスのコミック翻訳者にしてBD(バンドデシネ)ブーム仕掛人・原正人氏と訪れ、谷口原画を管理する会社「ふらり」(2017年設立)の米澤伸弥氏が館の前で待っていてくれた。
こんなメンバーで展示を観るとどうなるか。冒頭の巨大な『歩くひと』(1990~91年)カラー見開きのパネルや主要作品のコピーを観ながら「この人物じつは大きく描いてるよね。家のドアと比べると分かる」「木の葉が一枚一枚描かれてるみたいに見えますねえ」などといちいち細部を指摘し、語り、一向に原画の展示に辿り着かないのである。結局3時間かかって全部観終えた。それでもまだ見尽くした感がない。会期中にまた行くつもりだ。
ところで、スクリーントーンというデザイン用品は、本来マンガに使われるものではなかった。日本でマンガに使われるようになったのは恐らく60年代。やがて宮谷一彦などが削ったり、重ねてモアレを出したりして独特の効果を出し始めたのがほぼ70年代。規則正しく並んだドットや線を透明シートに印刷したトーンを重ね、角度をズラすとモアレと呼ばれる縞模様などが浮き出す。これを効果に使うのである。以来、当時劇画と呼ばれたジャンルで盛んに使われ、やがて多種多様のマンガ用トーンが作られるようになった。
この技法は、白黒マンガ主体で発達した日本マンガ特有の表現で、50年代の米国コミックスにあったようだが、ほぼ日本のお家芸である。一時期は、東アジアの日本マンガファンにとって垂涎の画材で、香港などにメーカーが進出したが、2010年代以降、マンガ制作のデジタル化とともに急速に過去のものとなりつつある。
谷口ジローは、このトーンワークの優れた使い手であり、かつてフランスのBD作家フレデリック・ボアレの『東京はぼくの庭』(原作ブノワ・ペータース。1998年)でトーンワークを担当して名前をクレジットされている。僕の知る限り、日本では上條淳士などに並ぶトップクラスのトーン使いだった。その凄さは、原画展でいえば、夢枕獏原作の『神々の山嶺』(2000~03年)などで確認できる。この作品の主人公は登場人物を取り囲む山であり、その絵のほとんどがトーンワークで表現されているのだ。
原画を見ないと実感できないかもしれない。が、印刷作品だけでも読者は圧倒的な山の存在感を感じるはずだ。近景はペン画を含み、遠景はトーンだけで、それを繊細に削ったり重ねたりして仕上げている。山の奥深さが実感として伝わってくる。人物は、山の風景に吞み込まれるように描かれ、見ているだけで寒さや空気の薄さまで感じられる気がしてくる。


といっても、普通の読者にはなかなかわかりにくいだろう。一部を拡大した図版で、背景の山肌がトーンを重ね、削った表現であることがわかるだろうか。
宮谷一彦のデビューは1967年で、当時の若い漫画家や、まだ読者だった漫画青年たちに大きな影響を与えた。谷口も影響を受けた一人で、トーンワークはその一つだろう。しかし谷口は1970年のデビューの頃から、すでにBD(フランス、ベルギー中心のコミック)に興味を持ち、メビウスがジャン・ジロー名義で描いた西部劇などを好んだ。
70年代の谷口作品には、その影響のように思われる山肌が、繊細で細かい線分の集合で描かれている。谷口の絵には、人物であれ背景であれ、マッス(かたまり)としての存在感が3D的に浮き上がる。谷口やごく少数の作家は、写真などの資料を見て、その空間を自在に回転させて3D的に再現する能力を持っているように思える。
話をトーンワークに戻そう。谷口原画展を見るたびに私が感動するのは、彼を多くの日本読者の記憶に残した久住昌之原作『孤独のグルメ』(1994~2008年)の中の、豆かんの絵である。そこには、おいしそうな照りのある黒豆が一見素朴に描かれている。が、これを原画で見ると、これまた繊細に貼り重ねられたトーンを削った表現であることがわかる。毎度見るたびにため息が出てしまうのである。


さて、今回は谷口ジローの原画、とりわけトーンワークを中心に書いてきたが、賢明なる読者諸君は、今やある疑問を抱えているのではないかと思う。
そもそも、こんなに繊細で緻密な背景を谷口一人で描けるわけはなく、ましてトーンワークはふつうアシスタントの仕事なのである。それを谷口という一人の作家の技法として語っていいものなのか。「それって有体にいってアシスタントの技量なんじゃないの?」という疑問である。
谷口作品にトーンが多用され始めるのは『「坊っちゃん」の時代』(1987~96年)からだが、谷口のアシスタントだった上杉忠弘は〈それ[凝ったトーンワーク]はアシスタントのライバル競争の中で、勝手にやっていたんです。〉*2と意外なことを語っている。また、谷口の背景についての指示は、ごく短いくせにハードルは高かった。たとえば『神々の山嶺』の時は「登れない山を描いてくれ」だった*3。写真一枚渡されて、しかしトレースすると「やめてくれ」といわれたという*4。
やはりアシスタントだった真柄耕一は、〈アシスタントが描いて絵柄が違っても、あまり文句は言われなかったですね。だから、どうやってクオリティをコントロールしていたのか、我々にもよくわからない(笑)。〉*5という。上杉は別のところで、谷口から背景への指示がほとんどないとした上で、〈こう言うと、アシスタントが任されて勝手に描いているように聞こえますが、実際には資料とペンの入った人物やサッと描かれたアタリで、描かなきゃいけないものはきっちり決まっているんです。〉*6と語っている。ここには部外者にとって不思議な関係性がある。
そして、この疑問は谷口ジローだけではなく、マンガ制作の集団性にかかわる問題でもある。共同作業で制作されたマンガ作品は、一人の作家に集約して語られていいものなのか、それとも共同的な作品として扱うべきか—というようなお話は、次回あらためて考えてみるつもりである。乞うご期待。
(※編集部補足…原正人さん出演のポッドキャスト「サンデーマンガ倶楽部」の谷口ジロー『ふらり。