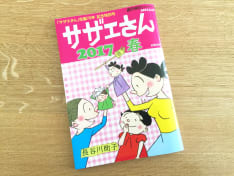鳥山明は、縦の間白(コマとコマの間)より横の間白を広くとり読みやすくする工夫など、先鋭的な作品ではむしろダサく見えてしまう表現上の更新もしている。が、それが典型的に示すように、新しい革新的な表現に注目しがちな批評言説からは注目されにくい作風である。けれど、彼は間違いなくジャンプ最盛期の牽引役で、その後のジャンプ路線のシンボルだった。のちにジャンプを支える『NARUTO』の岸本斉史、『ワンピース』の尾田栄一郎ら、多くのジャンプ作家に影響を与えた。いわば読者を育て、そこから作家を生み出したのである。いいかえると、彼はジャンプの基準、範例のようにも見なされ、結果「明朝体」のように感じられるようになったのかもしれない。
鳥山明はとてつもない作業量をこなし、しかも締め切りを守った。その理由が、会社員を経験したので、〈原稿が遅れるといろんな人に迷惑がかかる〉*1と思ったからだという。ただ、絵を描くのが好きで、悟空が成長して大きくなったのも、じつは〈アクションが描けない。だから等身を大きくしたい〉*2という絵への欲求からだった。それ自体は手塚の成長物語志向とは無関係だったようだ。彼は、小学校卒業後はマンガを読まず、マンガが好きだったわけでもない。「仕事だから」と割り切っていて、『Dr.スランプ』も『ドラゴンボール』も自分の好みではなかった。〈だって本当に自分の好きなように描いたら、絶対受けないのがわかってますから(笑)。〉*3このあたり、じつはジャンプを目指す多くのマンガ家志望者とは人格類型が異なるように感じる。発想がズレている。熱くない。冷めている。むしろジャンプ的ではないとすらいえそうだ。
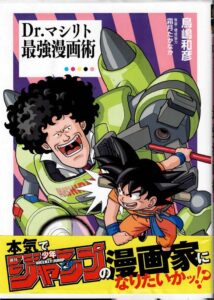
「ジャンプ的ではない」といえば、彼を見いだした鳥嶋和彦もまた、少なくとも担当編集者時代までは「ジャンプ的」ではなかった。「ジャンプ的」とは何かといえば、「女性の入ってこない男の子の競争世界」、もっといえば「番長物的な闘争」、具体的にいえば本宮ひろ志マンガを基準とする世界(というとあまりにも単純化しすぎかもしれないが、話をわかりやすくするために)、とりあえずそうしておこう。
せっかく人気が定着しつつあった悟空の等身を大きくするといわれ、担当の鳥嶋和彦(そう、あのDr.マシリトだ)は大反対した。が、そうでないと連載を続けられないと鳥山にいわれ、西村編集長に相談する。すると〈「いいじゃん別に。そうしたいんなら。」って冷たくいわれて。〉*4と述べている。前回の終わりに触れた、西村の『ドラゴンボール』への低い評価もそうだが、西村は自らのジャンプ路線からズレている鳥嶋、鳥山に対して評価が低い。そうしたことを隠さず言ってしまう西村の直裁さも興味深いが。
鳥嶋はまた、桂正和に『ウイングマン』(83~85年)『電影少女』(89~92年)などを描かせ、西村が否定的だったラブコメ路線をジャンプに引き込んでいる*5。それに関して、〈この頃から『ジャンプ』が、何か子供の手から離れていくような印象が〉あったとするインタビューアーに対して、西村は〈『バスタード』にしても『電影少女』にしても、『ジャンプ』では本来載せちゃいけないマンガなんですよ。〉*6と答えている。西村の中には自ら信じる「少年マンガ」の原型が強固に存在していた。それは盟友だった本宮ひろ志マンガのような男の子世界だったのかもしれない。少年マンガは、まっすぐで無垢であるべきで、マニアックであってはならないのだ。
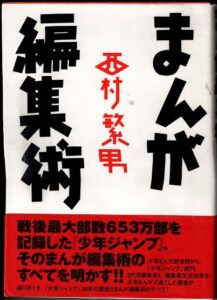
鳥嶋はそこに新しい遺伝子を持ち込み、その後のジャンプを構築していった。もうひとつ鳥嶋が持ち込んだ重要な遺伝子に、ゲームへの進出がある。『ドラゴンクエスト』立ち上げにかかわり、93年ゲーム雑誌「Vジャンプ」創刊編集長となり、メディアミックスの拡大に貢献している。西村は、86年、すでに編集長を退任していた。西村、鳥嶋の例には、同じジャンプ編集部内での一種の対立構図があるように見える。私のような外部の人間からすると、そうした対立こそが当時の最盛期ジャンプの力学であり、エネルギーだったのではないかと思えてならない。
ただし、ここで注意しなければならない。我々はえてして、こうした対立、競争、闘争の図式で複雑な現場をのちの観点から理解してしまう。それは「三国志」のような面白さとわかりやすさで受け手にも受け入れられ、結果として「歴史」という幻想、イデオロギーを構築してしまいがちなのである。だが、本当にそうだったかと、あらためて問う必要がある。
実際のところ、当時のジャンプ編集部がどうだったのかは、当事者でない私にはわからない。そうした対立がどの程度深刻に存在したのか、あるいは案外和気藹々としたところもあったのか(それはないか・笑)。そのあたりは当事者たちに詳細な取材を重ねない限り見えてこない。けれど、困ったことにマンガ編集という閉鎖的な世界では、そうした情報はめったに流失してこないのだ。それでなくても、現場の当事者というのは案外正確に自分を把握できておらず、外部に説明する言葉を持っていないことが多い。我々のような立場では、いつもわかりやすく面白い構図で歴史を描き、受け手に興味をもってもらわねばならない。と同時に、じつは案外そうじゃないかも、という視点を常に持って相対化を組み込んでいかねばならないのだろう。
- *1 ^ 「鳥山明・鳥嶋和彦 最強対談」『Dr.マシリト最強漫画術』集英社 2023年 P.125 鳥嶋の発言。そういう発想は〈あなた[鳥山明]以外に秋本さん亡くなった高橋和希からしか聞いたことがない。〉とある。 [ ]は引用者注。
- *2 ^ 同上。P.122
- *3 ^ 同上。P.125
- *4 ^ 同上。P.122
- *6 ^ 西村繁男『まんが編集術』白夜書房 99年 P.307