こちらの記事は後編です。前編はこちら。
漫画表現のビジュアル化
明治37(1904)年に日露戦争が起こると、戦争報道への関心が高まり、数多くの雑誌が刊行される出版ブームが起こりました。漫画を売りにした物も多数登場しますが、その中でも北沢楽天が中村弥二郎と共に創刊した『東京パック』は、大判のカラー印刷で大成功を収めます。『東京パック』豪華な誌面は、それまでの言葉主体から、ビジュアル主体へと諷刺漫画の表現を大きく転換させるものとなりました。また、コマ割り漫画やエッセイなど多様なコンテンツが掲載され、幅広い層が楽しめる雑誌になっていることも、注目すべき点です。

『東京パック』の発行部数は6万部程度だったとされますが、楽天は主筆として雑誌の売り上げの数%を貰う契約を結んでいたため、月俸2000円という大金持ちになりました。(ちなみに明治40(1907)年に東京朝日新聞に入社し、社長より高いと言われた夏目漱石の月俸は200円)これはかなり例外的な例ではありますが、誕生したばかりの漫画家という職業は当たれば大きく儲かる職業ともなりました。
また、楽天は人材の育成にも力を入れており、自らの内弟子(小川治平や下川凹天)を養成するだけでなく、若い画学生などを雇い入れ、漫画を描ける人材を育てました。『東京パック』には、川端龍子、坂本繫二郎、石井鶴三、山本鼎、前川千帆、幸内純一など、その後の美術界や漫画界で活躍する錚々たる面子が執筆しており、楽天の才能を見抜く眼力の確かさが解ります。
漫画家の活動範囲の拡大と物語表現の開拓
大正期に入ると、様々な新聞に漫画が載るようになり、週一回の漫画ページなども真似する新聞が現れました。
大正4(1915)年には、新聞社に所属する漫画家たちが集まって「東京漫画会」が結成されます。これは漫画家たちの親睦と職業認知の向上を目指した団体で、漫画の展覧会を開催したり、漫画祭というイベントを開催しては、その様子を各自が所属する新聞紙上で面白可笑しく発表して注目を集めました。こうした活動により漫画家という職業は広く認知されはじめ、一般の雑誌などにもその活動の範囲を広げていきました。大正末ごろには漫画家は一種の文化人として扱われ、マスコミにもしばしば登場するようになっていきます。

東京漫画会の第一回の漫画祭に参加したのは10名の作家でしたが、大正12(1923)年に「日本漫画会」に改組をした時には20名の漫画家が名を連ねました(樺島勝一も特別会員として参加しています)。漫画家が有名になったと言っても、職業として漫画家を名乗れていた人は、その程度しかいなかったのです。
東京漫画会の活動の中心となった岡本一平は、大正元(1912)年に東京朝日新聞に入社し、頭角を現してきた新進の漫画家です。夏目漱石も認めた文章センスと、自己プロデュース力の高さで、「総理大臣は知らなくとも、岡本一平の名は知っている」と言われるほどの超人気漫画家へとなって行きます。

岡本一平は滑稽な絵と同程度のスペースを文章に割いた「漫画漫文(まんがまんぶん)」のスタイルで人気を博しました。これは一平が文章を得意としていたのもありますが、限られた新聞紙面で読み応えのあるコンテンツを載せるために考え出されたスタイルとも考えられます。
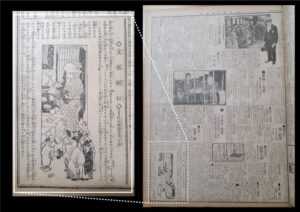
文章の割合がかなり多い漫画漫文は、現在の感覚では漫画と認識するのは難しいかもしれませんが、そもそも、フキダシが一般化する以前は、コマ割り漫画にも説明文が添えられていることは普通であり、娯楽の少なかった時代にあっては好まれていた可能性が高いです。
一平は当初、漫画漫文で探訪(リポート)漫画などを描いていましたが、やがて漫画漫文の物語を描きはじめます。特に息子の太郎が物心がついてくると、子供に読ませる漫画を描こうと子供向け雑誌に「珍助絵物語」などを発表。大正10年には東京朝日新聞に長編の物語漫画「人の一生」を連載、漫画での長い物語表現を開拓して行きました。

また、岡本一平の弟子である宮尾しげをは「正チャン」の始まる前年の大正11年に『東京毎夕新聞』にて子供向けの連載物語漫画「漫画太郎」を連載し人気となっていました(ただし、日刊連載ではない)。新聞でも子供向け漫画の需要が高まっていたのです。

『正チャン冒険』は、このような漫画表現の多様化と、新聞という媒体での漫画の普及・浸透、漫画で物語を描くという試行などが背景にあって登場することになるのです。
マンガ誕生100周年記念プロジェクトのウェブサイトはこちら!




