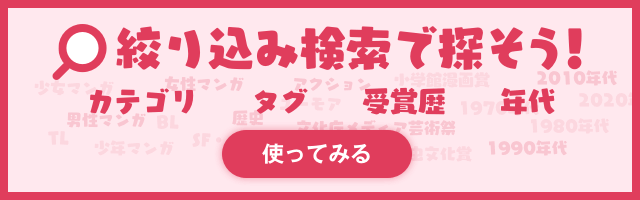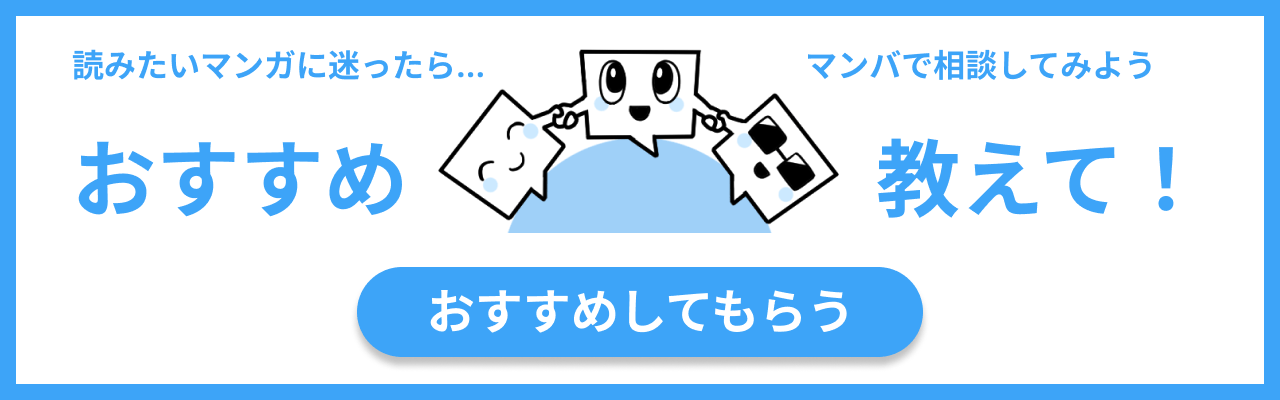写真/後藤武浩
感染症をめぐる医療ミステリ『インハンド』、パンデミックものの新たな名作『リウーを待ちながら』など、医療にまつわる作品を描き続けるマンガ家・朱戸アオ。彼女が医療マンガを描くに至った経緯や、作品づくりについて考えていることについてインタビューをおこなった。てっきりそういう分野を大学で学んでいたのかと思いきや……。

朱戸アオ(あかと・あお)
2010年、アフタヌーン四季賞冬のコンテストにて、準入選を受賞。2011年、都心の湾岸地区で起こったパンデミック(感染症の大流行)を描いた『Final Phase』で単行本デビュー。「アフタヌーン」にて2013年『ネメシスの杖』を、2016年『インハンド 紐倉博士とまじめな右腕』を連載。その後「イブニング」で、『リウーを待ちながら』連載(全3巻)、医療サスペンスの新たな描き手として注目を集め、現在は『インハンド』を「イブニング」に連載中(現在1巻まで刊行)。『インハンド』は2019年、TBS系列にて山下智久主演でドラマ化されたことでも話題を呼んだ。
美大出身のマンガ家が、医療マンガを描くまで
──朱戸さんの作品って、ドラマ化された『インハンド』だけでなく、単行本デビュー作の『Final Phase』や、そのリメイク作『リウーを待ちながら』など、医療ものが多いですけど、もともと医療の分野に関わりがあったんですか?
いや、実は大学は美大だったんです。
──美大! 進学するときからマンガ家になることを意識していたとか?
美大といっても建築科なんですけど。高校が進学校だったので、「大学に行かない人生」をイメージできなかったんですよね。幽霊部員ではあったけど漫研には入っていて、「マンガ家になりたい」とも思ってたんですけど、それと大学進学が結びつかなくて。マンガ家以外にもいくつかなりたい職業があって、それで選んだのが建築科だったんです。自分の得意科目で入れそうなのが美大系の建築科だったので、それで美大に。
──在学中もマンガを描いていたんですよね?
4年生のときに初めて持ち込みをしました。スピリッツ編集部だったんですけど、「読み切りを持っていく」という基礎的なことも知らなくて、400ページくらい持って行って「読んでください」って(笑)。
──4年生って、進路を決めなきゃいけない時期ですよね。どんな風に考えていたんですか?
「マンガ家になりたいんだけど」と親に言ってみたら、「許さん!」みたいな話になったんですよ。親の価値観からすると「マンガ家になる」なんてとんでもないことなので。それでしょうがないから勉強して大学院に進学しました。その間にしっかりマンガを描こうと思って。当時、「ビッグコミックスピリッツ カジュアル」という雑誌があって、その新人枠でネームコンペがあったんですよ。そこで初めて声をかけられて参加したときのコンペ課題が「セックス」だったんです。「課題を与えられて解く」というのは大学時代ずっとやってきたことなので、スイッチが入って、違う種類の3本のネームを描いて、そのうちの1本が採用になって、大学院1年生のときにデビューしました。そこでようやく「マンガ家になるか」と決めましたね。スピリッツの新人をやりつつ、当時『日本沈没』のコミカライズをされていた一色登希彦先生のところでアシスタントをしてました。

──そこからの道のりは?
それが、その後が大変で。スピリッツカジュアルは無くなるし、ヤングサンデーが廃刊になって、その連載が9本スピリッツに移籍してくるし、私のマンガはもう全然載らなくなってしまって。それでアフタヌーンに投稿したりしてました。
──マンガ家になるにあたって、どんな感じのマンガ家になりたいかというイメージは持っていたんですか?
「なんでも描けるマンガ家になりたい」と思ってました。名前を出すのもおこがましいですけど、手塚治虫先生ってあらゆるジャンルを描かれてるじゃないですか。そういうマンガになりたいと。いわゆる「職業もの」みたいな分野にはあまり興味が持てなくて、手塚先生とか、萩尾望都先生とか、大友克洋先生とか、士郎正宗先生とか……巨匠ばかりですけど(笑)、みなさん「●●もの」のマンガ家という感じじゃないですよね。『トーマの心臓』が学園ものかと言われると、ちょっと違う気がしますし。そういうマンガ家が好きなので、私もそうなりたいなと。だから、私のマンガが「医療もの」と言われ始めた頃は、「えっ、私は医療マンガ家なのか!?」と思ってました。
──じゃあ今でも「医療マンガ家」のような自意識はない?
大学の専攻は全然違うので、医療の知識は完全に後付けで勉強したものなんですよ。高校は進学校だったので、医者になった方が何人もいて、その人たちに聞いたりできるという強みはありますけど、勉強した結果こうなったので、勉強すれば違うジャンルのマンガ家にもなれるだろうという感覚はあります。『インハンド』も医療といえば医療ですけど、ちょっと科学寄りだったりしますし。医療ものって、「病院にお医者さんがいて、そこに患者さんが来て、病気を治していく中に泣けるドラマが生まれてくる」みたいなフォーマットがあると思うんですけど、私が描くとそこからはどうしてもはみ出してしまうんですね。
東日本大震災と『Final Phase』『リウーを待ちながら』
──調べ物は専門的な知識がメインだと思うんですけど、たとえば重い病気にかかってしまったときのリアクションや感情のように文学的な部分については、自分自身の中から出している部分が大きいわけですか?
そこは微妙なところですね。自分の中から出す場合もありますけど、たとえば『リウー』の中で、奥さんを亡くした人が奥さんの幽霊を見る話が出てくるんですけど、東日本大震災でそういう心霊現象がすごくあったらしいんです。それについて研究している研究室があって。

──聞いたことあります。東北大の金菱研究室ですよね。事例を集めた本も出てて。
そうです。そういうのを読みながら想像を膨らませていく部分もありました。あと、ローリー・ギャレットの『カミング・プレイグ』という、感染症のエボラと戦った人たちの話を読んだり。といっても「内容をなぞる」というよりは、「本で書かれているこの状況に私のキャラを放り込んだらどうなるだろう?」というシミュレーションをやっている感じですね。
──東日本大震災といえば、『Final Phase』は2011年に連載されていた作品ですよね。震災と連載時期が近いですけど、それは偶然なのか、それともきっかけの一つにはなっているのか。
揺れたときが、ちょうど1話のトビラ絵を描いてたところだったんですよ。
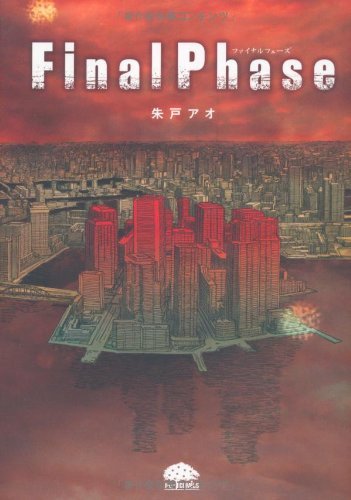
──え、そんなタイミングだったんですね。
でも、その時点では物語全体の流れがだいたい決まっていたから、震災のことは『Final Phase』に反映できてないんです。でも、そのあと(『Final Phase』のリメイクである)『リウー』のお話をいただいたときに、編集の方から「震災後だから描けることがあるんじゃないか」と言われたんですね。あの頃、日本人はみんな震災についていろいろ考えていたと思うんですけど、私も自分なりに考えたことがあったのでそれを反映していけるんじゃないかと思って、『リウー』をやることにしたんです。
──リアルタイムでは描けなかったけれど、むしろ少しタイムラグを置いているからこそ、作品の中に反映できたと。
あと、ちょうど同じ頃(2016年)に『シン・ゴジラ』とか『君の名は』とか、災害をある程度モチーフにした映画がヒットしましたよね。それを見て、ああいうものをエンタメに取り込める時期が来たんじゃないか……という感覚もありました。まだ復興が続いてる場所はいっぱいあると思いますけど、やっぱり震災を消化して「あれはどういうことだったのか」を考える時期に来てるんだろうな……という思いもあって、『リウー』を描きました。
── ところで『Final Phase』の舞台は東京でしたけど、『リウー』では富士山に近い都市に変わってますよね。それは朱戸さんがいま住んでるのが富士山の近くだから?

そうです。ちょっと引っ越してみようと思って田舎に住んでみたら、すごく面白い……という話を編集者さんにしてて。生まれも育ちもずっと東京だったから、1時間に1本しか来ないバスとか、いろいろ新鮮なんですよ。あと、自衛隊の街なので、そこらじゅうで車が操縦訓練してたりするんです。朝、窓を開けると落下傘部隊が落ちてくるのが見えたりとか。そういう生活をしてるので、自分なりに一生懸命調べて、作品にも取り入れました。調べたとはいえ、ミリタリーものに詳しいわけではないので、「ミリオタの人に怒られたらどうしよう」という恐怖はあったんですけど、特に叱られていないので、そんなに間違ってなかったということなんですかね。
──気候も東京と全然違う?
標高500mくらいのところに住んでるんですけど、夏は涼しくて、エアコンがいらないです。だいたい東京からマイナス5℃くらいの気温で、富士山もよく見えますよ。近所の人は「暑い暑い」ってエアコンつけてますけど、「何を言ってるんだ!?」という感じですね。
──富士山は見ていて全然飽きない?
飽きないですね。登ったことはなくて見るだけですけど、いろんな雲がかかるので。地方都市に住んだことなかったから本当に楽しいんですよ。ど田舎ではないんだけど、それなりに田舎で、いいとこ取りの街だなと。
(次ページに続きます)
プロフェッショナルが揉めてるのを見るのが好き
──キャラクターの話になりますけど、『Final Phase』も、『リウー』も、『インハンド』も、「頭が良くて変わり者の男」というキャラクターが共通して登場してますよね。ああいうキャラに思い入れがあるということですか?

私、「バカで頑張り屋さん」みたいな人が描けないんですよ(笑)。これは欠点でもあるんですけど。スピリッツで読み切りを描いていたときに「やっぱり主人公はバカで頑張り屋さんがいいんじゃないか」と思って、そういうキャラクターを描こうとしていたんですけど、全然描けなくて。
──それは自分の中にそういう要素が全然ないから?
というより、頭のいい人やプロフェッショナルな人たちが揉めてるのを見るのが好きなんですね、きっと。「素人がプロの中に入っていって成長する」のがよくある成長物語のフォーマットだと思うんですけど、それがどうにも描けなくて、プロ同士の話になってしまった感じです。でもプロ同士の話をまともに描いてしまうと、とっつきにくい印象になりかねないから、それをなんとかエンタメになるようにする……というのがいつも苦労しているところです。
──『インハンド』の紐倉先生って、最初に登場したときは主人公ではなく、主人公の調査員を助けるポジションでしたよね。でもだんだん主役にシフトチェンジしていって。
これは完全に予想外のことで。もともとは短期集中連載で、続編のことは特に考えてなかったんです。「『Final Phase』がウイルスだったので、次は寄生虫でやってみよう」くらいの感じで描き始めたんですけど、予想外にキャラが立っちゃって、「この人が出てくる続編をもっと描けばいいんじゃないか」という話になっていったんです。後々のことを考えずに作ったキャラクターなのに、まさかドラマ化までされるなんて。
──作品に登場する感染症についてお聞きしたいです。出てくる病名はだいたい聞いたことのない名前で、一瞬「もしかしてマンガのために作った架空の病気なのかな?」とも思ったんです。でも巻末を見るといろいろ参考文献が書いてあって、実在する病気だとわかる。朱戸さんの中で「ストーリーはフィクションであっても、そこに出てくる病気は実在するものでないとダメだ」という倫理観があるということなんでしょうか?
うーん……そこまで何でもありにしてしまうと、もう本当に「何でもあり」になってしまって、逆につまらなくなるような気がするんですよ。
──登場する感染症は、どうやって選んでるんです?
基本的には、感染経路の面白さで選んでます。だからすごくマイナーなものになりがちで。「咳で伝染ってくる」だとわかりやすいけど、実は飲み物で伝染る経口感染なんだよと言われるとオオッ、と思うみたいな。医療ものの海外ドラマで「ドクター・ハウス」というのがあるんですけど、あれは完全に「安楽椅子探偵」フォーマットなんです。つまり現場に調べに行かず、診察をせず、自分は部屋にこもってるけど、部下が情報を持ってきて「これだ」という答えを出すという。でも感染経路の要素を入れると、そこにドラマが生まれるんですよね。
──そうですね。「感染経路がわからない」というのが、そのまま得体の知れない恐怖感に直結したりしてて。
ミステリーの要素として感染症があって、それを紹介しつつ、感染経路が謎解き的にわかるのがいいかなと思って、感染症を選んでるんです。調べたことをベースにしているとはいえ、細かい部分では嘘をついてる箇所も実はあるんですけど、でも基本的に「奇跡的に回復した」という話にはならないですね。現実に存在する感染症を使って、「この感染症にはこういう困難さがある」というのをベースに作っています。
──「架空の病気を入れたら何でもありになる」というのは、医療ものだと確かにそうだと思いますが、そういうスタンスは仮に他のジャンルのマンガを描くとしても共通している?
今描いているのは全部医療ものだから、全部そのスタンスで描いていますけど、他のジャンルでもきっとそうだと思います。医療マンガを描く前、たとえばアフタヌーンに投稿したのは画家の話だったんですけど、でも「画家と画廊の関係」みたいな部分はリアルに描きたいと思って調べ物をしていたので。もしファンタジーを描くことになったとしても、民族衣装を調べたりするんだろうなと思います。「調べ物をしっかりしてリアリティのある話を描ける」というのがどうやら自分の強みだとだんだんわかってきたので、それを手放す道理はないなと。
子育ても含めて人生
──以前に比べると、仕事のペースは上がってきているんですか?
いや、子供がまだ小さいんですよ。4歳になる子と1歳半の子がいて。『リウー』の最終話を描き終わった1週間後くらいに下の子を産んだんです。
──そんなタイミングだったんですか!
で、産んで2カ月後くらいに『インハンド』のドラマ化の話が来て。ドラマ化の話は授乳しながら聞いてました。
──乳児を育てつつ、マンガも描くの、相当ハードなんじゃないですか?
だから育児の息抜きがマンガ、マンガの息抜きが育児みたいな生活です。今は夜泣きもなくなってだいぶ楽になりましたけど、ここ数年は気力体力の限界という感じでした。「独身でマンガだけに集中してたら、もっとハイペースで描けたんじゃないかな」とも思いますけど、でも子育ても含めて人生なので。

──アシスタントも入れてるんですか?
デジタル作業で何人かいます。ガッツリ入ってやってもらうアシスタントさんはいなくて、「トーン貼りだけお願いします」みたいな感じで頼んでいて。高校の同級生にトーン貼り頼んでるんですけど(笑)。デジタルだと、絵を描けなくてもトーン貼りはできるので。アシスタントはネットで応募して、ネット経由でお仕事をお願いしているので、一度もお会いしたことない方もいます。
──今、そんな感じなんですね。『リウ―』と『インハンド』を描いたことで、自分のマンガ家としての進む道は見えた感じですか?
よく「処女作にすべてが詰まっている」みたいなこと言われますけど、私にとっては『Final Phase』が重要だったのかなと思うんですよね。『Final Phase』と『ネメシスの杖』が自分の中でポイントになる作品で、今はその延長線上で描いてる感じです。
──自分のマンガがドラマ化されるというのは、原作者にとって嬉しさ以外にどんな意味合いがあるんですか?
私はまだまだマイナーなマンガ家なので、山下智久さん主演でドラマ化されたことで、今まで見たことのない感想をたくさん見られるのがとても新鮮で。それで自分の長所も欠点もなんとなく見えてきたように思います。「山Pカッコいい!」みたいな感想もあるんですけど、実はそれも重要なことで。
──どういうこと?
ここ数年の私の課題なんですけど、「プロットの面白さのほうには力を入れてるけど、私のマンガにはリビドーが足りないんじゃないか」と思ってて。そういうところも含めて、次のネタのいいフィードバックになればいいなと思います。ドラマ化して感想もらえるって、そうそうない機会なので。
──ドラマには、原作にはないオリジナルのエピソードも出てきてましたね。あれは?
『ネメシスの杖』と『インハンド』の間に2年半くらいあって、その間に書いたプロットでお蔵入りになっていたものがいろいろあったんです。自殺させるウイルスの話とか。それをドラマの打ち合わせのときにお渡ししていたら採用されることになって。自分なりにいろいろ調べて作ったプロットなのにお蔵入りしてしまって、2年半が無駄になってしまっていたのが、ドラマのおかげで日の目をやっと見られて、非常にありがたいお話でした。画面に一瞬映る研究ノートだって、作るのが大変だというのは分かっているので、美術さんも素晴らしいお仕事をされていたと思います。
──「この先、こういうものを描いてみたい」というのはありますか?
しばらくは『インハンド』をこれからどう進めていくかを考えるのでいっぱいいっぱいだと思いますね。他にもやりたいネタはあって、少しずつ調べたりしてるんですけど、とにかく『インハンド』が大変すぎて。『リウ―』の単行本3冊分で調べたことを、『インハンド』5話分で使い切っちゃうくらいのペースなんですよ。毎回の事件ごとに違うネタを勉強しなきゃいけなくて、本当に頭パンクしそうなんです。勉強もしないといけないし、ミステリーのプロットも書かないといけないし、大変です。つらいです(笑)。でも楽しんで読んでいただけたなら、それが本望ですね。

*本文中に登場した朱戸アオさん原作のドラマ『インハンド』はParaviにて配信中(※記事公開時の情報です)。