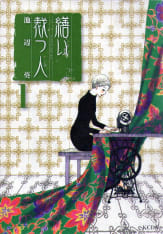1 はじめに
2009年2月、村上春樹はエルサレム賞の受賞挨拶で「もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます」*1と宣言しました。「壁」と「卵」のメタファーに関して、彼はつぎのように説明しています。
こう考えてみてください。我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにひとつの卵なのだと。かけがえのないひとつの魂と、それをくるむ脆い殻を持った卵なのだと。(略)そして我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにとっての硬い大きな壁に直面しているのです。その壁は名前を持っています。それは「システム」と呼ばれています。*2
このように述べたうえで、彼は自分が小説を書く理由は「個人の魂の尊厳を浮かび上がらせ、そこに光を当てるため」であり、「我々の魂がシステムに絡め取られ、貶められることのないように、常にそこに光を当て、警鐘を鳴らす」ことこそが物語の役目だと聴衆に語りかけました。*3
もとより、これは小説に限らずマンガを含むすべてのナラティブ・メディアの役割にほかなりません。物語とは一人ひとりの魂にときに寄り添い、ときに賦活する存在たりえます。複雑化し混迷を極める現代を生きる「壊れやすい卵」のもとに正しい物語を届けたい。そのささやかな思いから、筆者はいま、この文章を書いています。
本連載では多くの方がお手にとりやすいように、比較的短めのマンガ作品を中心に紹介したいと考えています。また、対象は、できるかぎりここ20年のものに限定するつもりです。これは日ごろよりマンガに関心を寄せている一群を除き、普通の読者がリーチするのが、リアルタイムの大ヒット作や90年代以前の古典的名作といった抜群の知名度を誇る一部に限られる傾向が、近年強まっていると感じているためです。
インターネット環境とマンガの電子書籍形態が当たり前になった現代は、これまでになくマンガへのアクセスが容易な時代といえます。ですが、知名度の高い作品以外は受け手に十分に訴求できていないのが現状です。
世界がインターネットに覆われる以前の1990年代までは、一人の送り手によって語られる一つの物語を受け手が消費する一方通行的な「コンテンツ」が娯楽の中心でした。ところが、メディア環境は劇的に変化し、無数のユーザー同士によって交わされる無数の物語(の断片)、すなわち双方向の「コミュニケーション」が娯楽の中心となりました。
可処分所得と可処分時間が限られるなかで、マンガは現在、残念ながら余りコストパフォーマンスに秀でた娯楽と見做されていないのだと思います。マンガを読むには普通時間とお金がかかります。気心の知れた友人とSNSを通じてやりとりをする方がコスパが高いという感覚が生まれるのは当然でしょう。また、相応のコストをかけるからには「ハズしたくない」という思いから、人々が手に取るのが、コミュニケーションのネタにもなるリアルタイムの大ヒットコンテンツや、既に評価の定まった90年代以前の古典的名作に偏ってしまう傾向も概ね理解できます。
しかし、マンガとは、ひいては物語とは、単なる娯楽ではありません。村上春樹が説くように、物語とは私たちの魂がシステムに絡め取られ貶められることのないように個人の魂に光を当ててくれる不可欠な存在だと、筆者は信じています。こうした観点から本連載を「壊れやすい卵のための21世紀マンガレビュー」と名づけました。
2 作者・作品紹介
今回ご紹介するのは、村上かつら『淀川ベルトコンベア・ガール』(全3巻)です。『月刊!スピリッツ』に2009年10月号から2011年9月号にかけて連載されました。
村上かつらというマンガ家の魅力は一見分かりにくいと思います。作画は丁寧ですが、画力はそれほど高くありません。コマ割りもオーソドックスで、正直にいえば地味な作風です。岡崎京子やよしもとよしともに似ていた初期の方が、画風にしても演出にしても、むしろセンスが感じられたように思います。
あまり器用とはいえない彼女のマンガには、やはり器用とは言い難い性格の人物たちが登場します。作者の人柄が滲み出ているのでしょうか。個人的には、こうした不器用さこそが作者の最大の魅力だと思います。この不器用さは、誠実さにほかならないからです。
本作は大阪・淀川の川べりにある食品工場で働く少女・瀬川かよと、工場にパートとしてやってきた名門私立進学校に通う女子高生・黒崎那子との出会いを皮切りに10代の少年少女の成長を描いた青春劇です。
かよは地元を離れて一人で暮らしています。職場の人たちは親切ですが、ほとんどが中高年です。かよには同世代のともだちがいません。工場の行き帰り、友人同士で語らう高校生たちとすれ違い、孤独を感じていたかよは、16歳の誕生日に淀川に架かる鉄道橋の下で「ともだちが、ほしい!!」と願掛けをします。[図1]そんな折に出会ったのが一つ年上の美少女・黒崎那子でした。

工場内の盗難騒ぎをきっかけに那子との交流が始まります。そして二人の仲が深まるにつれて、かよの小さな世界が少しずつ開かれていきます。読者はおそらく、世代に応じて彼女たちに共感したり、職場の先輩で何かとかよの世話を焼くお姉さん的存在の大沢スミ江に同一化したりしながら、かよの16歳の一年間を見届けることになります。
3 経済格差というモチーフ
日常における人物描写に冴えを見せる作者のペン先が本作で描き出すのは、残酷なまでの経済格差です。
瀬川かよは家庭の事情により高校進学を断念し、福井から単身大阪に出て、豆腐と油揚げをつくる中小企業・はせ食品の社員寮に住み込みで生活しています。暮らしぶりは質素そのもの。何かが落ちていると換金できないだろうかと考えるのが、かよの「ふつう」です。[図2]

黒崎那子の家庭は娘を名門私立に通わせられる程度には生活に余裕があります。にもかかわらず那子がアルバイトをしているのには事情があります。那子はファッション誌の読者モデルもつとめるお嬢様・天川エリカとクラスメイトです。彼女はオーダーメイドのアクセサリーを購入したり、服を買いに東京に出かけたりと、裕福な学校生活を送っています。那子が学校に内緒でバイトをしているのは、このエリカを中心としたグループに属しつづけるためです。[図3]

本作は物語を通じて、貧乏な子、普通の子、裕福な子、三人の少女の格差を浮き彫りにします。村上春樹風にいえば、各々のやり方で資本主義と対峙する個人を描いた作品です。かよはもとより、那子の苦しみに寄り添ったことで、間口の広い作品になりました。エリカを単なる悪者にしなかった点には、作者の人間に対する洞察を感じました。
ところで、本作は単独で支障なく楽しめますが、じつは2003年に『週刊ビッグコミックスピリッツ』で短期連載された「純粋あげ工場」(『CUE』第3巻所収)の後日譚として構想されています。
執筆経緯を記した第1巻のあとがきで、作者は興味深い証言を行っています。曰く、世の中の変化により七年の間に主人公の設定のリアリティが一変していた、2003年には16歳の少女が高校にも行かず町工場に住み込みで働くという設定が不憫すぎるとの理由で編集者と議論が交わされたが、2010年には中卒の少女を正社員として雇用し社員寮の個室を与える会社の設定が好待遇すぎるとの理由で議論が交わされた、と。*4
以上を踏まえて、主人公のかよにフォーカスしてまとめるならば、本作で村上かつらが抗ったのは、個人を搾取し魂の尊厳を貶める「新自由主義」という名の忌まわしきシステムだといえます。これが2020年現在においてもアクチュアルな問題意識であることは言うまでもありません。
4 不器用さの肯定
かよは、那子、那子の級友・エリカ、はせ食品の一人息子で、幼馴染の那子に思いを寄せる長谷川ヒロキといった同世代と関わることで楽しみや喜びを知り、ときに翻弄されて痛みや苦しみを味わいながら、やがて「さみしいのは、他人との繋がりが弱くなってるときじゃなくて、ほんとは、自分とうまく繋がっていないときなんだ」と自身の感じていた孤独の本質に気づきます。かよは自分の気持ちと向き合い、スミ江に背中を押されながら前を向いて新たな一歩を踏み出す決心をします。
かよをはじめ不器用な若者たちが、自分を殺して現実と折り合いをつけるのではなく、一度きりの人生で悔いを残さぬよう、自分に正直に生きていく不器用な姿を肯定しながら、本作が彼らそれぞれに未来への希望を提示したうえで幕を下ろしたことに、筆者は感動しました。このような分かりやすい希望は従来の村上かつら作品では示されていなかったからです。
5 『リバーズ・エッジ』からの転向
ここで、本作と同じく川べりを舞台に少年少女たちの出会いと別れを描いたある著名なマンガ作品を補助線にしながら、本作における転向の意義を考えたいと思います。その作品とは岡崎京子『リバーズ・エッジ』(『CUTiE』1993年3月号‐1994年4月号)です。
女子高生・若草ハルナは、いじめられていた同級生・山田一郎を助けたことをきっかけに彼の秘密の宝物を教えられます。それは河原に放置された人間の死体でした。ゲイの山田と、レズビアンで摂食障害のモデル・吉川こずえは、唯一腐敗し白骨化しつつある死体を見ることで生を実感するといいます。山田を執拗にいじめるハルナの恋人、山田に一方的に好意を寄せる少女、父親の分からない子を妊娠するハルナの友人、その友人のオタクで引きこもりの姉。これらの登場人物たちが絡み合いながら不穏な物語が進行していき、ついに新たな死体が生まれます。
周知のとおり、岡崎京子の代表作であるのみならず90年代サブカルチャー全般を代表する傑作です。岡崎はバブル崩壊後の東京では都市の表層下に抑圧していた自然が回帰しつつあることを敏感に嗅ぎ取り、東京郊外を舞台に、むしろ露わにされた自然にこそ安寧を見出しました。グロテスクな自然に目を向けて慰安をおぼえる経験によってこそ、逆説的に「平坦な戦場でぼくらが生き延びること」*5が、すなわち平凡な日常を私たちが生きていくことができる、そう岡崎は感受性豊かな読者に訴えたのです。
村上かつらの初期作品には岡崎京子の作風が色濃く影を落としています。作者はこれまで主人公たちが不幸をまといながらも、日常へと帰ってささやかな幸せを生きていく結末を好んでいました。救われているような、いないような、なんとも曖昧な結末は、現実を「平坦な戦場」と捉える『リバーズ・エッジ』の認識と、感覚のうえで地続きだったはずです。
しかし、本作は違いました。終盤はやや駆け足になりましたが、登場人物たちそれぞれの成長が実感できる大団円を迎えました。これは村上かつらの愛読者から見れば、決定的な変化でした。それではこの転向は何によってもたらされたのでしょうか。
6 契機としての東日本大震災
最終巻のあとがきで、作者は2011年3月11日に起きた東日本大震災を受けて、ラスト2話を当初の予定とは全く別の内容に差し換えたことを明かしています。*6メディアを介して剥き出しの自然の猛威と莫大な死者の存在に触れ、一瞬にして日々の平穏な暮らしを奪われた大勢の人たちを目の当たりにし、作者はもはや戦場が平坦だとは(日常が平凡だとは)感じられなくなったのでしょう。作者の転向をもたらしたのは、この「3.11」の衝撃にほかなりません。
かくして未曾有の大災害を経て変更された結末に示されたのは、登場人物たちの前途を照らす希望でした。2020年現在、日々の生活で暗く孤独な戦いを強いられているあまたの壊れやすい魂のもとに、とりわけ新自由主義、自然災害、コロナ禍等によって経済的苦境に立たされ尊厳を貶められている方々のもとに、この光が届くよう願っています。
7 おわりに
終盤、スミ江がかよに別れを告げ、淀川の川べりにある小さな食品工場から外の世界へ出ていくよう促す、本作屈指の名場面があります。「――かよっぺ、(略)あんたはちゃうやろ? ここに居つづける人間とちゃうやろ」と語りかける、そのスミ江の台詞と表情に、筆者は作者の声を聞き、まなざしを見出します。[図4]

村上かつらが休筆して、もう六、七年になります。事情は不明ですが、惜しくてなりません。勝手ながら、作者はマンガを描くべき人間だと確信しています。彼女が復帰を果たし、ふたたび壊れやすい卵のための物語を不器用に紡いでくれることを、筆者は心待ちにしています。
[註]