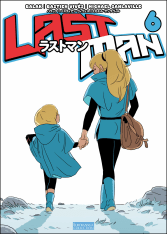早いもので2019年も残すところあと数日。1年の終わりということで、今年1年を振り返ってみると、筆者が調べた限りでは、紙と電子を合わせて約160点の邦訳海外マンガが単行本として出版された。とりわけ電子について何をもって単行本とするのか等、実はいろいろややこしい問題があったりはするのだが、それはさておき、とにかく今年2019年も決して多くはないにせよ、少ないとも言えない数の邦訳海外マンガが出版されている。
それらの邦訳をザッと見渡すと、一番多いのはやっぱりアメリカのコミックス。ひと口にアメリカのコミックスと言っても、スヌーピーで知られる『ピーナッツ』からDC、マーベルのいわゆるアメコミまでさまざまだが、それらが全体の約6割を占めている。
フランス語圏のマンガ“バンド・デシネ”はそこまで多くもなく、全体の1割強。案外多いのが韓国を中心としたアジアのマンガで、約2.5割を占めている。実は韓国のマンガはアプリ上で邦訳されている作品がすごく多いので、それらをカウントすれば、一番邦訳が多いのは韓国のマンガということになるのではないかと思う。
アメリカのコミックスにしろ、バンド・デシネにしろ、韓国のマンガにしろ、日本でもある程度なじみのある海外マンガと言っていいかと思うが、毎年、これらのおなじみの海外マンガに混じって、あまりなじみのない地域の海外マンガもちらほら出版される。今年目立ったのは北欧のマンガで、以下の作品が出版された。
・アンナ・フィスケ『話し足りないことはない?―対人不安が和らぐグループセラピー』(枇谷玲子訳、晶文社)
・マルタ・ブレーン作、イェニー・ヨルダル画『ウーマン・イン・バトル―自由・平等・シスターフッド!』(枇谷玲子訳、合同出版)
・アンネッテ・ヘアツォーク作、カトリーネ・クランテ、ラスムス・ブラインホイ画『北欧に学ぶ 好きな人ができたら、どうする?』(枇谷玲子訳、晶文社)
・モーテン・デュアー作、ラース・ホーネマン画『ZENOBIA ゼノビア』(荒木美弥子訳、サウザンブックス社)
・アンナ・フィスケ『あかちゃんはどうやってつくられるの?』(さわきちはる訳、河出書房新社)
最後の『あかちゃんはどうやってつくられるの?』は、絵本として出版されている作品だが、考えようによってはコマのないマンガと言えなくもない。『話し足りないことはない?―対人不安が和らぐグループセラピー』と同じ作者の作品で、こちらはコマのあるれっきとしたマンガである。
今回はこれらの北欧のマンガの中から、アンナ・フィスケ『話し足りないことはない?―対人不安が和らぐグループセラピー』(枇谷玲子訳、晶文社)を紹介したい。北欧のマンガとひとくくりにするのも雑な話だが、今後さらに邦訳が増えていくことで、筆者を始め、読者の側の知識も増えていくことだろう。『話し足りないことはない?―対人不安が和らぐグループセラピー』は、北欧は北欧でもノルウェーのマンガで、原書は2014年に出版された。地味な小品(全97ページ)だが、多くの人に読んでほしいコミュニケーションをめぐるアクチュアルな名作だと思う。

ページを開くと、「9月第1週」と書かれた見開きの扉があって、続いてひとつの部屋に集まって話をしている7人の人物が描かれる。
年配の女性が会話の口火を切る。彼女には娘がいて、この集まりの前日に遊びに来てくれてうれしかったのだが、娘が帰ってしまったとたん、虚しい気持ちに襲われたのだという。会話はそのまま既婚者は友情をなおざりにしがちだというテーマをめぐって転がっていき、続いてひとりの女性が、週末のたびに母親が遊びに来るのだが、1日目はともかく、2日目になるとイライラしてしまうと切り出す。また、ある男性は、IKEAでパニック障害に陥ったが、薬を飲んでこの集まりで習った呼吸法をしたらおさまったという体験を語る。

副題にあるとおり、彼らは対人不安=対人恐怖症をわずらっている人たちで、週に一度セラピストを囲んで集まり、グループセラピーを受けているのだ。
グループセラピーとは、同じ問題を抱える人たちが集まり、グループで話し合うことで、不安を共有すると同時に、自分への理解を深める心理療法のこと。この作品に登場するセラピストは、グループセラピーを「自分たちの社会的境界線(ボーダー)や限界を探る、人付き合いの実験の場」(P052)と語っている。

本書の構成は、9月第1週から10月第3週までの全7章(7週間)。各章のページ数は6ページから16ページまでまちまちだが、いずれにせよどれも短い話である。
グループセラピーに参加しているのは7人だが、そのうちひとりはセラピストで、主な登場人物はマーリ、ペール、グレータ、スタイナー、シーヴ、アリの6人。週(章)ごとにまずはグループセラピーの様子が描かれ、その後、グループセラピーに参加している彼ら彼女らの日常がひとりずつ順番に語られ、最後の第7章に当たる10月第3週は、グループセラピーの様子だけで締めくくられている。
対人恐怖症というと、多くの読者から自分とは無縁のことと思われてしまいそうだが、6人の登場人物が抱えている問題は多かれ少なかれたいていの人に当てはまる問題で、およそ他人事ではない。
例えば、マーリは夫とふたりの子供と暮らしている女性。週末ごとに母親が遊びにやってくるが、何かといえば不満をこぼし、無神経で、旧弊な価値観の持ち主である母親とうまくコミュニケーションできず悩んでいる。ペールは企業に勤める独身男性で、日中は働き、夜はテレビでお笑い番組を見る日々を繰り返している。同僚とはほとんど会話をせず、職場で定期的に行われるモチベーションアップ研修が苦手。グレータは年配の女性。夫と別れ、娘も結婚して巣立っていったので独り暮らし。ところが、独身生活を楽しむというのとはほど遠く、趣味もなく友達もいないため、寂しい思いをしている。娘がよく訪れるが、遊びに来ているのか、洗濯をしに来ているだけなのかわからない始末。娘が帰ったあとは決まって孤独感に苛まれる。最近はささいなことで涙を流してしまう……。といった具合である。

作者はグループセラピーの様子とそれに続く参加者の日常を、引き気味のショットで淡々と描いていく。定期的に登場人物たちの足元が描かれるのが印象的ではあるが(どういう狙いがあるんだろう?)、それを除けば、登場人物が大写しになることも、アングルが切り替わることもほとんどない。マンガの画面としてはいささか退屈だが、コミュニケーションに問題を抱える人々を描いた作品ということを考えると、派手な演出をしたり、ちょっといい話に仕立て上げることを断固として拒否しているのではないかと、深読みしたくなる。
登場人物たちそれぞれの人生が口当たりのいい物語になって消費されてしまうことは、おそらく作者の本意ではあるまい。もちろんそういう物語だってあっていいわけだが、本書はそういう作品ではない。実際、本書には、グループセラピーのおかげで登場人物たちの対人恐怖症が克服されました、などという結末は用意されていない。
登場人物たちはそれぞれ違和感を抱えながら日常を生きている。違和感は職場の同僚や赤の他人との間にだけ生じるのではない。家族との間にも横たわっている。彼ら彼女らはしばしば自分の気持ちを表に出さず行動しがちで、その寡黙さはどこかアキ・カウリスマキの映画の登場人物たちを思わせる(アキ・カウリスマキは同じ北欧でもフィンランドの映画監督だが)。ついつい自分の内側に貯め込んでしまいがちなもやもやした気持ちを、登場人物たちはグループセラピーを通じて、とつとつと言葉にして紡ぎ、おそるおそる他の参加者たちと共有していく。作者の狙いは、そのたどたどしい模索を視覚化することにこそあるのだろう。この一見不器用なマンガは、その不器用さゆえに胸に迫る。
10月第1週のセラピーで幼馴染の自殺について語ったアリに対して、セラピストが「話し足りないことはない、アリ?」と尋ねる。この言葉が本書のタイトルになっていることは言うまでもない。アリはそれに対して、「十分さ。余計なことを言いすぎたって、ちょっぴり後悔してるぐらいさ」と答える。もちろんなんでもかんでも話せばいいというわけではない。時には話したことで後悔することだてあるかもしれない。それでも、私たちには誰かと話をすることが必要なのだ。