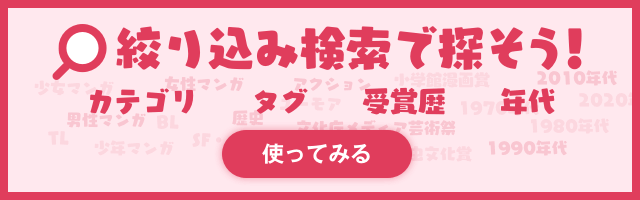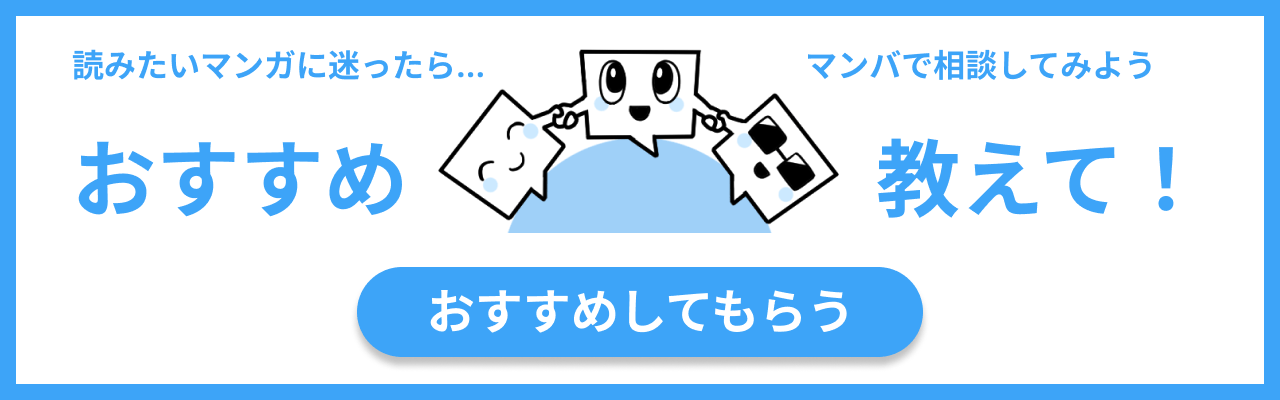マンガの中で登場人物たちがうまそうに酒を飲むシーンを見て、「一緒に飲みたい!」と思ったことのある人は少なくないだろう。酒そのものがテーマだったり酒場が舞台となった作品はもちろん、酒を酌み交わすことで絆を深めたり、酔っぱらって大失敗、酔った勢いで告白など、ドラマの小道具としても酒が果たす役割は大きい。
そんな酒とマンガのおいしい関係を読み解く連載。9杯目は、海の生き物たちが集う小さな酒場で小さなドラマが展開される『バー・オクトパス』(スケラッコ/2019年~20年)をご紹介しよう。

サンゴ礁の海の奥に、その店はある。「バー・オクトパス」という名のとおり、マスターはタコ。手(足?)が8本あるので、カクテルを作るのも手際がいい【図9-1】。無口というか基本的に言葉を発することはなく、たまに口から吐く墨が「え?」とか「ぎょっ」とかいう形になる独自のコミュニケーション方式は、映画『メッセージ』を彷彿させる。

客として訪れるのは、さまざまな海の生き物たち。ハコフグ、タツノオトシゴ、ウツボ、カレイ、コブダイ、ウミガメ、オウムガイ、メンダコ……と、それこそ水族館のように見ているだけで楽しい。お酒を飲んでボッとトゲを立ててふくらむハリセンボン、自前の灯りで本を読むチョウチンアンコウなど、生態に合わせた描写にもグッとくる。
なかでも常連は、関西弁のアマダイ・ぐじさん、編集者のチンアナゴ、そして主人公的ポジションの人魚のお嬢さんだ。会社帰りに立ち寄る彼女が飲むのは、薄めのハイボール。人見知りでお酒も弱いけれど、小さく流れる音楽と寡黙で飄々としたマスターが醸し出す空気(水中なので水気?)が好きで通うようになった。給料日には、ちょっといいお店で食事をしてからバー・オクトパスへ。いつものハイボールではなく、気分を変えてぐじさんおすすめのマティーニをミニサイズで注文したりする【図9-2】。

マスターは愚痴も最近ハマっているドラマの話も黙って聞いてくれるし、ウザ絡みしてくる客にはストップをかけてくれる。「恋愛というものがイマイチわからない」と言い、いわゆる「おひとりさま」を満喫する彼女にとって、バー・オクトパスはリラックスできる居心地のいい場所なのだ。そんな彼女を中心に、小さな酒場で繰り広げられる小さなドラマが、軽やかな筆致で綴られる。
海の底のバーという設定は、完全にファンタジーの世界。魚介類の擬人化や人魚の存在はいいとしても、そもそもどうやって酒を注ぐのか。ツッコミどころはもちろんある。しかし、そこにやってくる客たちの振る舞いにはリアリティがある。基本的に一人か二人で静かに飲む。顔見知り同士で会話することはあっても、仕事やプライベートについては詮索しない。よそよそしすぎず、なれなれしくもない。そんなバーという空間に求められる適度な温度感が、画面から伝わってくる。
それはやはりマスターの人柄によるところが大きい。常連のチンアナゴに頼まれても雑誌の取材はNG。前述のとおり、ウザ絡みする客はきっちり制止する。が、人気のインスタグラマーに紹介されて若い女子が押し寄せたときには、さすがのマスターもタジタジ。思わず(タコの習性で)背景に擬態して姿を隠そうとしたのには笑った。店の壁に並ぶレコードのジャケットがいろんな名盤のパロディになっているのも見逃せない【図9-3】。

そしてもうひとつの見どころは、エピソードごとに登場するカクテルだ。ブルーハワイ、マンハッタン、スクリュードライバー、マルガリータ、ピンク・レディー、クォーター・デッキ、グラスホッパー、ギムレット、ブルームーン、バラライカ、コスモポリタン……。名前は聞いたことがあってもどんな酒かは知らないものも少なくない。しかし、それらを作る過程が逐一描かれるので、どういう配合なのかがわかり、何となく味の想像もつく。そういうカクテル豆知識的な部分もちょっと得した気分になる。
ところが、実はマスターは多種多様なカクテルのレシピを完璧に覚えているわけではなく、客から見えないカウンターの裏側にカンペを貼っているのだった。クールに見えて、ちょっと抜けたところもある。そこがまた、みんなに愛されるゆえんだろう。
それにしても、よくぞマスター役にタコを選んだものだと思う。いろいろ考えてみたが、海の生き物でタコ以上にバーのマスターにふさわしいものはいない気がする。その分、最も擬人化されているのがマスターであり、その他の魚介類は(人語で会話するものの)ほぼ図鑑的なルックスだ。にもかかわらず妙に人間味を感じさせるのは、作者の超絶画力あればこそ。シンプルかつ自在な線には、ほれぼれする。本当にうまい絵とは(写真のように精細な絵ではなく)万物に生命力を宿らせるような絵のことをいうのである。
終盤のまさかの事件と結末もファンタスティック。海の底の店だから、我々人間が行くことはできない。でも、どこかにこんな店があると思うだけで幸せな気持ちになる。