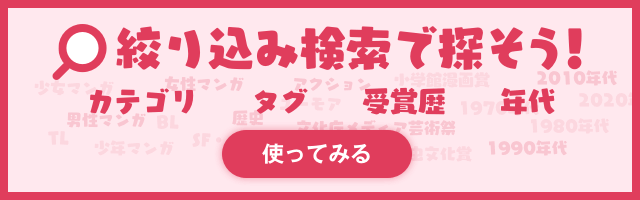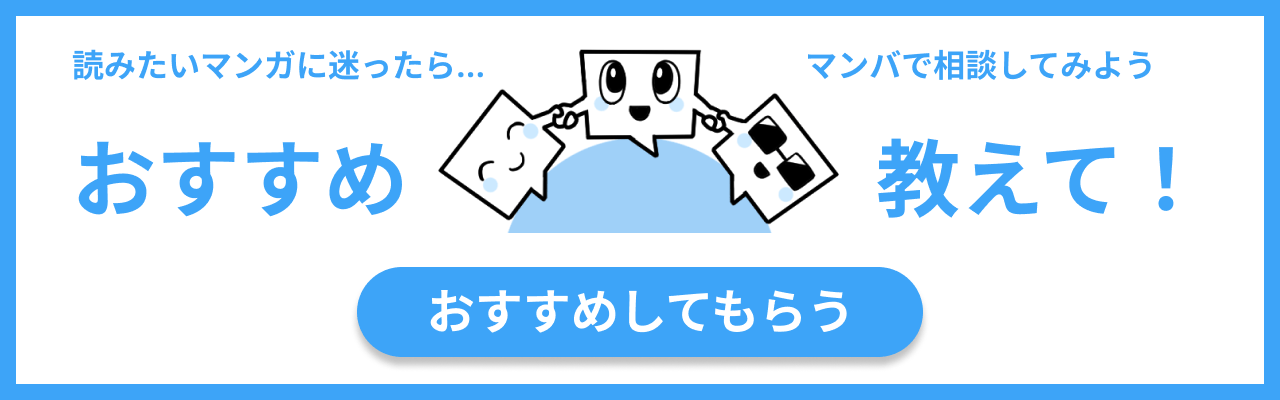この連載ではこれまで4つの作品を紹介してきた。その内訳は、アメリカのコミックスが3作品にフランス語圏のバンド・デシネが1作品。当然のことながら、海外マンガ=コミックス&バンド・デシネではなく、その他の地域にも優れたマンガはいくつも存在している。
ちょうどつい最近、アメリカでもフランスでもなく、韓国で出版されたすばらしいマンガが邦訳されたので、今回はその作品を紹介したい。ソン・アラム『大邱の夜、ソウルの夜』(吉良佳奈江訳、ころから、2022年)である。

***
韓国のマンガについては以前、同じマンバ通信の連載「海外マンガだってマンガなんですけど―邦訳で読む10年代の世界のマンガ」で、ユン・テホ『未生 ミセン』(全9巻、古川綾子、金承福訳、講談社、2016年)を紹介したことがある。この記事を書いてからもう2年半くらい経つのだが、その間、日本語で読めるようになった韓国のマンガの数は相当増えたのではないかと思う。その大半が縦スクロールで読むウェブマンガ“ウェブトゥーン”である。
韓国のウェブトゥーンはLINEやピッコマを開けばいとも簡単に電子で読めるのだが、KADOKAWAを中心にいくつかの出版社から、わざわざ見開きに構成し直した紙版も出版されている。それらはしばしば複数巻に及ぶシリーズもので、サイズは日本のマンガの定型である新書版やB6判、開きは右開きという作りになっていることが多い。中面がカラーであることを除けば、日本のマンガに実によく似ている。作中の韓国語の固有名詞が日本語になっていることも多く、もともと韓国で作られた作品の日本語訳だと気づかないこともある。さすがにウェブトゥーンのすべてというわけではないが、人気作品は次々と紙のマンガになっている印象で、昨2021年に刊行されたタイトルは、既刊作品の続刊も含めれば優に30を超える。

日本で紙のマンガとして出版される際のそれらの仕様は売る側の都合だろうが(そもそも韓国で出版される紙のマンガの多くは左開きだろう)、邦訳された韓国マンガの中には、主流をなすそれらとは異なり、1巻完結で、左開き、新書版やB6判より大きなサイズで出版されているものもある。点数的にはまだまだ決して多くはないが、そうした作品を継続的に出版しているのが、今回紹介する『大邱の夜、ソウルの夜』の版元ころからである。
ころからはまず2016年に、1987年6月に起きた韓国民主化運動を描いたチェ・ギュソク『沸点 ソウル・オン・ザ・ストリート』(加藤直樹訳、2016年※2018年に増補版刊行)を刊行し、その後、2020年に日本軍「慰安婦」イ・オクソンの生涯を通じて韓国の戦前・戦中・戦後を描いたキム・ジェンドリ・グムスク『草 日本軍「慰安婦」のリビング・ヒストリー』(都築寿美枝、李昤京訳、2020年)を刊行した。なお、筆者は後者の解説を執筆している。興味がある方はぜひ作品ともどもお読みいただきたい。

民主化運動に日本軍「慰安婦」と、なかなかヘビーなテーマが続く印象だが、これらの本を刊行してきたころからが3冊目として世に問うた韓国のマンガが、『大邱の夜、ソウルの夜』というわけだ。
ちなみに本書『大邱の夜、ソウルの夜』は、ころからと「場末(BSEアーカイブ)」がコラボして立ち上げた新レーベル「KGB(Korocolor Graphicnovels with Basue)」の第1弾だという。場末(BSEアーカイブ)とは、放送作家・コラムニストの町山広美さんが主宰する東京の下北沢にあるグラフィックノベルを中心に扱う新刊・古書店だそうで、ころからと場末(BSEアーカイブ)がタッグを組んだこのKGBレーベルからは、今後、シンガポールのマンガ家ソニー・リュウの『チャーリー・チャン・ホックチャイの芸術』(以前、筆者はこの作品のレビューを書いている。よかったらぜひお読みいただきたい)の邦訳出版も予定されているのだとか。今後が非常に楽しみである。
***
本書『大邱の夜、ソウルの夜』は、もともと2017年に、直訳すると『二人の女の話』というタイトルで、韓国で出版されたらしい。日本語版のタイトル通り、「大邱の夜」と「ソウルの夜」という2編の短編が収録されている。紙の雑誌等に掲載されたのか、同人誌として出版されたのか、あるいはウェブトゥーンとして配信されたのか、詳しいことはわからないが、「大邱の夜」が2013年に発表され、その後、丸3年かかって「ソウルの夜」が完成。2017年に両編を収めた本書が出版された。
「大邱の夜」の主人公は、ソウルでフリーのイラストレーターをしているパク・ホンヨンと、韓国の地方都市・大邱出身で、やはりソウルで編集者をしてるソ・コンジュというふたりの女性。年齢は記されていないが、ふたりとも20代後半か30代前半くらいだろうか。
ある日、ふたりは互いに話があると言って待ち合わせをし、その場で、パク・ホンヨンはできちゃった婚をする羽目になったことを、ソ・コンジュは仕事を辞めて故郷の大邱に戻る決断をしたことを、それぞれ告げる。幸い、ソ・コンジュの故郷・大邱は、パク・ホンヨンの夫の実家の近くである。ふたりは今まで以上に会えるかもなどと冗談を言い合って別れる。

それから2年の月日が経過した。その後ふたりは、あの日ソウルで話し合ったようには会えていないらしい。お盆で夫の実家に里帰りした際に、パク・ホンヨンは久しぶりにソ・コンジュと会う約束をする。大邱まで足を延ばしたパク・ホンヨンは、ソ・コンジュに会うなり、夫との結婚生活や夫の実家での扱いに対する不満をぶちまける。そんなパク・ホンヨンにソ・コンジュは、彼女の実の母親が癌で余命いくばくもないことを告げるのだった……。

「大邱の夜」はどちらかと言えばパク・ホンヨンを中心に据えているのに対し、「ソウルの夜」はソ・コンジュに焦点を当てた作品である。物語はふたりの出会い以前に遡り、生まれ故郷の大邱で大学生をしていたソ・コンジュが大学を休学し、いつかソウルに行って「エディター」になるという夢を実現するために、アルバイトに明け暮れる場面から始まる。彼女は実家暮らしだが、父母以外に認知症が進行した父方の祖母が同居していて、祖母の面倒を見るのはもっぱら彼女の役目になっている。かつて祖母から母に対して嫁いびりのようなことがあったのか、ふたりは折り合いが悪く、そのせいもあってか、今では祖母の面倒を見ているソ・コンジュと母の関係も険悪になっている。

ソ・コンジュの愉しみと言えば、アルバイトが終わったあと、祖母が寝たのを確認し、深夜にひとり酒を飲みながら、ブログを更新し、ブログ読者の書き込みに返信することだった。そんな読者のひとりが、ソウルでイラストレーターをしているパク・ホンヨンだった。やがてふたりは交流を深め、その関係を足がかりに、ソ・コンジュは念願のソウル行きを実現することになるのだが……。

ご覧の通り、2編目の「大邱の夜」が1編目の「ソウルの夜」の前日譚のような構成になっていて、それぞれ独立して読むこともできるが、両方合わせて読むことで、主人公たちの人となりや彼女たちを取り巻く社会が、より立体的になっていく。
背景や小道具の綿密な描写が、本書に描かれた社会にリアリティを
とりわけ印象的なのがお盆のシーンである。母親がいる実家に戻り、くつろいだ様子を見せる男たちを尻目に女たちはひたすら料理を作り、洗い物をし、子どもたちの面倒を見なければならない。男たちが祭祀に参加する様子を脇で立って見守り、祭祀が終わって食事の時間になると、夫たちとは別の部屋に引き下がり、女たちと子どもたちだけの食事が始まる。

本書には主人公のふたりパク・ホンヨンとソ・コンジュだけでなく、世代も立場も違う複数の女たちが登場する。パク・ホンヨンの義母と義姉、そして、ソ・コンジュの母と父方の祖母。物語の中心はあくまでパク・ホンヨンとソ・コンジュだが、彼女たちの物語から浮き彫りになるのは、韓国に生きる女性たちの大半が見舞われているであろう生きづらさである。ソ・コンジュの祖母や母、パク・ホンヨンの義母や義姉がそうしてきたように、ソ・コンジュもパク・ホンヨンも男たちや家族のために自分を殺す生き方を繰り返さざるをえない。
女たちは自分たちの苦しみ、悲しみを癒すためであるかのように語り合う。本書には女たちが語り合う場面が実に多く描かれている。「大邱の夜」では、同世代の友人同士であるパク・ホンヨンとソ・コンジュが、カフェやおでん屋、居酒屋、あるいは公園のベンチ……、折につけさまざまな場所で、愚痴を言い合い、軽口をたたき合い、慰め合う。「ソウルの夜」では一転して、ソ・コンジュが実の母親と父方の祖母と向き合う様子が描かれる。その語り合いの様子は、当然、友人同士のそれとは異なるだろう。とりわけ家のために自分を殺し、不満ばかり言っている実の母親に対して、ソ・コンジュはもどかしさや憤りを感じざるをえない。しかし、そのソ・コンジュもまた、やがて母のように、そして一足先に結婚して子どもを産んだ親友のパク・ホンヨンと同じように、家族を持つことになる。

物語を通読して思うのは、はたしてソ・コンジュの母には、ソ・コンジュにとってのパク・ホンヨンのような人がいただろうかということである。「お互いの暮らしを根堀葉堀り話しながら、笑って怒ってまたすぐ忘れて、それぞれの生活に戻ることを繰り返」(P66)す親友のような存在が。おそらくかつてはいたのかもしれないし、残念ながらいなかったのかもしれない。
夢を実現するために大邱からソウルに上京し、がむしゃらに頑張っ
前回取り上げたマリコ・タマキ作、ジリアン・タマキ画『THIS ONE SUMMER』は、子どもから大人になろうとしている少女の目を通して女性の生きづらさを描いた作品と言っていいかと思うが、本書『大邱の夜、ソウルの夜』はそれとはまた違ったやり方で、女性の生きづらさというテーマにアプローチしている。作家の個性はもちろん、作品が制作された社会が大きく影を差しているということもあるのだろう。韓国には、そしてアジアには、他にもこういった作品があるのだろうか? 本書を皮切りに、韓国を始め、アジアの女性作家のマンガの邦訳が、さらに増えていくことを期待したい。
筆者が友人たちと行っている週一更新のポッドキャスト「サンデーマンガ倶楽部」でも、2022年3月13日更新回で本書『大邱の夜、ソウルの夜』を取り上げている。よかったらぜひお聴きいただきたい。