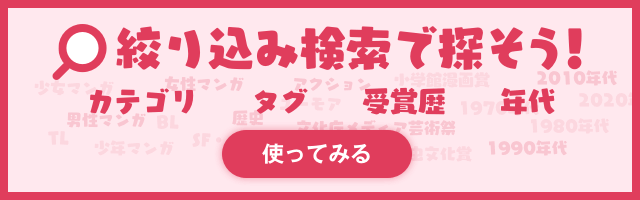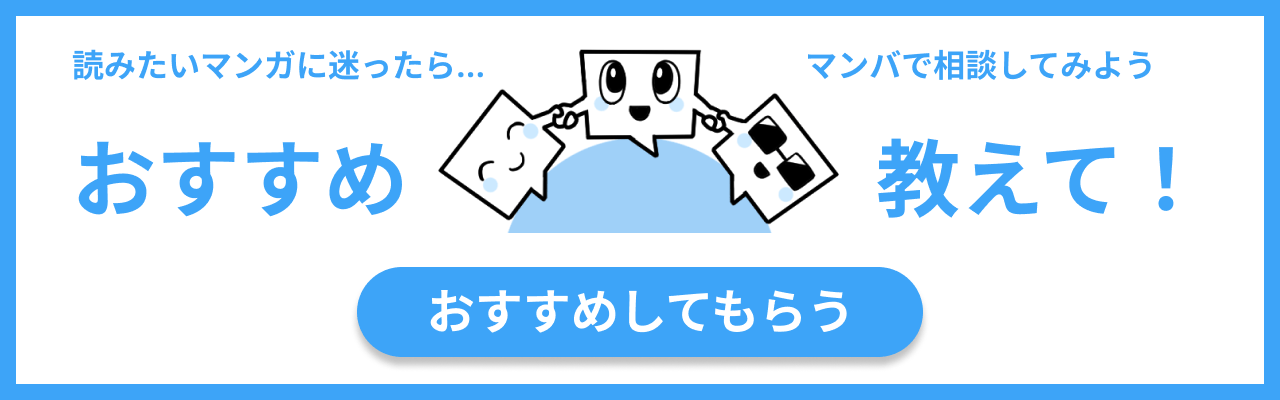ペス山ポピー先生の『女(じぶん)の体をゆるすまで』(小学館)は、タイトル通りセクシャルハラスメントにあった作者が、自責の念から持ち直す中で自分の体を見つめなおす物語です。忘れたくても忘れられないセクハラという泥沼を見つめなおす作者の奮闘からは、セクハラ被害からのリカバリーや性自認を問うことの難しさが伝わってきます。
心理療法には、絵を描くなどアート活動を通じて自分のありのままの考え方を表現し、自分の抱えている問題と向き合うアートセラピーという手法があります。日記などを書くことにも自分を客観視する効果があるといわれています。こうした行動にならうかのようにペス山さんが直面したセクハラを漫画に落とし込んだのが今回の作品の出発点です。実際に起こったのは2013年ですが、漫画家とアシスタントという立場を考えると、私は権力関係を利用するパワーハラスメントも入っていたのではないかと思いました。
その描写はすごく克明。実際に行われたことはもちろん、ペス山さんの漫画による表現がセクハラ・パワハラのつらさをしっかりと伝えてきます。心臓がつぶれる感じなどペス山さんが衝撃を受け傷ついた表現が巧みで、筆者は被害者ではないのにセクハラの被害者が加害者にその事実と伝える苦しさやフラッシュバックなどダイレクトに苦しさを受け取りました。
ペス山さんはセクハラを「相手を自分の想定したロールプレイに勝手に巻き込むこと」と定義します。その巻き込まれた時の嵐に襲われたような感情の表現が私たちにぶつけられます。正直、今もセクハラやパワハラの被害で苦しんでいる方は、冒頭部分は読むのに覚悟が必要です。
ペス山さんはそうした嵐から、いろいろな人の手を借りて少しずつ折り合いをつけていきます。経験談を読んで「これを描いてどうなりたい・・・?」と聞いてきた編集者。弁護士の先生、カウンセラーらがセクハラされた事実と向き合う手助けをしてくれます。
そしてこの作品を純粋なセクハラ体験記とそこからのリカバリーの物語にとどまらせないのは、リカバリーの過程でペス山さんが自分の生物学的な女性としての体を受け入れていく物語も重なっているからです。
ペス山さんは自己紹介部分で「自分の性別、絶賛迷子中」と表現。生物学的には女性として生まれ、感覚的には男性と女性だとやや男性よりで、ジェンダークリニックに通院されているとのことです。セクハラを受けたペス山さんの中でも「なんで女に生まれてきたんだ」「女に生まれたのが悪い」という声が響きます(実際は、セクハラやパワハラを受けるのは女に生まれてきたからではありません。セクハラやパワハラは、男性と女性の間だけでなく男性同士女性同士でも起こりえます。もちろん、女性が加害者になることもあります)。
2021年現在、日本ではLGBTQ+に対する理解が急速に進もうとしています。そうした中でペス山さんのように体の性と性自認が一致しないというのはどういうことかを漫画で表現してもらえるのはありがたい限りです。特にペス山さんは、子供のころから男性がいいけれども女性の体を持っていることで揺れているようにみえました。「ここまで一致していないとどう生きていけばいいのわからない」という率直な思いは当事者だから出てくる言葉でしょう。もちろん描かれているのはペス山さん個人の話でほかの人に当てはまるかはわかりませんが、理解の一助になりえます。
本人にとって進行中のものを商業出版で出す是非はあるものの、ペス山さんも指摘するように#MeToo`運動の広がりなどがセクハラなどの告発を受け入れる土壌を形成したことで出版が可能になった側面もあります。正直、よくぞ書いてくれたという気持ちです。セクハラも性自認のどちらのテーマもまだ現実社会ではなかなか率直に質問するのが難しいもの。これらに触れられる貴重な機会というところにも、エッセイ漫画の醍醐味を味わえます。