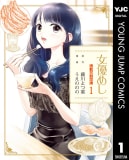
女優めし連載・感想雑談

「ハヴィラ」という小さい者たちの戦いの物語
※ネタバレを含むクチコミです。

ユーレイになってもアゲてこ↑
事故で亡くなったギャルが幽霊になってクラスメイトの僧侶に取り憑いちゃった!四十九日までにやりたいことを全部やって成仏できるかな?なコメディです。死んじゃってもギャルマインド全開なので悲壮感がゼロなのがいいですね。

この関係はかなり尊い!
※ネタバレを含むクチコミです。

バツイチになってモテ始めた主人公
※ネタバレを含むクチコミです。

天才少年が出会ったのは野球
※ネタバレを含むクチコミです。

『ドッグスレッド』最新話の感想
※ネタバレを含むクチコミです。

有能だが変人?義手の学者による医療ミステリー
※ネタバレを含むクチコミです。

憧れの清楚お姉さんが黒ギャル教師になっていた話
※ネタバレを含むクチコミです。

ネガッチョ #読切応援
最強ジャンプって子供向けだと思ってたけど、これはオトナが読んでもメッチャ面白かった。

薄い
自分は溺愛なら結構何でも受け入れちゃうとこあるけど、そんな私にもこれは薄かったなー。 なんか表面だけサラッと流して終わった感じ。

【楽しく】徳川埋蔵金で大抗争!?
※ネタバレを含むクチコミです。

驚くほどつまらない
作画の無駄遣い

アラフィフ女性の再出発
※ネタバレを含むクチコミです。

週末BBQ婚マンガ
※ネタバレを含むクチコミです。

夫とレスで女性風俗に行ってみたら死にたくなった話
※ネタバレを含むクチコミです。

競合だらけのアパレル界で生き残れ!!
主人公は自社ブランド・ミシロのMD(マーチャンダイザー)。ミシロの商品を売るためにあらゆる売上データを検証し、それをもとにデザインを検討し、販売したらまた検証を繰り返す。服が売れない今、アパレル界で生き残ることは大変なんだなというのが伝わってきます。いちばんの競合ブランド「アンノワ」に対抗するため、今まで扱わなかったメンズにも挑戦することにしたミシロはアンノワに対抗できるのか。
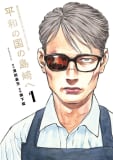
元戦闘工作員・島崎は祖国日本で平和な暮らしを手に入れることができるのか
※ネタバレを含むクチコミです。

野球界のレジェンドがオレ流異世界転生!
※ネタバレを含むクチコミです。

新感覚キャンプ漫画
独りでキャンプをし、自然の醍醐味を味わうことに喜びを覚えるおっさんの元に現れたのは、おっちょこちょいな女性。ただのキャンプ漫画ではない、「ふたりソロキャンプ」の始まり! ビア缶チキンは旨そうで食べたくなった。キャンプ場でのご飯はやはり格別だから美味しそうに描けているのは強い。キャンプに使える雑学も程よく入っているのもポイント。個人的には恋愛方面にいかなければいいが、どうだろう。今後も追っていきたい

ヤ◯ザと盲目の花屋さん
うーん、自分にはあまり刺さらなかったかも。 惹かれあった理由がよく分からない。 なんとなくこんな感じ?みたいに曖昧に描かれていた気がする。 そして流血もあり。ヤクザ出ててもハートフル、みたいな作品ではない。

作者です!良し悪し互いにクチコミよろしくお願いします!
ダークな作品なので嫌われやすいジャンルですが めちゃくちゃ素直な感想沢山待ってます! 全部受け入れるので!よろしくお願いします!

悪から目を背け続けた男が、娘のため悪に立ち向かう…!
※ネタバレを含むクチコミです。

チェンソーマン第2部を語るスレ
※ネタバレを含むクチコミです。





※ネタバレを含むクチコミです。