
禁断のソリッドシチュエーションSF
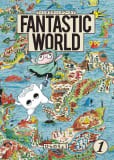
超絶的な冒険マンガがここにあった。
未知の世界。 見たことのない景色や生物。 知的好奇心から来る「冒険」というものへの憧憬は、人間の奥底に根ざしています。そして、物語はその冒険の興奮を疑似体験させてくれます。『指輪物語』や『地底旅行』、『エルマーの冒険』などを読んで、夜眠れなくなるほど心踊らせた子供の頃のあの想い。 『ファンタスティックワールド』は、そんな感覚を再び呼び起こしてくれました。 トーチWebで読んでいた時から様々な面で普通のマンガとは一線を画した作品でしたが、紙の本になってそれは更に加速しました。何と豪華な装丁! 実際に手に取った時にその素晴らしさに感激しました。 表紙をめくった部分にある、異文化の文字による手稿。全く読めはしないのですが、図解で何となく概要は掴めます。もうここだけで最高にときめき、わくわくします。 小口や天地が表紙と繋がる一枚絵になっているなど、なかなかこのような贅沢な装丁のマンガはありません。 WEB掲載時にはなかった冒頭部のイントロダクションとタイトル見開きも、それだけでこの作品のスケールの大きさを雄弁に語ってくれます。圧倒的に広大で、明らかに既知の地球上にはない光景。この見開きを見せられて胸が高鳴らないわけがありません。 大判サイズで、これだけ美麗なフルカラーのビジュアルで見せられると圧巻です。極彩色の世界に陶酔します。これは紙で持っておきたくなる一冊。 内容については「地球の内部に存在する地表とは別の文明圏で、少年が歯を相棒に旅をしていく」という、あらすじだけ字面だけで見ると若干意味不明なものです。キャラクターの造形が独特過ぎると共にシュールな部分も多々あるが故に、最初は取っ付き難さを覚える方もいるかもしれません。しかし、そんなものはこの本の中の広大な世界と遙かなる奇想の数々に比べれば瑣末なことです。 ファンタジーだとかSFだとか、そんなジャンル分けをすることもこの作品に関しては無粋に思えて来ます。ただただ、ひらのりょう先生によって紡がれていく独特の世界を、読むというよりは体全体で浴び続け深く味わうような感覚に陥ります。そして、それが非常に心地良いのです。脳の普段使わない部分を活性化させられます。 これは、ただ単純に絵が魅力的であるというだけではなく、マンガとしてのコマ運びや静と動の緩急が上手く行われている所に起因しています。この作品がマンガとして表現されている意義を、読んでいて十全に感じます。 一見すると荒唐無稽な世界観に思える箇所もいくつかありますが、一方で現代社会や人類史上の現象や問題、哲学的なテーマを掬って解体し提示する面も見られます。 未知の世界のもたらすわくわく感を純粋に楽しむのも良いですし、創作的な刺激や思考の材料にもなる優れた物語です。 主人公の少年、ビコの以下の言葉に共感するなら、ぜひともこの唯一無二のファンタスティックな世界を体験してみて下さい。 > 「色んなヒトや知らない景色と出会える… > もっと見たくない? > この世界の先を…」 果たして、ビコと歯ちゃんの旅はどこまで達するのか……。続きと結末が非常に気になります。

漫画史に煌々と輝く魔球、その名もハクション大魔球!!
マンガとはひとつに夢をみさせてくれるものでしょう。そして魔球とは正しくすべての野球ファンにとっての夢……。そんな夢をみさせてくれるマンガとは、あるいは魔球とともに歩んできた歴史なのかもしれません。 そもそも事の始まりはこうなのです。プロ野球界に女性だけで構成された新球団ができる、その名も「スイート・メイプルス」。もうこの時点で夢のような話なのです。こういって差し支えなければ、メイプルスの面々は、男だらけの球団を相手にまったく出鱈目と積極的に言っていきたいほどの懸命さと天真爛漫さで勝ち上がっていきます。この途方もない出鱈目さ加減がほんとうに感動的で胸を打つ。男たちを相手に女性だけのチームがどうやって勝っていくのか、なんていう、説明責任はこのマンガには端から存在していないのです。 マンガに関わらず、いま、あらゆるものに説明責任なるものが蔓延しているように思われます。しかし、それはなんと窮屈で不自由なことだろうとも思うのです。説明責任とは、アレはしていけない、コレはしてはいけない、というふうな否定的で不自由に方向にしか物語を運んでいかないことでしょう。そんな説明責任なるものから始めから自由になっている『メイプル戦記』は、それ故に感動的としか言いようがないのです。私たちはまだ見たことのない魔球を見てみたくてマンガに熱中するのではなかったか、私たちはまだ見たことのない夢を目の当たりにしたくてマンガに熱中するのではなかったか。私は『メイプル戦記』ほど自由で豊かで感動的なマンガを他にあまり知りません。

面白い野球漫画
どのシリーズよりも面白い野球漫画です。 青春感じたい人はぜひ!!

面白い野球漫画
熱い野球漫画 リアルな趣向で青春が読み取れてすごく良いです。 ほかの野球漫画の中で1番面白いシリーズです!

ちょっと悲しい気もするけど幸せで素敵な体験ができる本
パラ、とめくった時に宮崎夏次系の絵っぽくてアーティスティックな作風かな、と思った。 主人公は友人を交通事故で亡くしてしまうんだけど、星に願ったらその友人に会えるようになってしまう。 切り株の穴を潜るとか、蛍の光を追いかけるとか、どこか童話的だなと思うけど主人公の健の心情とか友人とか人間が描かれててストーリーはすごく大人…な気がする。 何というか、大人が夏休みのある一日を振り返ったような、そんな感じもしてくる。どこか懐かしいような。 悲しい始まりなのに、死んでしまった人は別のどこかで生きてるとか、こうあって欲しいな〜ってことが漫画では実現できる。 だから幸福感を感じるのか。子供の話だから懐かしさを感じるのか。 タッチも作品に合っていて総じて素敵だな〜って思う。 うまく説明できない。ちょっと読んでみて欲しい。

サイン会&トークイベ
超地方だけどサイン会とトークイベントやるってよ! 3/2 サイン会、3/3 トークイベ http://www.coamix.co.jp/3952 こんな地方で? って感じだけど地方だからこそゆっくり聞けて質問とかできるかも

気がついたら好きになっているが最強
ギャルゲーの知識と経験を活かして女の子を「攻略」していくというコンセプトがまず面白い。人によって好き、嫌いが分かれる設定だが主人公の桂馬君がオタクゲーマーとは思えない行動力を備えており見ていて清々しい。実は顔、知力、コミュ力と揃った稀有な主人公。ロジックで行動しているだけのように見えて、きちんと一人一人の女の子のことを桂馬君なりに考え、きちんと感情、気持ちを向けている点が好ましい。また、ただの色物設定の漫画ではなくて、人を好きになるってのはどういうことなの?ということや、オタクはどうやって現実と向かい合うの、と言ったテーマが込められているように感じる。ひきこもりの経験が作品内で活きていることは作者にとっても救いであろう。

主人公よりも地球監視者に肩入れした
良かった点 ・横山光輝の書く六神体のかっこよさを堪能できる ・表紙もラストも衝撃的な内容 ・一番好きな神体はウラヌス 総評 ・このマンガに登場する地球監視者たちは自分の仕事に責任感を持ったプロ中のプロだ。
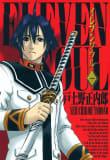
無冠の傑作
タイトルだけ見ると、11人で闘うサッカー漫画? と思うかもしれません。ただ、残念ながらそうではなく21世紀中盤を舞台にしたSFバトルアクション青春群像劇です。 しかしながら、ある意味でサッカーとも共通点がない訳ではないのです。それは、まさしくサムライの心、志を描いているという一点。 サッカーの日本代表は、サムライブルーと呼ばれる「現代の侍」。そして『イレブンソウル』で描かれるのは、「近未来の侍」。やることは違えど、その根底に流れるソウルは同じ。イレブンは漢字にすれば十と一で「士」となる点からも、サッカー選手をサムライと呼ぶのには理が感じられます。 この作品では、常に死と隣り合わせという状況の中で、「心とは何か」、「愛とは何か」といった哲学的な問い掛けが度々なされ、その度に名言が頻出します。 その流れの中で、「幸せとは何か」という問いに対する、ある人物の答。 > 士(もののふ)とは… > 「十」の経験を「一」に帰結させる人種だと…… > (中略) > 一つのことを成し遂げるその瞬間… > そこに心の全てを傾けて生きる… > それが「志」ある生き方なんだと…… > そんな生き方ができるなら…… > 俺は「幸せ」だな…… この台詞を放った乃木玄之丞という男、あまりに格好良過ぎてシビれ憧れ尽くします。彼の「生きるとは何か」という問への答には思わず唸らされましたので、是非読んで確かめて頂きたいです。 ワールドカップ前にサムライとしての心構えを再認識させてくれるこの作品を読むことで、熱く闘う男たちの姿により一層感銘を受けることができるようになるかもしれません。 ■イレブンソウルの世界の魅力 2051年、遺伝子技術の発達によって不老不死に肉薄した人類。しかし、バイオハザードが発生。実験サンプルは自然界から遺伝子を取り込み急激に進化。「シャヘル」と呼ばれるようになったそれは、2年で南北米大陸を制圧。歴史上に初めて現れた自らを超える種に対抗すべく、人類は外骨格兵装を纏えるよう身体強化と訓練を施された「侍」と呼ばれる少年少女の部隊を結成。未曾有の進化を遂げる正体不明の敵を相手に対峙して行きます。 今作の主人公・塚原武道、通称たけちーは、およそ軍人には向かない穏やかな性格で、入隊前の適正検査でもEランク。特Aランクの秀才ヒロインに罵倒されながら、それでもある「志」を持って必死に地獄の訓練に喰らいついて行きます。 今作の魅力は幾つもありますが、まず上で挙げた乃木も含めキャラクターが実に魅力的。普段は軽口を叩き合う彼らですが、それぞれが抱える様々な凄絶な過去や切なる想い、そして迎える運命に胸が熱くなります。常にいつ誰が命を落とすか解らない極限状況の中で、重厚ながら人の温かみを感じるドラマに思わず涙してしまう箇所も。 「あいつらにもつまらない大人になる権利はあった」と語る渋い上官の言葉に、何とも言えない想いを噛み締めます。そう、このマンガでは美男美女だけでなくおっさん達も実にイイ味を出しています。おっさんが格好イイ作品は良い作品です。 強化外骨格による、シャヘルとの戦闘シーンの迫力も圧巻。中でも、前半の山場でもある7巻において、ある理由から自ら窮地に飛び込んだたけちーが地平線を埋め尽くすおびただしい数のシャヘルに対して単騎駆けを敢行する場面の盛り上がりは特筆すべき物。シチュエーション的にも、そこで飛び出す数ページにわたる名言も、あまりに熱すぎます。これに燃えずに何に燃えろというのか! 必見です。できれば序盤では切らずに、ここまでは読んでみて欲しいと思います。 又、最終15巻収録の一切セリフなしのサイレントで描かれる、サブタイトル「真空(オトタチ)」は、SFアクションマンガ史に強烈な一撃を斬り刻みつけたと言っても過言ではありません。『スラムダンク』の山王戦を髣髴とさせる、この圧倒的なクライマックスが語り継がれないなんて、そんなオカルト有り得ません! ■進撃、シドニア、オルタ、ガンパレが好きな人はイレブンソウルも読むべし! ある時「『ガンパレード・マーチ』や『マヴラブオルタネイティヴ』のような漫画がある」と聞いたのが、その両作品が死ぬほど好きな私と『イレブンソウル』の出会いの始まりでした。「マヴラブオルタネイティヴ」は、あの『進撃の巨人』の諫山創先生自身が「物凄く影響を受けた」と公言している作品。そして、「ガンパレード・マーチ」はその「マヴラブオルタネイティヴ」が大きく影響を与えているのではないかと言われている作品です。あるいは更にそれらの大本である往年の名作SF『宇宙の戦士』的な物語です。 又、現在アニメも放映中の『シドニアの騎士』の原作である弐瓶勉先生も、諫山創先生が敬愛し影響を受けている一人であり、『シドニア』もまた類型的な世界観を持つ作品です。それらの作品が好きな方には、特に強くお薦めしたいです。 『マヴラブオルタネイティヴトータル・イクリプス』や『シドニアの騎士』のBD/DVDが5000枚以上売れる今の時代、『イレブンソウル』も然るべきクオリティでアニメ化すれば、必ず世に受け入れられると確信しています。強化外骨格での迫力ある戦闘シーンを動画で見られる日が来ることを願って止みません! ■SF好き・ロボットアクション好きにも、そうでない人にも 絵に関しては、序盤クセがあると感じられるかもしれません。ただ、物語と共に後半になるにつれて顕著にスタイリッシュに進化して行きますので、ある意味そこも見所と捉えられます。逆に、読み終えるとこの作画を全て一人で行っているという事実に驚かされます。 かなり濃厚なSF設定や兵器描写はニッチさを醸し出しているかもしれませんが、この作品が持つ心を揺さぶる人間ドラマは多くの人に届くはずです。何より、純粋に続きを渇望するほど面白いのです! これから『イレブンソウル』を読む人が羨ましい限りです。一気に全巻揃えて、続きが気になって狂おしい夜を過ごすことがないのですから。そして、たとえ夜中であっても、Kindleで全部買えてしまうのですから! どうぞ、心行くまで熱き士魂の活劇に酔い痴れて下さい。

復讐のために最強になったキャバ嬢 #読切応援
ボクシング世界王者とめくるめく夜を過ごすのかと思いきや、殺るか殺られるかの勝負を挑むキャバ嬢。いやぁ〜笑いました。もう今となってはタイトルの雌ライオンの牙で笑えます。独特の狂気的なノリのある作家さんですね!

F先生の凄さが分かる!
いつもの子供向けF作品にはあまりない、ねっとりとしたブラックな物語というギャップだけではなく、社会風刺を取り入れた物語の巧さや、完璧なオチに驚愕しっぱなしだった。 「ノスタル爺」は実写化したらこの短編だけでも一本の映画が作れそうなくらいのすごい物語だと思いました。 星新一なんかが好きな人はぶっ刺さりますよ!

最近の魔王城は人道的という説
短くまとまってて、面白かった。姫がむちゃくちゃで、魔王たちを振り回してる感じは、魔王城でおやすみを思い出す。まぁ独房もない、拘束もしない、食事がちゃんと出る魔王城は結構居心地がいいかもしれない。たしかに家出する時にはちょうど良さそう。 ツッコミどころとしては姫がカルパスとか、焼き肉のたれとか庶民的かつ非ファンタジーのもんをなんで持ってるんだよ。しかもさらわれる時に!とは思った。

おもしろかったけど、王子のキャラが弱い
姫が魔王城を親戚の家感覚でくつろいで馴染んでるところは、銀魂みたいなコメディの空気がよかった。ただ王子に特にキャラ付けとかなくて姫がさらわれるシチュエーションありきで仕方なく存在してる感が微妙かな…

ウチとは違う、『人んちの介護』を知る一歩
下巻まで読み終えたとき、上巻の序盤を読み直してみて、作者の母・トシ子さんがどれほど痩せたかに驚きました。 「骨折を機に徐々に細っていき、ヒゲが伸びる」という描写に、自分の祖母もそうだったな…と深く共感しました。 また読み進めるごとに、「これ以上痩せられないだろ」という想像を超えてやせ細っていくトシ子さんの姿を、可愛らしいデフォルメを残したまま各段階を描写しきったところが素晴らしいと思います。 作中で印象的だったのが、車椅子に乗った女学生の姿で若い施設のスタッフさんを探すトシ子さんと、怒りっぽくなったトシ子さんのことを「好きだ」という夫・あきおさんの言葉。 …思わず目にこみ上げてきました。 作中でも述べられていますが、母の介護だけでも大変なのに、「遠距、怒りやすく偏屈な父、ケアマネさんは新人」というのが作者の家の『介護』なのです。 マンガを通して人の家の事情を知ったことで、すこしは介護というものをより多面的に把握できるようになった気がします。 Kindle Unlimitedで上下巻読めるので是非。

「老いるとはどういうことか」を示してくれたマンガ
大学生だった2012年頃によんでますよ、アザゼルさん。を追うためにイブニングを読んでいて出会ったのがヘルプマン!22巻に収録されている「介護企業編」でした。 主人公・飛石が介護ビジネスで一儲けしよう企む過程で誰もやっていない、利用者を喜ばすケアプランを思いつくものの、プラン内容は全て国の定める介護保険法に違反することを知る。 当時、今は亡くなった祖母が施設に入っていたこともあり、飛石と同じ目線で驚きながら介護について学ぶことができました。 次の「認知症予防編」は、元宇宙飛行士の女性が父を介護することになり、認知症の衝撃的な現実を(壁に…)目の当たりにするというエピソードもすごく好きでした。 ヘルプマン!は後半のこの2編しか読んでいないので、ずれ全部読み通したいです。

もしかしたらとんでもない作品になっていくかもしれない
※ネタバレを含むクチコミです。

喫茶店の女子高生店主と小学生大家のまっすぐな交流を描く
まず女の子がカワイイ。信じていい、大丈夫だこのマンガは。 むしろ「20代も後半になって美少女が喫茶店でキャッキャウフフするような作品を読もうという俺が大丈夫か?」という気持ちだったのですが、本作はその20代後半の「働く人間」にザックリと刺さります。 とはいえ序盤は入り込むまで正直時間がかかったし、兼業作家として活動する作者の念みたいなものがカワイイ女の子レイヤーを貫通して透けて見える瞬間もあります。 が、だからこそ届いてしまう。 喫茶店月の岬に集まった人たち(※みんなカワイイ)が 素直に自分の好きなものを、好きなひとたちとやっていこうとするまっすぐな気持ちが。 ただカワイイだけの作品ではない。 作者のまっすぐな思いがたっぷりと詰まった、信頼できるマンガです。

何度読んでも面白さが消費されないマンガ
1つの作品の中に『異なるジャンルのマンガ表現』が混在していてすごい…! ネコがおもちみたいに溶けて子どもがコロコロしている絵柄は、大人っぽい**「ゆるいデフォルメ」**。町並みや道路は丁寧に描かれ味があり、まるで歴史漫画のような**「リアルな背景」**。そして日常を描いた作品でありながら、襖を開けるシーンではナメたりや卓球中は俯瞰したりと、カメラワークはまるで**「少年マンガのような迫力」**。 **そしてただ違うジャンルの技法を取り入れるだけでなく、それが見事に調和がとれていて読んでいて気持ちいい…!** そしてストーリーは、舞台背景について説明がほとんどないにも関わらず、スッと世界に入れてキャラクターを身近に感じました。 というか、登場人物たちの関係や、キューポラ堂はなんで卓球を置いているのか、八絵ちゃんは過去に何があったのかを野暮ったく語らないところが粋…! **説明しすぎず、読者自身に想像で自由に余白を埋めている状態こそが、まさにこの作品の面白さの根源**かなと思います。 読み手の数だけ「キューポラ堂とは何か・なぜ卓球があるのか」の答えらしきものが無数に存在する以上、この作品は何度読み返しても面白さが消費されない。

この短篇集に収録された「青いサイダー」はあまりにも天才的!
読み始めてすぐに衝撃を受け、読み終えると五秒ほど深く嘆息しながら、その卓越したセンスに拍手を送るばかりでした。漫画読みでいて良かった、と心の底から思えた作品です。そして、何度か読み返す内に涙すら零れて来ました。 町田洋先生のこれまでの作品は、イメージでいえば圧倒的に「夏」。自分の中にある過去の夏の情景が想い起こされます。しかし、それは常夏の南国のような陽気な夏ではありません。どちらかと言えば、夏休みのプール教室に行ったものの知り合いが誰もおらず蝉時雨の中で歩んだ孤独な帰り道や、最後の一本の線香花火の火が消えて後片付けをしている時のような、鮮烈な季節の中にある陰。夏の終わりに存在する、独特の寂しさのようなものを感じさせます。そして、それは切なくもどこか仄かに温かです。 ■ 町田洋、その誉れ高き新鋭 町田洋先生は、そもそもが珍しい経歴の作家です。元々は自サイトで漫画を掲載していた所、電脳マヴォに掲載。そして、デビュー作となる前短篇集、『惑星9の休日』が、描き下ろし単行本として祥伝社から昨年刊行されました。今の時代、連載も無く単行本が出される、しかも新人が、というのは非常に稀なケースです。ネットの海の中で人知れず花を開いていた才能が発掘され、そうして特殊なルートでデビューを果たすことができたということは、マンガ業界における一つの希望でもあります。 それに続き、電脳マヴォに掲載された三作品を中心に、描き下ろしとして8ページの短編「発泡酒」を加えて書籍化されたのが、二冊目となる『夜のコンクリート』。その内の一作「夏休みの町」は、文化庁メディア芸術祭で新人賞を受賞しています。 ちなみに、『夜とコンクリート』刊行にあたって、最初は電脳マヴォに「青いサイダー」だけを残すことが町田先生に提案されたそうです。しかし、その提案とは逆に町田先生は「青いサイダー」のみを掲載作から外すことを要望したのだとか。私はそのエピソードを知って、とても納得が行きました。それは、言い換えれば他の2篇をWEBで読んで既読の状態であっても、本を買った時に「青いサイダー」さえ読んで貰えれば満足して貰えるだろうという自信の表れではないでしょうか。 ■ かつて見たこともない描線が織りなす、独特の世界 町田洋先生の描く絵は、シンプルですがそれ故にエモーショナルです。 表題作「夜とコンクリート」と「発泡酒」ではフリーハンドで、「夏休みの町」では定規を使った作画になっています。 その中で、異彩を放つのが「青いサイダー」。この作品だけは、全ての絵も書き文字も、Windowsのペイントで描いたかのように直線のみで構成されています。 数多くの漫画作品に触れて来た私ですが、かつて出逢ったことのない画面作りにまず衝撃を受けました。 『夜とコンクリート』P109 > この島はシマさんという > ステレオタイプな島だねと > 人はいうだろうけど > まぎれもなく僕の友人なのだ という、1ページ目から始まる「青いサイダー」。何を言ってるか解らないと思いますが、私も解りませんでした。しかし、このちょっと掴み辛い物語、読み進め、じっくり咀嚼するとその味わい深さに唸らされて行きます。 近年の中でも、町田洋先生は静寂を紙の上に現出させるのが一番上手い作家です。敢えて何も語らせない、キャラクターが無言でいるコマの多さ。そして、どこまでも静謐を感じさせる広漠な風景。それらは謂わばミロのヴィーナスの両腕のようなもので、無限の想いの余地が茫洋として広がり行きます。ぽっかりと開いた空間に夏の匂いと追憶を感じながら、そこに成長と共にある大人になることへの寂寥感、それとコントラストを成す大人として世界の要請に付き合ったが故に生じた後悔といった繊細な情動がもたらされ、胸を締め付けられます。 ■ 今年の夏の傍らに、町田洋を 「夜とコンクリート」「夏休みの町」「青いサイダー」「発泡酒」という四篇によって構成されるこの本は、一冊の短篇集として総体的にも完成度が高いです。「夏祭り」や「夏影 -summer lights-」を夏が来る度に聴きたい曲だとすれば、『惑星9の休日』と『夜とコンクリート』は夏が来る度に読みたいマンガ。 是非、夏の夜に一人静かになれる場所で、町田洋という海に潜ってみて下さい。漫画の世界の無限性を改めて感じさせてくれる、清冽なる才気がそこに輝いています。

早く続きを!
傑作web漫画。 10年近く前にwebで読んでいた面白いマンガが違うweb漫画発の作家の手で改めて漫画にされるということで、懐かしさ半分楽しみ半分で手に取ったけど、やっぱり結構好き。 神とも言われる存在「韋駄天」が数百年に一人の割合で世の中に誕生する。 かつて魔族との大きな争いがあった以後に誕生した「平穏世代の韋駄天達」と、新たに発生し始めた魔族の脅威の話。 「韋駄天」や「魔族」という存在に対するトライアンドエラーの末に至る考察や、その応用、バトルなどスピード感もある見どころがたっぷり。 懐かしさ補正もあるかもしれないが、面白い。 というか刷新されて読みやすくなっているのもいいが、早く更新が止まったwebの続きを読みたい。 原作はコチラ→http://amahara.bob.buttobi.net/
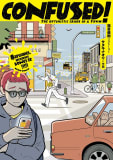
制作陣まとめ「CONFUSED!」
作画『サヌキナオヤ』 イラストレーター・漫画家・アニメーター http://sanukinaoya.com/ ストーリー『福富優樹』 京都在住の4ピース・バンド『Homecomings』のギター https://twitter.com/pizzaplanet_hom 編集『森敬太』 自主制作漫画レーベル『ジオラマブックス』主宰 https://twitter.com/dioramabooks/status/1083992081121460224 マンガっぽくないマンガだと思ったら、編集が音楽イベント開いたりしてた人で、原作者のバンドのジャケットを担当してるのが作画の人…っていう、制作陣は音楽関係者だった

正義も悪役もいない
ストーカーを懲らしめる集団。そこまでは誰でも想像するけど一巻読み終わると「なるほど、そういうことね」と納得する。 行き過ぎたストーカーを止めるのはヒーローではない。 無償で被害者を助けるヒーロー的なものは存在しないということ。 「被害者側」も「加害者側」もこの「ストーカー浄化団」もそれぞれエゴを持ってて最終的に全て綺麗に解決する様、見てて気持ちいいです。 かっこよくも見えてくるし、恐ろしくも見えてくる。

彼女がどういう人間か…
最初はおしかけてきた彼女(斎藤さん)人とズレてるし言動がやばいし好きになれなかったけど回を進めるごとに彼女がどういう人物なのか丁寧に描かれててどんどん好きになってきました;













何という面白さ! 面白すぎる! 凄すぎる!! ルートダブルに本腰を入れ始めた時、私は「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメのリアルタイム視聴すら諦めて、この過酷な世界に徹夜で没入してしまいました。そして、暫くの間うわ言のように「ルートダブル面白い」「ルートダブル面白い」としか言わない、壊れたレディオのようになりました。 「ルートダブル」は、2012年の6月にXBox360で発売されたAVG。今や禁忌とも言える極限状況。知的好奇心を刺激して止まない、近未来における新たな理を描くSF設定。それらが合わさって構築される、濃密な物語。その圧倒的な面白さは、私が2012年に触れた全ての物語の中で最高ともいえるものでした。 ■禁忌の絶望的極限状況 「ルートダブル」は、メルトダウンした原子力施設の中に閉じ込められた9人の脱出劇を描いた物語です。蔓延する放射線、火災、バックドラフト、酸欠空気、殺人……様々な苦難が満ちた地獄の世界で、果たして彼らは生き残れるのか。 このあらすじを聞けば、「福島の事故があったのに、そんな話は不謹慎ではないか」と感じる方もいるでしょう。実際、社会情勢を鑑みて発売中止になるかもしれない、という時期もありました。しかし、この作品の制作が発表されたのは2010年。元々、原発事故の被害者を貶める意志など微塵もなく、むしろ極限状況における人間の希望を描いた作品であるということが強調され、何とか発売されました。私は、この作品が世に出てくれて本当に良かったと思っています。純粋に面白いのは勿論ですし、触れれば悪意を持って創られた作品でないことは明白に理解できます。そして、放射線・放射能・放射性物質やベクレル・シーベルト・グレイの違いといったような知識を改めて学ぶことができる内容、そして作品の中で語られるテーマは今の社会において非常に重要で有用であるからです。 ■視点は「二つ」あったッ! 双極から立体化する物語 「ルートダブル」は、そのタイトルが表す通り、二つの異なる視点から同じ対象が描かれます。√Aは、記憶喪失になってしまった救急隊員の笠鷺渡瀬の視点で、√Bでは母親が研究所の職員である高校生の天川夏彦の視点で。マンガ版でもそれぞれのルートの話が別々に一本の作品として描かれ、単行本も√Aと√Bが二冊同時に発売される形でした。 たとえ見るものが同じであっても、観点が変わればその印象は全く違う……そんな面白さも見事に表現されています。一方的な視点見るだけでは解らない側面。他者の立場に立ってみて初めて解ること。この双方向的な構造それ自体が、批評性を持っています。これ以上ない緊張感溢れるシチュエーションで、二転三転していく物語。何でこんなに続きが気になる所で仕事に行かなければならないのか! と理不尽な怒りすら湧くほどの牽引力でした。この作品に込められた様々な趣向と構造には、思わず溜息すら漏れます。 ■SFの世界が現実に ジュール・ヴェルヌが描いた潜水艦や宇宙船、アーサー・CD・クラークが描いた衛星通信技術、H・G・ウェルズの描いた光学迷彩……優れたSFは、未来への真摯な想像力によって、現実を先取りしすることが多々あります。「ルートダブル」もその好例です。実際に制作中に原発事故が発生してしまった、というのも先見的ですが、この作品では根幹となる部分に一つ大きな設定を導入しています。それが、「Beyond Comminucation(BC)」、いわゆるテレパシーと呼ばれるような能力です。脳と脳による直接的なコミュニケーションが超能力としてではなく、極めて濃厚な科学的考証を経て、社会では普通の存在となった能力として描かれます。「"情報"もエネルギーの一種である」という理論は近年研究が進められ、今作で描かれるような現象も近い将来には実現しているのではないか、と思わされるリアリティがあります。知的好奇心の擽られるSFが好きな人間には堪らない作品です。 ガンガンオンラインのサイト上で1話の試し読みができますので、まずは騙されたと思って触れてみて頂きたいです。商業的な要請から美少女が全面に押し出されてはいますが、中身は実に重厚です。 ただ、この「ルートダブル」は、マンガ版は物語の途中までで完結となっており、事件の全ての真実や、より細かい世界設定などを楽しむためには原作をプレイする必要があります。とはいえ、マンガ版にはマンガ版の魅力も勿論あります。ゲームでは見られなかったアクションやキャラクターの表情・魅力といったものを堪能できるのは、マンガ版の強みです。原作と共に相乗的により深く物語を楽しめる作品として、まずマンガ版から入るも良し、先に原作をプレイして後から読むも良し。現在、PS StoreにてPS3版とVita版の半額キャンペーンが行われていますので、是非とも原作と併せてこの類稀なる傑作として「ルートダブル」の世界をお薦め致します。 ■余談 マンガソムリエを名乗り、あまつさえマンガレビューサイトでこんなことを言っていいのか悩みます。しかし、敢えて言いましょう。こと物語創作において、今最も可能性を持った媒体はノベルゲームではないかと。ヴィジュアル面とサウンド面、そして構造的演出による相乗効果を駆使できながら、映画やアニメに比べれば遥かに低コスト。その気になれば四畳半の部屋で個人単位で制作し、世界を変えて行くこともできます。 原稿用紙数万枚分や単行本数十巻分、あるいは映像にして数十時間分の超大なボリュームの物語をいきなり新人が打ち出すのは極めて困難ですが、ノベルゲームはそういったことも可能にする世界です。今後も、野心的な素晴らしい作品が生まれることを期待しています。 ただ、マンガにおける音声面の補完としては、最近では集英社のVomicや、Domixといった試みもあり、非常に興味深い所です。あるいはニコニコ動画などでも絵が多少動きつつ音声も付けられた作品があり、そちらにも新たな可能性を感じています。ロッキーの練習シーンや、ラピュタ上陸シーンのような、聞けば一瞬でそのシーンを想起するような音楽の力がマンガに付加されたらどうなるのか。Webマンガやスマホで読むマンガが隆盛を極め、マンガ業界も過渡期を迎えている今、どんな形のマンガが今後生まれてくるか、楽しみです。