
転生したらヤムチャだった件

ハルタ47号はハクミコ祭り!
『ハクメイとミコチ』のアニメ化にあわせて、現在発売中のハルタ47号がハクミコ祭りになっている。 付録の「レモンのクレープやさん」は冊子形式の絵本で「ああ、こういうのが読みたかったんや…」ってなるし、巻末の大楠通信ではアニメ設定画が初公開。 あと、最新話ではイワシがかわいくてたまらなかった。

現実世界に揺さぶりをかける
たとえば、いまここに会議室があり、黒いスーツを着た男が6人、大きな四角いテーブルを囲んで、やれ何が正解だ、これが正解だ、いやそれは違う、と不毛な言い争いをしているとする。6人の意見はまるで嚙み合わず、それぞれの手元に置かれたコーヒーカップの中身もなくなろうとしている。 それはもしかすると、ありふれた光景なのかもしれない。 しかしウルトラヘヴンを読んでいると、そんなありふれた光景がなにか異様なものに思えてくる。いや、一周まわって、かえってありふれた光景にもどるというべきか。 6人の意見が嚙み合わないのは、それぞれが違ったものの見方をしているからとみて、たぶん間違いはないだろうと思う。そう、6人が6人とも違った見方で世界を捉えている。 さて、言い争いがヒートアップしてきたようである。ひとりの男が椅子から立ち上がり、テーブルを両の手のひらバンッと叩いた。向かいの男も立ち上がり、手振り身振りをまじえながら、喧しく声を荒立てる。隣の男が宥めにかかるが、それがかえって火に油を注いだようである。その手を乱暴に振り払った。その拍子、コーヒーカップが床に落ち、パリンッと音をたてて粉々に割れた。 手を振り払った瞬間、男にはコーヒーカップが見えていなかったと言わざるを得ない。コーヒーカップは確かにそこにあったのに……。なにもドラッグで視界がグニャグニャに歪まなくても、在るものが無かったり、無いもの在ったりするのは日常茶飯事のことなのだ。各々が(それは人間であっても動物であっても虫であっても地球外生命体であってもいいのだが)各々の目で、脳みそとかそれに準じた器官を通して、世界をみているにすぎないのだ。 いまここに会議室があり、黒いスーツを着た男が6人、大きな四角いテーブルを囲んで、やれ何が正解だ、これが正解だ、いやそれは違う、と不毛な言い争いをしているとする。6人の意見はまるで嚙み合わず、それぞれの手元に置かれたコーヒーカップの中身もなくなろうとしている。 はたしてそれは本当に目のまえに存在しているのだろうか。少なくとも人間である私たちにそれを確かめる手段はない。それは神のみぞ知るところである。

麻生周一のデビュー作
麻生周一のデビュー作。たしか僕が高校生くらいの頃にジャンプで連載をしていましたね。現在連載中の『斉木楠雄のΨ難』は高い構成力で達者なギャグマンガという印象を私は受けますが、勇者学は若さの迸りとでもいうのか、無茶苦茶なギャグが当時の私を虜にしました。 偉大なる悪の伝道師(校長)のホリ高クエスト回は電車で爆笑した覚えがあります。

『それ町』の好きなところは、みんな違ってみんないい
ミステリあり・ギャグあり・ホラーあり・SFあり・人情ありと、石黒正数先生の好きなものを詰め込んで嵐山歩鳥に全部体験させたようなマンガですね。(過去の短編を読んでの感想) そういう意味で、例えば、それ町ミステリ派など「どんなそれ町が好きか」で派閥も生まれうるのではとか考えたりします。私は、断然、それ町人情派。歩鳥のお節介でアホでバカだけど底抜けに優しい人柄がよく現れるところはいつもグッときます。特に、裏切られた過去から人と距離を置くようになった紺先輩を目にかける歩鳥は最高です。これだけでもう16巻出して欲しいほど。 私は人情ですが、ミステリ・ギャグ・ホラー・SF・人情、なんでもござれな作品なので、読んだ人それぞれの好きなそれ町が見つかると思います。

『駿河城御前試合』藤木源之助・伊良子清玄の因縁を描く
山口貴由といえば、型破りなオリジナリティが持ち味かなと思います。『覚悟のススメ』や『衛府の七人』は特にそれが顕著で、台詞回しに展開、キャラクターどれを取っても類を見ない。 しかし、山口貴由の代表作の一つであるこの『シグルイ』は南條範夫の『駿河城御前試合』を原作にしているということもあり、きっちりとした型にハマった印象を受けました。そのため山口貴由のオリジナリティがズシンと響く重たさを持っています。まるで空手の形を見ているような美しさです。藤木源之助・伊良子清玄の因縁、剣に生きる人々の生き様、重厚なストーリーには何度読んでもため息が溢れます。 それにしても、山口貴由の描く狂気はなぜあんなに絶望的なんでしょうね。岩本虎眼がいたから、三重は美しくとも夜這いをかけられなかったと説明が入るところでは、思わずそりゃそうだと吹き出しました。

テンプレでもいいのだ面白ければ
デスゲームが流行りだしてから〇〇ゲームみたいな名前の漫画が粗製乱造され、バナー広告映えするので「面白そうだな」と興味がわいていざ読んでみるとうーん…ってことも多いです。 勿論なかには面白いのもたくさんあって、そのうちのひとつがトモダチゲームですね。ストーリーやゲーム性などはライアーゲームに近い感じですが、ライアーゲームよりはルールがすっきりしていて読み易い印象。ときどき悪魔じみた友一の底知れなさに裏で眺めてた運営の人が「こいつ何者だ…」みたいな感じでざわつくのが、お約束ではあるんですが楽しいですw 「神さま」「アクマゲーム」が終わってマガジン本誌にはこういうのリアアカくらいしか残ってないので、そろそろ補充してほしい頃ですね。

あだち充作品は夏になると読みたくなる。
甲子園も始まって、夏本番といった感じですが、甲子園が始まるとあだち充作品が読みたくなります。 今、連載中のMIXは月刊誌なので、一ヶ月次の連載を楽しみに待っています。MIXは家族関係が複雑で、恋愛模様も複雑になっていきそうです。この作品には今までのあだち充作品んの要素がいろいろMIXされているらしいのですが、タッチやクロスゲームみたいにキャラがこの先に死んでしまうかもしれないという不安がすごいです。H2のひかりのお母さんが死んだ時も悲しかったですが。あと、台詞やコマの使い方もオシャレであだち充ってすごいなぁって思います。

出オチかと思いきや最後まで面白い1巻
表紙とタイトルのてんちょうがとにかく可愛いのだが、主人公やまわりの脇役もいいキャラしてるので、思ってたより出オチ感はなく楽しく読める。 俺物語のポジションを狙っているのかも?二番煎じにならないように舵取りするのが難しいだろうなぁとも(笑)いろんなパロネタが似合うのはてんちょうのアドバンテージですかね

映画みた?
原作好きで見るか迷っているうちに公開が終わってしまった…… 日本アカデミー賞の優秀賞?をとったらしい。DVD借りてみるか…… http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160118-00000572-san-movi

お客様は仏様
タイトルに興味を惹かれて読みました。 死人が行く先を決めるため訪れる「死役所」。短編で、その人の生前、死んだ場面を紹介していく感じです。1話ずつが短くてさっぱりしています。 私はいまいち物足りないかなと思いましたが、徐々に役所職員の謎が明らかになってきたのでとりあえず早く最後まで読みたいです。

現代社会への絶望の最果て。あなたの最大の後悔は何ですか?『空也上人がいた』
何たることでしょうか。 新井英樹先生が絶望しておられる……! 新井英樹という作家は、「漫画で、俺のペン一つで、世の中を変えてやる!」という気概が紙面から迸っている、極めて稀少な描き手です。その卓抜した筆勢は、『キーチ!!』やその続編『キーチVS』、『ザ・ワールド・イズ・マイン』、『SCATTER』などを是非読んで頂きたい所です。 いずれも圧倒的な作品であり、今世紀で好きなマンガを十作品選ぶなら、『ザ・ワールド・イズ・マイン』と『キーチVS』の二つ新井英樹先生の作品は入ります。必然的に私の中で新井英樹先生は現代でも最も注目度の高い作家となっています。 その新井英樹先生の最新作が、山田太一先生の小説を原作とするこの『空也上人がいた』です。この単行本を手にとって、私は大きな驚愕に包まれました。 最初のページを捲ると、何と上記の作品群を引用しながら9・11や3・11を経た世界への絶望に暮れる新井英樹先生自身がプロローグとして描かれているではありませんか! > 狂気が世の中への「反撃(カウンター)」として存在できたのはまだ世の中が少しは正常と思えたからで、今の狂気の世の中に喰らわす「反撃」を捜すと倫理、道> 徳ぐらいしかない!! > そう…思ってたんですけどねえ。本気で。あったまわるいから。 > 「世のため」なんて旗ふったつもりで、期待しすぎてこのザマですよ。 > 絶望っ だね 絶望… > 別に使命感とかじゃなくなんか嫌で嫌で… > オレなんかよりずっと売れて影響力ある人が描いてくれてりゃって思ってたんだけどね > 「ファンタジーなんて描いてる場合じゃない」ってアニメの巨匠だって言ってるじゃん > グローバリズム コーポラティズム カネカネカネ > 世界は金持ったキ●ガイと飼われたいブタだけ > そうだよオレあれもこれも全部嫌いだよ > 世界なんか滅べ!! もう知るか!! あんなに政治家の汚職を、検察の腐敗を、大企業の卑劣を、米国への従属を、クロスオーナーシップを、新聞特殊指定を、ありとあらゆるタブーを恐れず踏み込んで批判して来た新井英樹先生が! 文字通り、大切な「云」うべく敢えて「鬼」と化して絶大な魂を紙面に落とし込んで来た新井英樹先生が! 怒ることを忘れた日本人に喝を入れ、怒りを思い出させようとして来た新井英樹先生が! こともあろうに、あまりにも深い諦観に駆られている……! 現代社会における良心、希望の篝火のような存在が、遂にこの世の巨悪と狂気、弱さと同調圧力の奔流に屈してしまう時が訪れてしまったのか……そんな悲しいことはありませんでした。 大多数の人が見て見ぬ振りをしてやり過ごすことを処世術とする中で、自らへの不利益を省みなずに声を上げる勇猛さ。真っ当であれ、という極めて純度の高いメッセージ。それらが全て敗北してしまったとなると、私自身も絶望の深淵に沈まざるを得ません。 しかし、そんな魂を賭した長きに亘る闘いの果てに至った絶望、その先に描かれた本書もまた圧倒的に素晴らしかったのです。 **介護に携わる若者、キレる** 今作は、タイトルだけ聞くと歴史物のような印象を受けるかもしれませんが、現代社会の問題を描いた一冊完結の現代モノです。 特別養護老人ホームで働いていた27歳のヘルパー青年・草介は、毎晩叫び狂う老婆に対しある日キレて車椅子から突き落としてしまいます。そして、その6日後にその老婆は死亡。自責の念に駆られ職場を辞めた草介は、同僚の46歳ケアマネージャーから紹介された81歳の独居老人の在宅介護を始める、というのが今作冒頭の筋書きです。スーパーのレジ打ち並の収入で280円の牛丼を食べながら、人の命を預かる過酷な仕事、金持ちの老人の世話を行う若者像というのは、現代社会の様々な物の象徴です。 2014年現在、介護職員は150万人。少子高齢化社会の日本では、2025年までには職員数が250万人必要、つまり100万人の介護職員を増やさねばならない、という試算もあります。しかし、激務であり責任も重大な仕事内容でありながらも、その待遇は恵まれているとは言い難い状況です。一刻も早くこの現状を打破せねばならない、。現場で働く末端の介護職員の給与を増やし、負担を減じる方向に持って行かねばならない、ということは多くの人が痛感しながらも、決定的な方策を打つことができていない状況です。一方で、お金を持った老人相手のビジネスとして介護を認識し、食い物にして巨利を得る悪質な輩も跋扈しており、闇は深いです。 介護の大変さは、私も多少解ります。私自身、祖父の介護を数年にわたって行っていました。祖父は、私がこの世で一番尊敬する人物でした。聡明で、物腰が柔らかく何があっても決して怒らず、優しく諭してくれる人でした。70歳を超えても毎日二時間の散歩と運動を欠かさず、自炊によりバランスの取れた食事で健康を保ち、そしてあらゆる物事への好奇心が旺盛でした。触ったこともないTVゲームにも付き合ってくれて「何事も経験。何でも積極的にやってみること」と幾度となく教えられたことも、私の中で血肉となっています。 しかし、そんな祖父も認知症を患ってしまうと、深遠な知識も高潔な人格も、全てを失って行きました。下の世話などはまだ全然良いのです。それより何よりも、話をしても何をしても意思を通わせることができない虚無感・絶望感というのは凄まじいものです。その中で生じる負の感情に、介護をしている自分の不寛容さを曝け出され突き付けられることも伴って、自分自身も精神を苛まれ、蝕まれ、病んで行きます。悪意が無いと解ってはいても、繰り返される様々な蛮行に、苛立ちや憎しみすら抱く瞬間が全く無かったと言い切るのは難しい程です。生涯で最も尊敬する人物をしてこんな感情を抱いてしまうのですから、赤の他人である老人の介護をしている方々の心的ストレスはいかばかりかと思ってしまいます。 作中で、女性ケアマネージャーが > 介護やってれば気持じゃ何百遍もほうり出してるよ。 と語る通りでしょう。 日々、心身を傷付け抉られながら、一方で命を預かっているという緊張感。その状態が何年、何十年と続くのか全く先の見えない状態。その抑圧を、原作者の山田太一先生は「キレないはずがないというのもちょっとひどい言い方だけれども、キレても不思議はない」と実際の取材で感じた体験を元に、この作品を著したそうです。今後の社会で重要なテーマであるにも関わらず、こういったことを描いてくれている作品は寡少なので、私はよくぞ描いてくれたものだと思います。 「後悔」と「他者の眼差し」 今作はノンフィクションの介護小説としてでなく、老人が後悔に苛まれる傷付いた青年を救う物語として描かれたことで、介護というテーマは勿論ですが、それに留まらない普遍性を獲得しています。その軸となっているのは、「後悔」。きっと、誰しも人生の中での最大の後悔というものがあるはずです。その後悔と、人はどう付き合い、どう向き合っていけば良いのか……。 主人公の27歳の草介は、おばあさんを一時の激情に駆られ、それが原因かどうかははっきりとは判らないものの、人を死に至らしめてしまったという罪悪感に囚われます。一方で、彼が出会う81歳の老人もまた、長い人生の中にある一つの大きなわだかまりを抱いています。 そこで、一つの象徴として登場するのが、タイトルとなっている空也上人です。踊り念仏や六斎念仏の始祖であり、疫病で多くの死体がその辺りに転がっている時代の中で、様々な公共事業に勤しんだ聖人。その空也上人の立像というのは、他の多くの彫刻や仏像と違い、顎を上げかすかな声で「南無阿弥陀仏」を唱えながら、前を見て歩いている。それは、罪を許してくれるのではなく、同じようにへこたれて共に歩んでくれるものなのだ、と。 そのようにして、自身が大きな感銘を受けた空也上人立像を、老人は青年に見せようとします。そして、六波羅蜜寺で青年が空也上人立像と対面した時の描写は、小説版でも漫画版でも一つのクライマックスとなっており、必見です。その眼差しは、草介を通して読者をも刺し貫いてきます。 思うに、この世界で生きる際に「他者からの眼差しに晒されている」という意識があるのとないのとでは全く違う次元に存在するようなものです。それは、世界の多くの国々では宗教と呼ばれるものでもあります。日本人は宗教性は薄い民族ではありますが、「お天道様が見ている」とか、「壁に耳あり障子に目あり」といった言葉にそういった精神性は散見されます。 誰も見ていないからといって、不善をなす。多くの人は経験していることでしょう。しかし、その犯した罪は消えることはありません。何らかの他者性を内在させることでその罪の芽をあらかじめ摘み取ることができるなら、それは現実的に推奨されるアティテュードなのではないでしょうか。眼差しを投げかけ、共に歩んでくれる、あなたの「空也上人」を。 そうして生きて行った先には、予想もしなかった新しい展開が開け、そこは想像もできない心地良い場所になっているのかもしれません。そんなことを思わせてくれる物語です。ラストは、表紙を一見した時のような何とも言えない優しさに彩られています。 ある意味で、これはドストエフスキー『罪と罰』の現代日本版であり、一つの返歌と言える作品かもしれません。 **結び** モンやキーチのような圧倒的カリスマは、この物語には出て来ません。ここには普通の人の、普通の現代社会の生活の中での有り触れた想いがあるのみです。しかし、それが静かに深く胸の奥底を叩き、貫いて行きます。それは言うなれば高級料亭で食べるシメの雑炊のように。見た目は地味でありながらも、それまでのあらゆる豊潤な食材のエキスを吸収して生み出される余りにも豊かな旨味に溢れていたのです。山田太一先生の原作に忠実でありながらも、確かに新井英樹作品としての生命の鼓動を感じます。私の中では今年の作品の中でも確実にベスト10に入ります。 今作の巻末に収録された、原作者山田太一先生と新井英樹先生の一万字対談には、こんな注釈もありました。 > 『キーチVS』については、漫画に主義や思想はいらないというご批判を多々受けました。そんなこと言ってるから、漫画は3・11や原発で、映画や小説の後塵を拝したじゃないか。 この一文に込められた気概に、私は喝采を送りたいです。 今作を描くに至った新井先生が、現在とんでもないことになっている『SCATTER』をどう着地させるのか。そして、その次は一体どんな作品を生み出すのか。今後も新井英樹先生の漫画表現による社会・世界との鬩ぎ合いを、心から応援していきます。

6巻発売 ヒロインは西片説が私の中で有力になりつつある
中学生の甘酸っぱい恋愛がかわいらしいマンガだけど、ちょっかい出す高木さんよりもいちいち照れてる西片がかわいくてしょうがない。 ご飯を食べに行くといえば駄菓子屋でカップラーメンだし、放課後に石蹴りしているし、宝の地図を見つけて喜んでいるしあまりにもかわいくて、ヒロインは西片でいいじゃないかと思ってしまう。 ウォータースライダーで無心になっているところが最萌でした。

細野不二彦の新連載
※ネタバレを含むクチコミです。

週マガ移籍記念
※ネタバレを含むクチコミです。

次巻完結ということで読んでみた
次巻完結ということで読んでみた すごい面白いんだけど、古狼(主人公)は飴菓子っていう植物?(ちっちゃい女の子)を食べないといけないっていうのは、面白いんだけど辛ーいって思った。

別れる前後に何が起きてるか
恋愛だけじゃなくて友情も含めて、人と人がすれ違う様子を描いた短編集。自分(男です)の体験と照らし合わせると「あの時やばかったんかもな」と思うような場面が出てくる。 女性と付き合ってから男がちょっとお洒落な店とか料理を知って行く一方で、女性は「小規模ビストロバルとか食傷気味」ってなるの、めちゃくちゃ笑った。でも5話の舞台になってる「SUNDAY BAKE SHOP」はマジでうまいし老若男女問わず絶対喜ぶ!
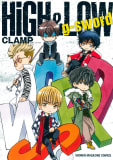
CLAMPのHiGH&LOWはゆるいぞ!!
扉絵見て察しだけど、超緩かった笑 スピンオフ漫画って感じでゆるゆるしている
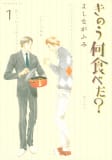
主婦におすすめ
最近初めて読みました。すごくほのぼのしたグルメ漫画でした。 イケメン弁護士のキリッとした史郎と、乙女な美容師の賢二。 2人の独特な空気感が良いですね。 料理はほぼ史郎が作りますが、スーパーでの材料選びから調理、残り物や次の日の献立なども全て考えられていて、しかも基本的に節約しつつ合理的に進めるので主婦の方には大変参考になるのでは…と思います。 個人的には同性愛カップルの楽しそうな生活が覗けるのは楽しいです。

仕事に疲れたら読む
これでいいんだと思える。どうもね!

何もかもリセットしたい時に
常識にとらわれない人の強さ、その人が退屈な日常にもたらしてくれる刺激、でもそういう人にもそういう人なりのしんどさはある、というのが描かれている。自分が生きる上で大切なものって何なのか、自分はどうありたいのかを考えさせられた。 最後に大島弓子の「ロスト ハウス」から一節が引用されているのだけど、合わせて読むとその鮮やかな対比に痺れます。

ORIGINからは生きるってなんだろうと考えさせられる
超高性能の人工知能を搭載したロボットORIGINが、製作者の最後に残した言葉「ちゃんと生きていけ」を全うするために人間社会に溶け込もうとする話。 ORIGINはロボットらしく「一般的にこういうとき人間は…」と考えてから行動に移す。誰かの命を守るときも「ちゃんと生きる、そのためにこの状況では…」と彼がちゃんと生きようとするプロセスが言語化されている。特に3巻は顕著だった。 SF設定が細かくてため息が出るし、バトルは激しくてカッコ良いのだがこの漫画の1番好きなところは、ORIGINがちゃんと生きようとする姿を通して、私も生きるってどういうことだろうって考えられるところ。

『レンチンガール』二駅ずい 別冊少年マガジン9月号 2017年
『彼女はろくろ首』の二駅ずいの読み切り 今度は電子レンジが主人公の男にはギャルっぽい女の子に見えているようで、レトルトのカレーとかを食べる時は彼女が温めてくれるっていうまたフェチをくすぐるマンガ。 女の子が可愛くなるシュチュエーションを考えるのがうまいね

AKBは正直あまり知らないんすけどね
アイドル戦国時代の昨今で、トップクラスのグループを題材にしたマンガなんて商業路線に乗っかり過ぎじゃないか?と思ってたんですが、夢やら希望やら想いやら、オッサンが忘れてるモノを思い出させてくれる良い作品です。 一生懸命頑張ってる人は気持ちが良い。






転生したらヤムチャだった件 すごいな。原作がちゃんと鳥山明ってとこも。。 http://plus.shonenjump.com/rensai_detail.html?item_cd=SHSA_JP02PLUS00005918_57