今はその国で戦争が行われている。
戦争前は聞いても覚えられなかった地名。 すっかりわかるようになっていた。 キエフ、チェルノブイリ通り。 戦争がある日常が通常となってしまっている国。 読んでいて思い出したのは、その戦争が起こる前、コロナよりも前、まだスマートフォンもなかった頃。 原発跡地がある街に、ガイガーカウンターとともにバイクで出かけ、自然に帰ろうとする街を写真に撮っていた女性(たしか女性だった)のホームページがあった。 森に飲まれつつある、時が止まった美しい街だけど、これほど線量がある。ここから先は行けない。 など、写真とともに彼女は書いていた。 そのホームページに、街の手前、まだ放射線量が高い地域に、よそへ越さず、昔からの生活を続けている家族がいたとも書かれていた。 線量の高いものを食べる、それがなんだ、この土地から離れたくないのだと言っていた。 あの人たちは今どうしているんだろう。 さて、漫画に登場する人たちの行動に、どうしてそんな恐ろしいことを!と思ってしまう。 でも、そもそも知らないのだし、放射線も放射能も見えないからわからないのだし。 自分も言われなければ同じことをしているのだろうし。 未来人はやるせない気持ちにしかなれない。 読んでみて、第一話が鮮烈な印象を残してくれたのだけど、その中でも街の人がバタバタと亡くなっていく様子が淡々とした描写で、なんともそら恐ろしかった。 そして主人公の女性が少しでも幸せに今を生きるのはどの方法だったのか、考えてしまった。 口述史というのは非常にセンセーショナルなものだけど、この作品も類に漏れず、読んだ人に思うことを残す激しさがある。








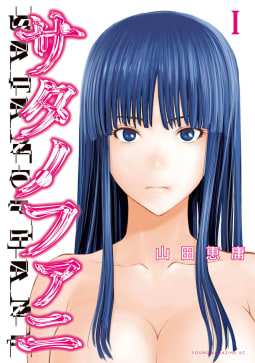



![ICHIGO[二都物語]](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_365,q_auto,w_255/https://manba-storage-production.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/book/regular_thumbnail/168214/b3c3d112-b303-42dc-b7a2-e3bc11642bb6.jpg)




















この作品読んでいると
「無学無知故に」被曝者を放射能の化け物と珍獣扱いしたり差別する悪意の塊の連中と
「無学無知故に」汚染された牛乳や作物を売ったりお裾分けしようとする善意の老人達も過程が違うだけでどっちにしろ他人を苦しめてるのは同じというのが悲しいくらい滑稽でした
そして学のある人達は放射能の危険をちゃんと理解してても恐怖政治で真実を言えなかったり被害報告書を上層部の意向に沿うように誤魔化したりで
民主主義の国じゃないと学があっても何も意味ないんだなっていうのも