
可愛い

テロを生き延びたマンガ家が示す「描く」ことの意味
ここ10年くらいのあいだに、自伝やエッセイぽいバンドデシネのスタイルが、フランス語圏を中心に広く市民権を得ています。 ヨーロッパのマンガといえばメビウスやエンキ・ビラルのような、ゴツめのSFのイメージがいまだ根強い気もしますが、もっと生活に身近なテーマで軽く読める作品が近年増えているんですね。 そのなかでもダントツに「重い」実話マンガが本作。 新聞社シャルリ・エブドで風刺マンガ家として仕事をしていたカトリーヌは、打ち合わせに遅刻したことで偶然ISのテロリストの襲撃から逃れ「生き延びる」ことに。 その日から彼女の苦しみが始まります。 昨日まで一緒に机を囲んでいた仲間のマンガ家たちがみな殺されてしまったというのに、これまで通り世の中を笑い飛ばす作品を描くという、それこそ冗談のような状況で仕事をしなければならないのです。 さらに当事者のカトリーヌの心は置き去りのままに、「JE SUIS CHARLIE(わたしはシャルリ)」の鬨の声が各国であがり、いち風刺新聞であったシャルリがテロとの戦いの急先鋒に祭り上げられ世界デビューする始末。(これも悪い冗談!) そしてカトリーヌは記憶を失ってしまいます。 シャルリ・エブドがなぜ差別行為とも取れるようなドギツイ風刺を行うのか、どんな存在なのか、なぜISがターゲットにしたのかなど日本ではなかなか想像しづらい部分がありますし、いい/悪い、被害者/加害者といった単純な構造で説明できる問題ではないと思います。 僕が心を打たれたのは、彼女が再びペンを取って本作に描いたのが、犠牲となった同僚のマンガ家たちが、生きて、誠実に表現をしていた姿だったことです。 シャルブやヴォランスキといったレジェンド作家たちが築き上げてきた、シャルリというマンガの牙城に自分も加わっていたという誇らしさが表明されているのです。 壮絶な境遇におかれた彼女にしか、この「描くこと」への誇りを「重さ」をもって、世の中に投げかけることは出来ないように思います。 手塚治虫先生は『マンガの描き方』のなかで差別を行うことの卑劣さと、創作することの尊さの両方を説いています。 カトリーヌはその混沌の渦中で命を拾い、創作の手綱と仲間を失いました。 彼女は今も立ち直れていないといいます。 それでも立ち上がるために「軽く」あろうと、描くことをやめず、「美なるもの」を求める彼女の精神は、この世界で間違いなく尊ばれるべきもののように思えるのです。

リクエストをよろしく感想
波よ聞いてくれもいいけどこっちもいいじゃん!? なんかおもしろそうだったので1巻読んでみました。 結構ラジオ好きなのでこういう制作の裏側には興味あるのですが、ああいうラジオ収録ブースを前にした時の感動はわからないなぁ〜…と思います。 でもこの作品で主人公に感情移入してラジオブースの見開きページ見た時心踊りました。 楽しいんだろうなこの現場は! すごい昔に地元のラジオ曲に潜り込んだ時のことを一瞬思い出しました。 単純に喋りがうまい主人公がそのままパーソナリティになってもあんまし面白くない気するのですが、波よ聞いてくれも、リクエストをよろしくも、こういう意外な人物、しかしその辺にいそうな人物が喋りをやるってとこがいいですね。 ずっと喋る仕事、よくよく考えるとすごい仕事だなと思います。話題性にとんだ内容でないといけないし、考えてもいなかったような話題を振ってくるリスナーもいるだろうし。 色々想像膨らむ漫画かと思います!

男性でも気軽に読める少女漫画
男性でも気軽に読める少女漫画です。 恋愛恋愛してないので手始めの1冊、入門に最適だと思います。

東村アキコ先生の自伝マンガ
作者のめちゃくちゃな青春時代を包み隠さず描いているので、なかなか自分の黒歴史をここまで描ける人いないぞっ!と圧倒されました。そしてギャグも楽しいので、一気にラストまで読めます! 病気になった先生が言う「描け」は心にぶっ刺さりますし泣きますね。

ハイスクールバトラーななえ!最強! #読切応援
前号の喫茶とらんぽりんに続き、今号も独特の世界観に魅了された!ぜひとも連載してほしい!
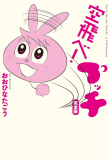
プリンセスに掲載されていたはず
純粋な少女漫画として読もうと思ったら、痛い目にあいます。 主人公プッチ以外にも濃いキャラクターたちがたくさん出てきます。 プッチのお母さん、うさぎなのにちょいエロに見えるのは私の目が腐っているから?

美しいが故の不幸を描かせたら右に出る者はいない
こんな生きてるだけで人を不幸にし、そして自分も不幸になる人って泉さんしかいないでしょう。 度々出てくる変装(仮装?)が最高です。 泣いてばかりの泉さんだけど、キャラが強すぎる友達に支えられて、果たして幸せな未来は訪れるのか? 最終巻まで猛スピードで読みきれます!

本格特撮百合マンガ「ヒロかん」始動!
悪の組織を追われた元怪人女幹部が女ヒーロー(※顔がいい)に助けられてイッパツで恋に落ちる。 展開に無駄がなくていいですね。そういうのでいい。そういうので。 そしてスーツや怪人のデザインが超秀逸で、「わかってる」感が滲み出ている。 特に主人公の颯ちゃんが変身する「ラピッドラビット」がめちゃカッコイイんですけど わかりすぎているがゆえに某ライダーとモチーフがドカブリする始末。 (※因果関係はないらしいです。当たり前だ!!) 個人的には敵対していた者同士がタッグを組むことのアツさを使って もうちょいシリアス展開も見たい気がするんですが 今のゆるっとイチャラブコメディの雰囲気も絶対的に維持してほしい…。 なんて贅沢な悩みだ! そういうのが全部盛ってあるカツカレーみたいなマンガです!ごちそうさまでした!おかわり!!

何者かになりたかった、なれなかった人へ
38歳、ふと高校生に撮った華子という同級生の女の子の写真から「何者かになりたかった」あの頃を思い出す。青少年期の感傷が年相応に色褪せて描かれている。そこには特別な強い想いがあるようには描かれていない。もはや遠い思い出だからだ。だからこそリアリティがある。 「あの頃」があった全ての大人に響くであろう作品。

美しく爆笑をかっさらってく! #読切応援
美形男子高校生とバブリーな美女幽霊のコメディー! 二人とも美男美女なんですけど、どっちもちょっとおバカなのがいいですね。作中たくさんある小ネタがふいにどツボにハマるので油断できません。個人的には姉ちゃんの趣味が「魚肉ソーセージの金具あつめ」にやられました。おもしろいです。
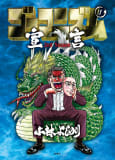
なんでSPAに載ってるんだろう……?
少し前に女子大生記事で炎上した下世話なオジサン向け週刊誌「週刊SPA!」……その誌上において数少ない読み応えのある数ページそれがゴーマニズム宣言w なんといってもこの雑誌、いきなり1ページめから女性への暴行傷害で起訴されているS氏の連載コラムが目に飛び込んでくる下劣ぶりですが、「エセではない真の保守」として世相をぶった切るゴー宣が、イデオロギー的に真っ向から対立しそうなS氏と1冊に同居してるというのは懐が深いというより節操がないようにも…。 ともあれ小林よしのり氏、ああ見えて大変な勉強家のインテリなので話には説得力がありますし、彼自身とは相いれない考え方の人にも一定の理解を示しつつも対比を交え自説を展開する論法は大いに学ぶところがあります。テレビ番組にもネットの掲示板やSNSにも人の話を聴けずに頓珍漢な噛み付きを繰り返す輩であふれかえっているので、彼のようなタイプはとかく誤解を受けやすいですね。もちろん私もゴー宣に書かれている氏の主張になにからなにまで賛同できるわけではないですが理解はできますし、「正論」を構築するのが上手いなぁと感心します。少なくとも冒頭のS氏のいい加減で不勉強な主張よりは遥かに…… ちなみに正論で武装した「ゴー宣」と比べて、FLASHで連載してる「辻説法」はオジサンのしょーもない下世話な本音がさらけ出されていて、これを同じ人が描いているのだから人間って面白いなと感じますw

最高夫婦4コマ
旦那さんのビジュアルの「どうしてこうなった」感はありますが 4コマ界のベストカップルといえばこの2人です。 この夫婦って元教師とその教え子なので、何を禁断の恋しちゃってんの、もう! という感じです。 全10巻、全く飽きずに読み終えられます。

相変わらずでホッとした
正直、買って読むべきか悩んだけれど…タラレバ1巻を読んだ時に受けた雷に打たれたような衝撃をまだ忘れられなかったので読みました。相変わらずの三人がそこにいてよかったです。 元彼たちがみんな仲良くなっているのもお決まりっぽくていいと思います。 リターンズを読んで、やっと自分の中で完結してくれた、と感じました。

グロテスクだけどどこか芸術的
この作品の魅力は表紙の美少女マリアの、地獄のような心象風景の表現だと思います。ホラーはホラーでもジワる的なものとは違い、シンプルに怖い、そしてものすごく気持ち悪い。 このマリアと部屋の秘密は何なのか、というミステリーでもあるのかと思いきや、終わり方は思ったよりあっさりでした。

panpanya世界が現実を飲み込んでいく
まずはじめに、panpanyaさんの作品を読んだことがないという方。この段落で一旦回れ右して、取り急ぎ今作ではなく、著者のページから過去作を手に取って見てください。個人的には「足摺り水族館」もしくは「蟹に誘われて」が入り口としては良いのでは無いかと思います。 panpanyaさんの作品は、一度見たら忘れられない圧倒的な書き込み量とその書き込みによって生み出される現実とも非現実とも付かない摩訶不思議な世界観が最大の魅力です。過去5冊の単行本ではその世界観を余すところなく展開していましたが、今作ではそこから1歩踏み出した感じがあります。 表題作「グヤバノ・ホリデー」は未知の果物"グヤバノ"との出会いから、それを追い求めてフィリピンまで赴き実食に至るまでのドキュメンタリー風の作品です。 この物語を読んだ時、非実在の存在を描きながら現実・非現実の境目が曖昧になるpanpanyaさんらしい作品なのかと思っていましたが、"グヤバノ"という単語を調べてみて、それが実在する果物と分かった瞬間、物語の見え方が大きく異なってきます。 この物語は、グヤバノを追い求めて海外まで行くという点を除けば、ほぼ全て現実に存在する物が描かれています。これまでのpanpanya作品では実在物と非実在物を織り交ぜて世界の境目が曖昧な作品を描いていましたが、今作では描かれているものは全て実在する、でも世界観は非現実的ないつものpanpanya世界。これは、panpanyaさんが自身の作家性をもって現実を飲み込もうとしている、私達はその過程に立ち会っている。そう思うのは考え過ぎでしょうか。いずれにせよ、panpanyaさんは過去作を含めて線で追っていくべき作家で、そして現在における到達点がこの「グヤバノ・ホリデー」ではないかと思います。

ルポルタージュを通して描かれる様々な"愛"の物語
今作は元々、今はなき幻冬舎「コミックバーズ」で連載されており、そちらで打ち切りの憂き目に遭った後、現在の講談社「モーニング・ツー」に移籍して連載を再開したという少し特殊な経緯を持っています。幻冬舎版は「ルポルタージュ」というタイトルで全3巻、講談社は「ルポルタージュ‐追悼記事‐」というタイトルで現在も連載中で、物語自体は連続していますが、講談社版から読んでも問題ない作りにはなっています。 幻冬舎版から一貫しているのは、恋愛すること自体が時代遅れという価値観の世界とその中で発生したテロの被害者たちの人生を描くというテーマ。これらをルポルタージュ作成のための取材という形で炙り出し、恋愛はもちろん、家族愛や友愛など、広い意味での人の愛を描く物語になっています。 この一貫したテーマ自体が毎回読ませる内容で面白いのですが、幻冬舎版から読み続けていると、逆に幻冬舎から講談社に移籍して変わった部分も見えてきます。 まず1点、幻冬舎版は1話5~60ページ、講談社版は1話3~40ページで構成されており、その結果、幻冬舎版では1つ1つのエピソードが重厚に、講談社版は物語の展開がよりドラマチックに動くようになっているように感じます。その辺りの雰囲気の違いを読み比べてみても面白いかも知れません。 そしてもう1点。幻冬舎版は新聞記者の1人、絵野沢(幻冬舎版2巻の表紙の人物)の視点が中心となって展開していきます。非・恋愛系の両親を持ち、その価値観に多く触れてきた彼女の物語は、物語の設定に沿って"恋愛"というものにフォーカスして展開、彼女のモノローグもかなり私的に寄っている印象があります。 その物語が、打ち切りの影響もあるのか幻冬舎版で一旦の結末を見せ、その後の講談社版ではもう1人の新聞記者・青枝聖(同1巻表紙)と、その恋人・國村葉を中心として展開していきます。2人の物語は、世界観に反して"恋愛"をしているという観点から語られる部分もありますが、それにとどまらず、テロの被害者のエピソードも内包したもっと大きな愛の物語へと拡大しているように感じてなりません。言わば、幻冬舎版の3冊の物語を土台に、より包括的な、懐の深い物語になろうとしているのではないかと思うのです。 一度は打ち切られた作品ではありますが、皮肉にも次巻で「MAMA」の巻数に追いつき、作者最長の作品になりつつあります。それに適う作品であることは保証しますので、興味を持って頂けた方は、是非土台となる幻冬舎版「ルポルタージュ」から手に取ってみてください。 2巻まで読了

原作ファンなので読んだ
高校時代に原作を読んで超ハマった作品。 内戦が起き海外マフィアや移民が流入し、孤児・暴力・貧困が身近にある日本。 孤児ながらもキチンと住所と定職を持ち弟妹を養っている主人公が、突然拉致され少年兵としての人生を歩むというストーリー。 1巻だけ読んだけど、生い立ちなどのブ厚い背景設定をバッサリカットして、兵士としての戦闘に重きをおいた構成になっていた。 太くて力強い線が独特の雰囲気があって良かった。

食道楽「YながFみ先生」の日常!
よしながふみ先生の描く漫画は、念入りに食事・調理シーンが描写されていることが多い。 西洋骨董洋菓子店、きのう何食べた?は料理をメインテーマにしているから、描写が細かいのはもちろんのこと、法律がメインテーマの1限めはやる気の民法でも藤堂が田宮のために朝食を作ったり、しっぽりした居酒屋で誕生日を祝うなど表現が際立っていて、「ああ、この人は本当に好きで食事シーンを描いているんだな〜」と、こだわりぶりに感心していた。 だからこそ、よしながふみの描く食事をテーマにした「半エッセイ的漫画」があると知った瞬間、Amazonで即注文…!(※紙しか出てない) 「こんな細かい食事描写を描く人は、いったいどんな食生活を送っているのか」。その理由を知ることができるとワクワクしながら読んだ。 読んでみると、よしなが先生はご自分で料理もされるし、お付き合いする相手については、「食事についてアレコレ感想を共有できる。美味しい食事をするためにわざわざ足を伸ばすことができる相手じゃなきゃ無理」というエピソードがあり、「ああ、やっぱりね。食へのこだわりの強い人なんだ…!」と、バッチリ腑に落ちた。 (回らないお寿司屋さんでの注文の仕方は、ぜひ真似しようと思います!) 主人公は「YながFみ先生」であり、「よしながふみ先生」ではない非実在漫画家と理解しつつも、いち読者としてはいったいどこまでが本当の話なのか興味が尽きない作品。

漫画の枠を超えて評価できる一冊
映画化おめでとうございます! これを読めば生理のことがすべてわかるよ、という漫画ではないですが、 こんなに女性に寄り添った漫画をつくってくれたことに感謝しかないです。 実際にこの表紙の生理ちゃんが家に来たら嫌だし邪魔だけど、生理ってそういうものでした。 ノーベル賞差し上げます。

離婚、拒食症の娘、ボケた母…だけどたかこの人生はこれから。
好きなもの、好きな人ができるといろんなことを頑張れる、という気持ちは理解できるけど、45歳の冴えないおばさんをここまで変えるほどのことって、ただ事ではない。 はたから見てるととにかくたかこの言動は痛々しいのだが、実際には誰もが一度は感じたことがある痛みばかりで、たかこの逆境に立ち向かう姿に「無理あるよー」と思いながらも目をそらすことなんてできない。 心を病んで拒食症になった娘に懸命に寄り添う姿も、若手のバンドのラジオを少女のようにときめいて聞いている姿も、どちらも一生懸命生きるたかこの姿だ。 入り込みすぎてなんかこっちまで足腰が痛くなりそうになる。笑

ほのぼの夫婦が食べる!東京実在の名店グルメ
サブタイトルにおウチで作るとありますが、 どちらかというと紹介されているお店に実際に行ってみたい、と思わせる内容でした。実際に日本橋のだしのお店に行きました! クリエイターの夫と編集者の妻という組み合わせが萌えます。 入江先生はこういうキャッキャした女性を嫌味なく描けるのがすごいですね。

満身創痍すぎるピュアラブストーリー
読めば誰でも、ピュアでまっすぐな(頭がおかしい、とも言えますが)キャラクターたちの虜になり、終わってくれるなと祈るほどになります。正直二巻で終わってしまったのが惜しすぎる。 主人公の山田が磯貝さん(表紙の女性)に恋をすることで、普通の人間であれば一発で命を落とすようなアクシデントに巻き込まれ、包帯まみれがデフォルトとなってしまうのですが、人間離れした純粋な心と鈍感さを持っている山田は、何があっても怒らない、逃げない、辞めない。磯貝さん大好き。狂ったように好き。 この本で描くのは磯貝さんと山田のラブストーリーだけではなく、 人間と山羊、生首とヤクザ、ヤクザと生き別れ森で一人生き抜いた息子との再会など、様々な垣根を超えて人間関係が交錯します。 個人的には、ヒロインの体臭が野生の熊と同じくらい臭いというのがツボでした。 試し読みをしてもらえばわかりますが、コマ割りとタッチが独特です。 時に、笑わせようとしているのか、真剣なのかどっち?と考えてしまいますが、何も考えずに読むのがいいです。 どのカテゴリーにも含まれない、読んだことのない漫画を読みたい!という人にオススメします。

藤末さくら先生の新作
普通にリア充な主人公が、サイコパスな年下美少年のいとこに絡め取られていくサスペンス。この作品が普通の少女漫画で連載されていたなら、ヒーローの狂気に気づかないまま『同居した年下美少年に溺愛されて困ってます』的なラブコメになる気がする。











小学生の時にちゃおで読んで、当たり前のように動物が喋っていたので衝撃を受けました。 ルドルフっていう犬がイケメンです。ずっとほのぼのしてるので安心して読めます(?)