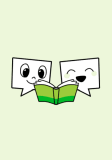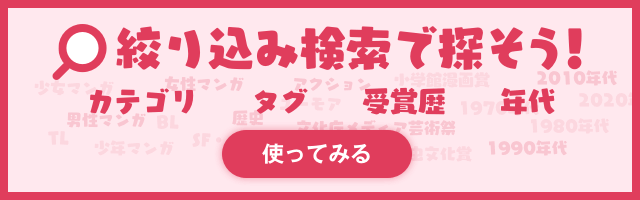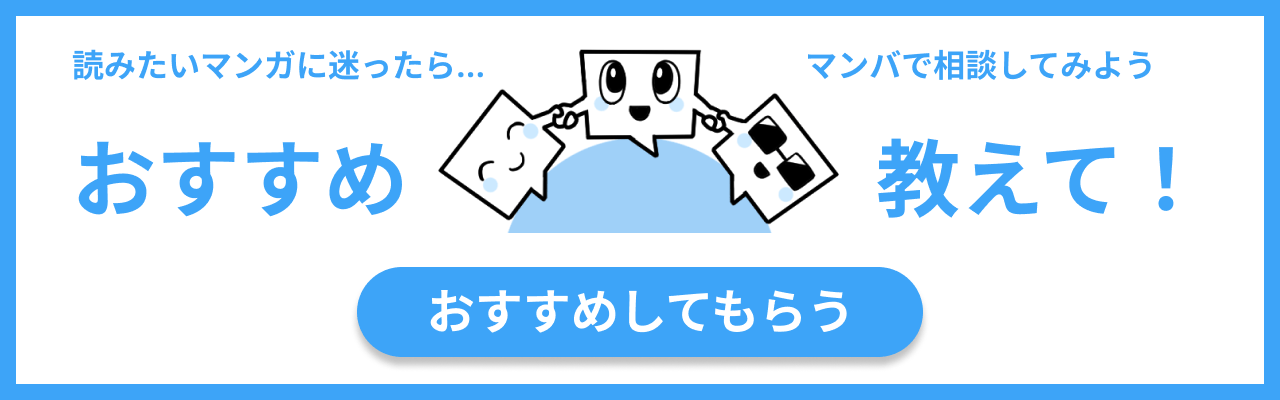(とりあえず)名無し
1年以上前
望月三起也で一番好きな漫画、というと、どうしてもこれが思い浮かんでしまう。
キャリアの長いかたで、ぶっ飛んだ名作・傑作・異色作がたくさんありますし、なんと言っても自動拳銃の排莢を描かせたら、まったくもって誰もマネが出来ないほどカッコイイ漫画家さんですから、そりゃあ『ワイルド7』も最高に決まっているのですが(「排莢の瞬間」がカッコイイんですよ。これは映画とか他媒体では描写不能。漫画だけに、望月三起也だけに可能だった絶品のアクション描写です。鳥山明も排莢描くの上手いけど、別にカッコよくはない)、なんか、この、銃も戦車もバイクも出てこない「チャンバラ時代劇」が、すごく好きなのです。
ぞろっとした新選組の段だら模様に、ギラっと冷たく光る本身…いやあ、良いなあ、チャンバラだなあ!
巻数も5巻で長くないですし(いや、打ち切りなんですけどね)、癌で余命宣告された時、「『新撰組』のつづきを描く!」と宣言なさっていたくらいですから、ご本人としても思いの強い作品だったのだと思います。(その望みが果たされることは、残念ながらありませんでしたが)
唯一無二の望月ワールドを堪能するのに、実に好適な名作ですよ。
もしそれで気に入ったら、そこから先は、『ワイルド』でも『JA』でも『JJ』でもヨーロッパ戦線物でも『ジャパッシュ』でも、なんでもドンドンいっちゃいましょう!