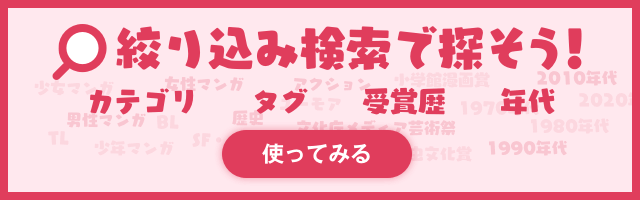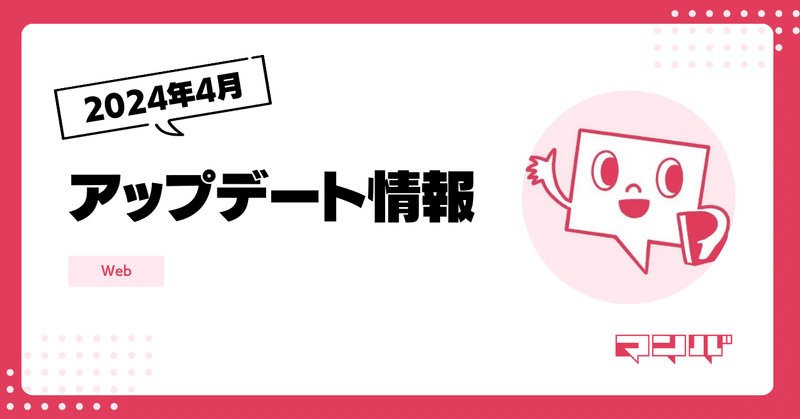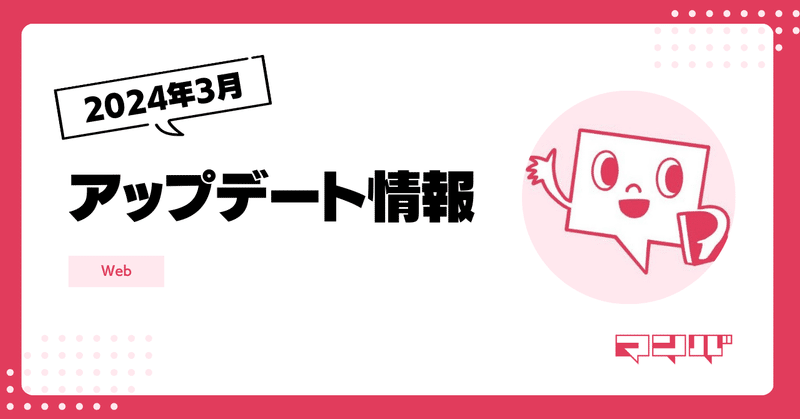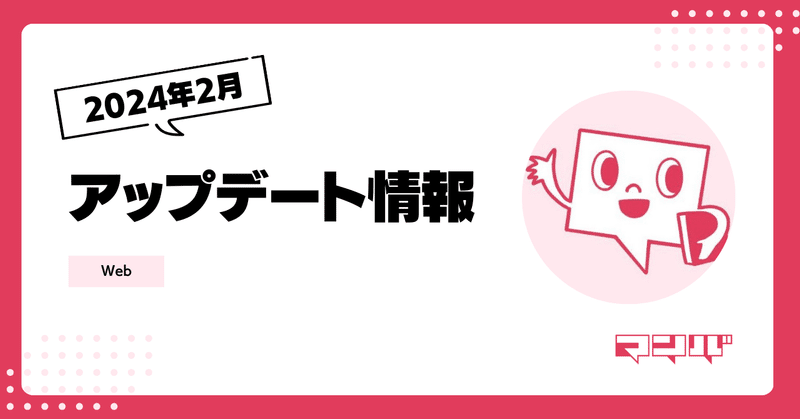今回は「川の人情マンガ」を紹介しよう。つげ忠男の『舟に棲む』だ。
初出は釣りマンガ専門月刊誌『COMIC釣りつり』1996年8月号から2000年5月号。もともとは4部構成の予定で描き始められた長編だが、掲載誌が休刊したためにちょうど2部が完結したところで中断している。第2部の末尾には「発表の場所があろうとなかろうと、描き継ぐつもりでいます」いうつげの決意表明がある。
2部まででも、つげ忠男の中では最大の長編だ。単行本は、ワイズ出版から2巻にまとめられて刊行されている。電子書籍でも読むこともできる。
内省的な中にそこはかとないユーモアを感じさせる兄・つげ義春とは違って、つげ忠男作品のトーンは、代表作『無頼平野』のようにバイオレンスが横溢し、ハードボイルドでクールなものが多い。作品のバックには、つげ兄弟が終戦を迎えた東京都葛飾区立石で経験した混乱期の風景が色濃く現れている。登場する失業者やチンピラ、売春婦、そのほか得体の知れない連中は、つげ忠男が中学校を卒業後に勤めた製薬会社(実態は血液銀行)に、血を売りにやってきた人々がモデルだ。
しかし、『舟に棲む』の全編に漂うのは時代に取り残された人々の情と、去りゆく時代への惜別や郷愁だ。その意味では、異色作と言えるだろう。
舞台は利根川下流の小都市。おそらく、作者が現在住んでいる千葉県流山市だろう。主人公の津田健太は小説家。生まれはつげと同じ1941年。作品上では57歳となっている。
津田がときおり、病弱で癇の強い二番目の父親から毎日のように殴られ、死のうとさえ考えた少年時代を思い出すことなどからも、彼がつげ忠男の分身ということはわかる。小説の中で津田が書いてきたのが戦後の混乱期の立石だったことも語られており、私小説的な味わいも感じる作品になっている。
サラリーマンだった津田は、37歳の時に文芸雑誌で新人賞を受賞したことで人生のターニングポイントを迎えた。津田の妻は夫を小説に専念させるために、今の土地にジーンズショップを開店。津田も39歳で勤めを辞めて筆一本に賭けることを決めた。
しかし、地味な作風のためか小説は売れず、最近の仕事は、エッセイや趣味の釣りに関する雑文ばかりだ。たまに店を手伝うこともあるが、ほとんど役に立たない。本人は日々、「店があるから生活できたんだ なんだかオレはヒモみたいな男だ」と煩悶している。
物語は、津田が川岸につながれていた古い川舟を手に入れるところから始まる。8万円で持ち主の老人から譲り受けたのだ。妻や実質的に店を切り盛りする息子、OLの娘は津田のもの好きに呆れながらも、反対はしなかった。
パイプを加工した簡単な屋根を舟に付け、息子のキャンプ用品を運び込んだ津田は、そこで生活するための準備を整えた。彼の頭には、少年時代に見た船上生活者の姿があった。
月に3日だけでも舟で寝泊まりしながら、長編小説の構想を練るつもりだ、と家族を説得した津田ではあったが……。
マンガは、釣り仲間のトメさんや、投網漁師でのん兵衛の坂本剛馬、坂本に紹介されたスケベな長久寺住職、廃材で河原に廃墟を作ろうとする不思議な男・花村忍、石を売る元マンガ家・金野ら川で巡りあった人々、さらには言霊のような得体にしれないものたちと津田の交流を描きながら進んでいく。彼らに共通するのは高度成長期以降の時代の本流からは逸脱して生きているということだろう。
中でも河川敷の小高い場所の掘っ立て小屋に棲む妙な二人組、利根川北斎老人と彼の弟子・山本写楽青年を描いたエピソードがとてもいい。
北斎老人は太平洋戦争で出征中に妻と生き別れ、終戦後は日本中を漂白するようになった。アメリカ兵を殴り逃れている、と北斎老人は語る。写楽青年は、8年前に老人に出会ってから旅を共にするようになった。
二人は津田の舟を無断で拝借したところを津田とトメさんに見つかり、お詫びとして掘っ立て小屋に津田たちを案内する。小屋から川の風景を眺めながら話を聞くうちに、津田は二人の生き方に惹かれて交流が始まる。
しかし、台風が上陸した日、ふたりは再び風のように利根川の河川敷から去っていったのだった。
「あの小説家も変わった人でしたね 先生 あの人があんな舟の暮らしをする本当の理由は何なのでしょう?」
「さてな………心の闇………人は皆その闇をさまよう旅人なのだよ………」
土手のススキ野原を行くふたりの会話はいつまでも心に残る。
このエピソードに限らず、作品全体には、漠然とした心の闇をゆるゆるとさまよいながら生きていく人間の煩悩が描かれている。
津田は肉体的な衰えを感じ、時には死を意識しながら、それでも小説を書かなければならないと考えている。そして、舟で暮らすことは、書くためではなく、書く事からの逃避ではないのか、と内心気づいてもいる。
2部では、小説をあきらめようかと考え始めた津田にC型肝炎が発見され、ますます死は身近なものになる。一方で、津田が少年時代の下町を描いた作品が映画化される、という展開も待っている。
本作は「流れゆく川のような人情マンガ」として読んでもいいのではないか。